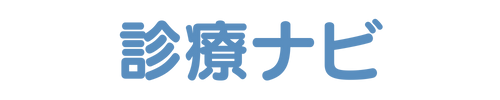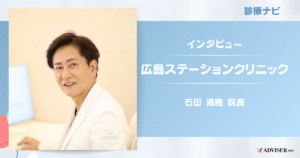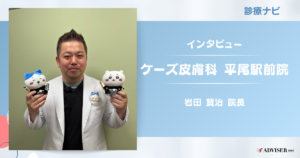2025年9月19日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「健康診断で血糖値を指摘されたけど、どうすればいいんだろう」
「今の糖尿病治療は、自分に合っているのだろうか」
「ただ薬を処方されるだけでなく、もっと自分の話を聞いてほしい」
生活習慣病、特に糖尿病の治療において、このような不安や悩みを抱えている方は少なくないかもしれません。
横浜市鶴見区で70年以上にわたり地域医療を支えてきた「渡辺医院」。
2024年4月、三代目として副院長に就任した渡辺雄祐先生は、大学病院・市中の基幹病院で研鑽を積んだ糖尿病専門医・総合内科専門医です。
祖父の代から受け継がれる「生涯のかかりつけ医」という温かな想いと、専門医としての最新の知見を融合させ、患者一人ひとりの「人生」に寄り添う医療を実践しています。
鶴見で70年。三代目・渡辺 雄祐 副院長が受け継ぐ「生涯のかかりつけ医」としての想い
渡辺医院は1953年の開業以来、三代にわたって鶴見の地域医療を担ってきました。
渡辺雄祐副院長が、この地で医師として貢献したいと考えるに至った背景には、幼少期の経験と、祖父・父から受け継がれてきた想いがあるようです。
ーー渡辺医院は70年以上の歴史があると伺いました。先生ご自身も、この鶴見で生まれ育ったそうですね。
渡辺副院長
はい、そうです。祖父が1953年にこの場所で開業し、父が院長を引き継いで今に至ります。もう70年以上になりますね。私自身、この鶴見で生まれ育ち、小さい頃から祖父と父が地域の患者さんのために働く姿をすぐそばで見てきました。
クリニックに来られる患者さんの多くは、徒歩や自転車でいらっしゃるご近所の方ばかりです。中には2世代、3世代にわたって家族ぐるみで通ってくださる方もいて、まさに地域に根差したクリニックだと感じています。
ーー幼い頃から、お祖父様やお父様の姿を見て、医師を目指そうと?
渡辺副院長
開業医の家に生まれると「跡を継げ」と言われるイメージがあるかもしれませんが、父から医師になるように言われたことは一度もありませんでした。ただ、やはり祖父や父の背中は大きかったですね。地域の患者さんのために尽くす姿を見て、ごく自然に「自分も将来、地域に貢献できる医師になりたい」と思うようになりました。
実は、小学校の卒業文集に「大きくなったら、大病院の部長や大学教授を目指すのではなく、地域の開業医となる」と書いたのを今でもはっきりと覚えています。その頃から、地域医療への想いは全く変わっていませんね。
ーー数ある専門分野の中で、なぜ「糖尿病内科」を選ばれたのでしょうか。
渡辺副院長
もともと高校生の頃から「医食同源」という言葉があるように、栄養や食事に興味がありました。私たちの体は日々の食事から作られますし、食事と医学は深く関連しています。そして、医学部の病院実習で糖尿病患者さんを担当させていただき、私は糖尿病内科を選択しようと思ったんです。糖尿病は、血糖値が上がりやすい食事や飲み物を知らず知らずのうちに摂取してしまい、病状が悪化しているケースが少なくありません。しかし、患者さんが正しい知識を得て、食生活を整えるだけで、薬がなくても劇的に症状や数値が良くなることがあるんです。極端な例ですが、ジュースを頻繁に飲んで血糖値が600まで上がってしまった方が、入院を機にそれをやめただけで、見違えるほど数値が改善することもあります。
その時、「患者さんとの対話が、治療そのものになる」という事実に深く感動しました。心筋梗塞やがんといった病気は、対話だけで治すことは難しい。でも、糖尿病は対話を通じて、患者さんと一緒に良い方向へ向かっていける。逆に言えば、ただ薬を飲むだけでは不十分で、生活習慣の改善も含めた全方位的なアプローチが不可欠です。その奥深さに魅力を感じ、糖尿病内科医を目指そうと決意しました。
「カルテはその人の人生」|なぜ対話を何よりも大切にするのか
渡辺副院長が診療において最も大切にしているのが「対話」です。
その根底には、研修医時代に出会った恩師の言葉と、「病気だけを診るのではなく、その人の人生を診る」という揺るぎない信念がありました。
ーー先生の診療方針である「病を診ずに人を診る」について、詳しくお聞かせください。
渡辺副院長
私が医師としてのキャリアをスタートさせた済生会中央病院での経験が原点になっています。そこに、ものすごく厳しい指導医の先生がいらっしゃったのですが、その先生から「カルテはその人の人生だ。だから、最初から最後まで、全部ちゃんと目を通せ」と教わりました。
当時はまだ紙カルテの時代で、膨大な記録のすべてに目を通すのは簡単なことではありませんでした。しかし、カルテには検査データや治療の記録といった医学的な事実だけでなく、患者さんが外来や入院中に話されたこと、例えば「何に不安を感じているのか」「何に困っているのか」といった言葉も記録されています。その人の性格や考え方、物事の見方までが、そこには詰まっているんです。
その言葉を聞いてハッとしました。カルテは単なる記録用紙ではなく、その人の人生そのものなのだと。私たちは、患者さんの人生の一部を任せていただいている。その責任は非常に重いものだと痛感しました。この経験から、ただ病気を治して終わりではなく、その方の人生に少しでも関わらせていただくという意識を常に持って診療にあたるようになりました。それが、私の考える「病を診ずに人を診る」ということです。
ーー診療の中で「対話」を重視されているのも、そのお考えからでしょうか。
渡辺副院長
例えば、血圧が高い患者さんがいて、薬を飲んでもなかなか下がらないとします。医学的なエビデンス(科学的根拠)に基づけば、薬を増やしてでも血圧を下げるべきです。そうしないと、5年後、10年後に心筋梗塞や脳卒中といった大きな病気になるリスクが高まってしまいますから。
しかし、患者さんには「これ以上薬を増やしたくない」というお気持ちがあるかもしれません。その時に、「エビデンスがあるから薬を増やしましょう」と一方的に進めるのは違うのではないかと思っています。それは医療者の独りよがりです。
ーー患者さんが治療に前向きになれない背景には、何か理由があるのかもしれない、と。
渡辺副院長
はい。そこで私は、「どうして薬を飲みたくないのですか?」「何かご不安なことがありますか?」と、まずはお気持ちをしっかりとお聞きします。そうすると、「以前、薬を増やしたら血圧が下がりすぎて、ふらふらした経験があるんです」といった答えが返ってくることがあります。
その一言があれば、こちらも「なるほど、それはご不安でしたね。では今回は、作用が穏やかな別のお薬から試してみませんか?」と、患者さんの不安を解消できるような新しい提案ができます。
このように、患者さんと同じ目線に立ち、難しい医学的な事実を分かりやすくお伝えし、患者さんが心の底から納得してくださって初めて、治療は前に進むのだと考えています。対話がなければ、患者さんの本当の気持ちは見えてきません。だからこそ、私は何よりも対話を大切にしているのです。
地域医療の要として|顔の見える連携で患者さんを守るネットワーク
渡辺医院は、クリニック内での診療にとどまらず、地域の基幹病院と密に連携することで、患者さんに切れ目のない医療を提供しています。
専門医としての深い知見と、地域に根差したクリニックならではの「顔の見える関係」が、患者さんの安心を支えています。
ーー地域のかかりつけ医として、他の病院との連携はどのようにされていますか?
渡辺副院長
はい、近隣の病院の先生方とは、色々な会で顔を合わせる関係です。またそうした日頃からのコミュニケーションはもちろんですが、「サルビアねっと」という横浜市の医療情報ネットワークにも参加しています。これは、同意を得た患者さんの採血データや画像検査の結果などを、地域のクリニックと中核病院とで共有するシステムです。これにより、よりスムーズで質の高い医療を提供することが可能になります。
ーー特に済生会横浜市東部病院や川崎市立川崎病院とは、深いつながりがあると伺いました。
渡辺副院長
はい。済生会横浜市東部病院は、2007年の開設時から当院と密接な関係にあり、院長である父も地域連携医として大変お世話になってきました。また糖尿病治療では全国的にも有名な病院で、糖尿病の教育入院(糖尿病について学びながら治療を行う入院)を積極的に行っており、そこで症状が落ち着いた患者さんを当院で引き継がせていただくケースも増えてきました。
また川崎市立川崎病院は、2021年に慶應義塾大学病院からの出向で赴任し、3年間密な診療を行いました。糖尿病・内分泌内科としてだけでなく、当時は新型コロナウイルス感染症の重症化が問題となっており、次々と入院される重症患者さんを一主治医として必死の思いで治療していたのを思い出します。川崎病院へは現在も週1回、糖尿病内科外来に非常勤として勤務させて頂いております。
「渡辺医院にも糖尿病専門医がいる」と認知していただくことで、インスリン治療など、専門的な管理が必要な患者さんでも、ご自宅の近くで安心して治療を続けていただけます。大規模病院から紹介していただけるというのは、当院への信頼の証でもあり、大変光栄に感じています。
糖尿病治療の常識を変える|専門医が語る「納得」と「二人三脚」のアプローチ
糖尿病専門医である渡辺副院長は、その治療においても「対話」と「患者の納得感」を重視しています。
画一的な指導ではなく、一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添ったオーダーメイドの治療が、ここ渡辺医院の大きな特徴です。
ーー糖尿病の治療というと、食事制限が厳しくて大変、というイメージがあります。
渡辺副院長
よくそういったお声を聞きますね。もちろん食事療法は糖尿病治療の基本ですが、当院では「あれはダメ、これもダメ」というような一方的な指導はしません。大切なのは、患者さんが無理なく、楽しく続けられることだからです。
例えば、外食やコンビニ食が多い働き盛りの方には、主食・主菜・副菜のバランスを意識する工夫をご提案します。「甘いものやラーメンは絶対に食べてはいけませんか?」というご質問もよく受けますが、私は「量と頻度次第ですよ」とお答えしています。大好物を完全に禁止するのは、あまりにもつらいことですから。患者さんとお話ししながら、「糖尿病が悪化しない範囲での量と頻度」を一緒に見つけていくことを心がけています。
ーー患者さんご本人の努力だけでは難しい側面もありそうですね。
渡辺副院長
おっしゃる通りです。ご家族の協力も非常に重要です。以前、他の病院から来られた患者さんで、治療を中断してしまった理由を尋ねたところ、「一方的に『食べ過ぎだ』と言われるばかりで、話を聞いてくれなかった」と打ち明けてくださった方が多くいらっしゃいました。中には、それほど食べ過ぎていないのに体質的に血糖値が上がりやすい方もいて、言われのない差別(スティグマ)に苦しんでいるケースもあります。
当院では、そうした患者さんの辛い経験にも常に思いを馳せながら、血糖値が上がってしまった背景を一緒に考えます。「何かご本人が言いづらいことや、困っていることがあるのではないか」と。ご家族が目の前でお菓子を食べてしまう、善意で勧められた健康食品が実は糖質が多かった、など、原因は様々です。その根本原因にアプローチしない限り、本当の解決にはなりません。
ーーお薬に関しても、患者さんの意思を尊重されていると伺いました。
渡辺副院長
はい。食事や運動でコントロールが難しい場合は薬物療法を検討しますが、その際も「この薬を出しておきます」ということはしません。糖尿病の薬には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
ですから、「今のあなたの状況ですと、Aという薬とBという薬が考えられます。Aはこういう特徴があって、Bはこういう利点があります。どちらに興味がありますか?」というように、複数の選択肢をご提示し、患者さんご自身に選んでいただくようにしています。ご自身の体に入るものですから、どんな作用がある薬なのかを理解し、納得した上で治療を始めていただくことが、治療を継続する上で非常に重要だと考えているからです。
渡辺医院の肥満外来|専門医だからこそできる手厚いサポート体制
渡辺医院では、これまでの診療に加え、新たに「肥満外来」の準備を進めています。
背景には、画期的な治療薬の登場と、肥満症に悩む多くの人々を専門医として正しくサポートしたいという強い想いがありました。
ーー最近、マンジャロというGIP/GLP-1受容体作動薬が「痩せ薬」として話題になっています。先生は、こういった薬をどうお考えですか?
渡辺副院長
GIP/GLP-1受容体作動薬はこれまでの常識を覆すような、非常に画期的な薬だと考えています。食欲を抑えるだけでなく、血糖値も改善する効果が期待でき、万病の元と言われる肥満を解決に導く可能性を秘めています。
ただ、現状では課題もあります。これらの薬が保険適用となるのは、肥満によって高血圧や脂質異常症など、健康障害を合併した「肥満症」と診断された場合です。そして、保険診療で処方を受けるには、多くの場合、基幹病院などの認定施設で半年にわたる栄養指導などを受ける必要があります。本当に肥満症で苦しんでいる方にとって、このハードルは決して低くありません。
ーー美容クリニックなどで自費診療として処方されるケースも増えているようです。
渡辺副院長
そうですね。しかし、美容目的で安易に使用されることには懸念を抱いています。これらの薬はもともと糖尿病治療薬であり、副作用が起こる可能性もゼロではありません。副作用が起きた際に、非専門のクリニックでは十分な対応が難しいケースも考えられます。
そこで当院では、専門医の管理下で安心して肥満症治療を受けていただける「肥満外来」を始めようとしています。保険適用の条件を満たす患者さんを対象に、半年間待つことなく、よりスムーズに治療を開始できる体制を整えたいと考えています。
ーー渡辺医院の「肥満外来」では、具体的にどのようなサポートが受けられるのでしょうか。
渡辺副院長
ただ薬を処方するだけではありません。薬物療法と並行して、専門的な栄養指導や運動指導も行います。急激な体重減少は、脂肪だけでなく筋肉も落としてしまい、かえって不健康な状態を招くことがあります。
そのため、当院では定期的に体組成計で筋肉量などをチェックし、筋肉を維持しながら健康的に体重を減らせるよう、トータルでサポートしていきます。私たちは糖尿病治療薬としてこれらの薬を熟知していますから、万が一副作用が出た際にも迅速かつ適切に対応できます。このサポートの手厚さが、専門医である我々の強みです。
鶴見区を中心に地域医療の未来を見据えた渡辺医院の挑戦
70年以上の歴史を持つ渡辺医院ですが、その歩みを止めることはありません。
渡辺副院長は、地域住民がより質の高い医療を受けられるよう、未来を見据えた新たな挑戦を始めています。
ーー今後のクリニックの展望についてお聞かせください。
渡辺副院長
当院はご覧の通り、非常に年季の入った、いわゆる「昭和のクリニック」です(笑)。しかし、より良い医療を提供するために、2026年2~3月頃を目処に電子カルテを導入する予定です。これを機に、「昭和から令和のクリニック」へと、大きく刷新を図っていきたいと考えています。
電子カルテが導入されれば、オンライン診療も可能になります。当院は最寄り駅から少し距離があるので、アクセスが難しい方にも診療をお届けできるようになります。特に、生活習慣病や睡眠時無呼吸症候群の治療のように、定期的な通院が必要な方にとっては、大きなメリットになるはずです。
ーーその他に、何か新しい取り組みはお考えですか?
渡辺副院長
現在、健康診断の結果を入力すると、未来の動脈硬化のリスクがどのくらいだと推定されるか計算できるチェッカーをホームページで公開しています。検査結果は、ご自身の体のことです。結果をもらって終わり、ではなく、まずは患者さん自身に興味を持っていただくことが健康への第一歩だと考えています。
さらに糖尿病を始めとする生活習慣病の患者さんに対してはN・Partnerさんのオンライン栄養指導を導入しております。特に忙しい方にとっては、オンラインで患者さんの都合の良い時にスマホで受けられる点は、非常に画期的だと感じております。
また、ホームページも、単なるクリニック紹介ではなく、患者さんのための「復習ツール」として活用していただきたいですね。診察室で説明を聞いても、忘れてしまったり、分からなかったりすることもあると思います。そんな時に当院のホームページを見返して、「先生が言っていたのはこういうことだったのか」と理解を深めていただく。知識を持って治療に取り組むことで、モチベーションも高まるはずです。
健康に不安を抱える皆様へ、渡辺副院長からのメッセージ
インタビューの最後に、この記事を読んでいる皆様へ、渡辺副院長から温かいメッセージをいただきました。
ーー最後に、読者の皆様へメッセージをお願いします。
渡辺副院長
まずは、ご自身の健康に少しでも気を配っていただけたら嬉しいです。日頃感じる些細な症状や、ちょっとしたお困りごとが、大きな病気のサインである可能性もあります。どんなことでも構いませんので、お気軽に当院へご相談ください。
当院は、風邪や腹痛といった一般的な内科診療から、糖尿病や高血圧、肥満症などの生活習慣病、そして甲状腺の病気といった専門性の高い領域まで、幅広く対応しています。地域の皆様の健康の窓口として、最初の相談相手でありたいと思っています。
何よりも大切にしているのは、患者さん一人ひとりの人生に寄り添うことです。病気のことだけでなく、ご不安な気持ちや生活の中でのお困りごとなど、何でもお話しください。私たちは、皆様が生涯にわたって元気で健康な人生を笑顔で過ごせるよう、全力でサポートさせていただきます。
渡辺医院
| 診療科目 | 内科、糖尿病内科、甲状腺内科 |
|---|---|
| 住所 | 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目133−2 |
| 診療日 | 院長診療日 (火・水・土)9:00〜12:00 (水)14:30〜18:00 副院長診療日 (月・木・金)9:00〜12:00 (月・火・金)14:30〜18:00 ※臨時で担当医変更や休診となることがあります。詳しくはホームページから最新の「お知らせ」をご参照下さい。 |
| 休診日 | 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日 |
| 院長/副院長 | 渡辺 雄幸 / 渡辺 雄祐 |
| TEL | 045-501-6457 |
| 最寄駅 | JR「鶴見駅」から市営バス「潮田町2丁目」下車徒歩2分、「向井町2丁目」下車徒歩4分 |