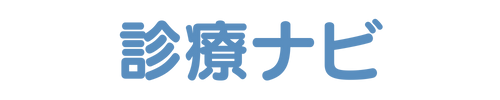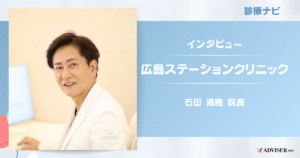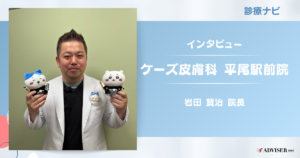2025年10月28日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「健康のために運動しましょう」と内科で言われても、膝や腰が痛くて運動できない……。
でも整形外科で湿布をもらうだけ……。といった悩みを抱えて、いろんなクリニックを行き来していませんか?
そんなあなたにおすすめしたいのが、池尻大橋にある「せらクリニック」です。
今回は、院長の世良 泰(せら やすし)先生にお話を伺いました。世良先生は日本整形外科学会専門医でありながら、内科診療にも精通しています。
整形外科と内科、その両方を深く知る世良先生が掲げるのが、アスリートのためだけではない、真の「スポーツ医学(Sports Medicine)」です。
世良先生がなぜ整形外科と内科の垣根を越えた診療に行き着いたのか、その原点にある想いとこだわりに迫りました。
「スポーツ医学」はアスリートだけのものじゃない。世良 泰院長が医師を志した理由
穏やかな笑顔の奥に、医療への情熱と独自の哲学を秘めた世良院長。
まずは、医師という道を選び、現在のスタイルの礎となった「スポーツ医学」に出会うまでの経緯を伺いました。
ーー先生が医師を目指されたきっかけは、ご自身のスポーツ経験にあるのでしょうか?
世良院長
中学からバスケットボールを続けていました。その中学時代に、成長痛の代表である「オスグッド・シュラッター病」という膝の痛みに悩まされ、ほとんどバスケができなかった時期があるんです。その時に慶應病院で診ていただいたのが、ご自身もバスケ経験者である先生で、「バスケやってるなら医学部で待ってるよ」と声をかけていただいて。その経験から、健康や医療、特にスポーツに関わる分野に興味を持ちました。
ただ、高校生の時に「医学部に行くか、法学部に行って弁護士になるか」で悩んでいました。当時の校長先生に相談したところ、「医学部から法学部へは行けるが、逆は難しい。」とアドバイスをいただき、医学部に進学しました。
ーー法曹界にもご興味があったのですね。医学部進学後はどのようなご経歴を歩まれたのでしょうか。
世良院長
大学1年の4月、バスケの練習中に鼻を骨折しまして。その3週間後くらいに「細菌性髄膜炎」という重い病気にかかってしまったんです。どうやら鼻だけでなく頬の骨も折れており、そこから菌が入ったようで、3〜4週間入院しました。
奇しくも、その時の主治医の先生が、医師と弁護士の「ダブルライセンス」を持つ方だったんです。ただ、お話を伺ってみると「医師に専念した方が良い」と言われまして(笑)。それで、弁護士のことは考えなくなりましたね。
ーーその後にご興味を持ったのが「スポーツ医学」だったのですね。
世良院長
はい。大学でもバスケを続けていたのですが、その中で「人間が健康でいるために本当に大事なことは何か?」と考えた時、私は4つの要素に行き着きました。それは「食事」「運動」「休養」「メンタル」です。
例えば「食事」や「休養」について困った時、病院の何科を受診すればいいか、すぐには思い浮かばないですよね。でも「運動」に関しては、医師として最も深く関わることができる分野だと感じました。
当時、慶應に新設された「スポーツ医学総合センター」という、いわゆるスポーツ整形外科とは一線を画す部門がありまして。本来は学部4年生の自主学習の受け入れ枠はなかったのですが、中学時代に膝を診てくれた先生にお願いして、個別に枠を作ってもらい、そこでスポーツ医学に関わるようになったのが始まりです。

せらクリニックを開業した理由|日本の医療システムへの課題感と「Family Medicine」への想い
研修医時代を経て、整形外科専門医となった世良院長。
大学病院などでの経験を通じて感じた日本の医療の課題と、開業に至った想いを伺いました。
ーー整形外科医でありながら、総合内科でも研修を積まれたのはなぜですか?
世良院長
スポーツ医学を追求する上で、整形外科の知識だけでは足りないと感じていたからです。研修を終えた後、まずは東京医療センターの総合内科で1年間学びました。その後、整形外科の専門医資格を取得しました。
ーースポーツ医学の「本質」とはなんでしょうか?スポーツ医学と聞くと、スポーツ選手の怪我を治すイメージが強いです。
世良院長
それは日本特有のイメージかもしれません。海外、特にアメリカで「スポーツ医学(Sports Medicine)」というと、整形外科だけでなく、「家庭医学(Family Medicine)」や総合診療科、小児科といった分野がベースにあるんです。
例えば、プロスポーツチームに帯同しても、選手が試合中に大怪我をして対応するケースは稀です。「お腹が痛い」「風邪をひいた」「ワクチンはどうする?」といった内科的な対応や、コンディション管理がほとんど。つまり、スポーツ医学の本質は「総合診療」なんです。
トップアスリートは、私たち一般人よりも高いレベルで「食事・運動・休養・メンタル」の管理を求められます。その知見は、スポーツ選手だけでなく、老若男女すべての人の健康に応用できる。私はそう考えています。
ーーまさに、その「日本の医療に足りない部分」を埋めるために開業されたのですね。
世良院長
その通りです。大学病院にいた頃、よく目にした光景があります。例えば、ご高齢で糖尿病と診断された患者さんが、内科で「血糖値が悪いから運動しなさい。1日8000歩、歩きましょう」と言われる。でも、その方は「私、膝が痛いんです」と。
そこで今度は整形外科に行くと、「変形性膝関節症ですね」と診断されて終わってしまう。結局、患者さんは「何をすればいいの?」と路頭に迷ってしまいます。
さらに細かく言えば、糖尿病で「増殖型網膜症」という目の合併症がある場合、激しい運動は眼底出血のリスクがあり、むしろ危険です。当院でも眼底検査を行えるようにしていますが、このように複数の疾患を抱える方を、トータルで診て「あなたに最適な運動」を処方できる場所が、日本にはあまりにも少ない。
大学病院では採算性の問題もあり、こうした診療を続けるのは現実的ではありませんでした。それならば、自分の手の届く範囲で、スポーツ医学の本来あるべき姿、つまり「Family Medicine」に基づくプライマリ・ケアを実践しようと決意し、開業に至りました。

せらクリニックの特徴|整形外科と内科を“同時に”診るということ
「せらクリニック」の特徴は、整形外科的な痛みも内科的な生活習慣病も、世良院長が一人でトータルに診療できる点にあります。
ーー「糖尿病と膝痛」を一緒に診てもらえるのは、患者さんにとって大きなメリットですね。
世良院長
そう自負しています。糖尿病の患者さんが「運動しましょう」と言われても、膝に痛みがあれば適切な運動はできません。当院であれば、まず整形外科医として痛みの原因を探り、治療やリハビリで痛みを緩和させます。その上で、内科医として血糖値や合併症(網膜症など)の状態を把握し、その方に本当に必要な運動療法を処方できる。これが当院の強みです。
もちろん、発熱などの風邪症状、胃腸炎、花粉症といった一般的な内科診療にも幅広く対応しています。「何かあったら、まず“せらクリニック”に行こう」と思っていただける、地域のかかりつけ医でありたいですね。
ーー院内にはリハビリ室も充実していますね。スタッフの方とはどのように連携をしているのでしょうか?
世良院長
リハビリ室には、フィットネスバイクなど、幅広い運動強度に対応できるマシンを揃えています。痛みを抱える方から、本格的なアスリートまで対応可能です。スタッフ(理学療法士)とは定期的にカンファレンスを行いますが、「百聞は一見にしかず」なので、時間があれば私もリハビリ室に顔を出し、患者さんの様子を直接見るようにしています。
診察室で私が「このあたりにアプローチすれば良くなるのでは」と考えていたことと、リハビリのプロである理学療法士の方針が一致することで、患者さんにより良いリハビリが提供できる。この連携は非常に大切にしています。
ーー子どもの成長促進や近視予防などにも力を入れているそうですね。
世良院長
はい。スポーツ医学の視点は、お子さんの成長にも非常に重要です。当院では「成長促進外来」として、低身長のお子さんに対し、医学的な治療だけでなく、運動や日常生活でのアドバイスも行っています。
また、近視予防にも取り組んでいます。怪我の予防、背を伸ばすこと、視力の低下を防ぐこと。これらは大人の治療と異なり、子どもの時期にしかできないアプローチや、知識で予防できることが多くあります。クリニックとして、今後さらに力を入れていきたい分野です。

せらクリニックの運動療法|“わかっているけど、できない”心理への寄り添い方
院長の診療の核となる「運動療法」。
その本質的な価値と、多くの人が実践できない現実の「ジレンマ」に、世良院長はどう向き合っているのでしょうか。
ーーせらクリニックの運動療法について教えていただけますか?
世良院長
有名な言葉で、「もし運動療法を“薬”にできたら、世界で最も処方される薬になるだろう」というものがあります。
高血圧、脂質異常症、糖尿病、そして膝の痛み。これらすべてに有効なのが運動です。もちろんやり方は様々ですが、多くの疾患の予防や改善に寄与するという意味で、私は運動を「ある種の万能薬」だと捉えています。医療や病気に対して、「運動が何ができるか」を考えるのが、私の信じる広い意味でのスポーツ医学なんです。
ーー「わかっているけど食べちゃう」という患者さんの心理を、どうサポートされていますか?
世良院長
当院では、いわゆる管理栄養士による細かな栄養指導は、あえて積極的に行っていません。なぜなら、ほとんどの人は「わかっている」からです。
例えば、目の前にファーストフードと和食が並んでいたら、どちらが健康的か、誰でもわかりますよね。でも、食べてしまう。これは知識の問題ではなく、「構造」の問題です。ですから、私は小難しいカロリー計算の話はしません。それよりも、「なぜ食べてしまうのか」という背景に寄り添い、まずは「できることから始める」ことを提案します。例えば、間食の洋菓子を和菓子に変えてみる。うどんより蕎麦を選ぶ。それだけでも第一歩です。
ーー患者さんと接する上で、一番大切にされていることは何ですか?
世良院長
とにかく「分かりやすく話す」ことです。専門用語は極力使いません。「運動しなきゃ」と思っていても、やれない。その気持ちは私にもよくわかります。だからこそ、ハードルを下げることが大事です。
例えば高齢の方であれば、「家からクリニックまで10分歩いて来る。それだけでも立派な運動のスタートですよ」とお伝えします。まずは「ここに来る」ことから一緒に始めましょう、と。患者さんご自身が納得し、理解して一歩を踏み出せるように、丁寧にお話しすることを心がけています。

せらクリニックのメディカルダイエットと運動|体重より「脂肪」を落とすために
「運動だけでは痩せない」と語る世良院長。
では、痩身治療として注目されるGLP-1受容体作動薬(メディカルダイエット)と運動は、どのように組み合わせるべきなのでしょうか。
健康的に「脂肪」を落とすためのメカニズムを伺いました。
ーー運動をするだけでは痩せないのでしょうか?
世良院長
はい。「運動だけでは痩せません」。例えばボディビルダーは、まず脂肪も筋肉も全部つけてから、最後に脂肪だけを落とします。なぜ脂肪だけ落とせるかというと、厳しい食事制限をしながら運動もすることで、筋肉を維持しつつ脂肪を燃焼させているからです。運動単独で痩せるのは非常に効率が悪いんです。
ーーでは、最近話題の「メディカルダイエット(GLP-1など)」はいかがですか?
世良院長
当院では自由診療になりますが、GLP-1製剤であるマンジャロやリベルサスといったお薬を使うケースもあります。これらのお薬は、脂肪肝にも良いというデータが出てきているんです。ただ、日本では糖尿病以外での保険適用が認められていないため、医療費がかなり高額になってしまうのが現状です。
ーー薬だけで痩せようとするのは、やはり良くないのでしょうか?
世良院長
その通りです。単純に「食べない」という選択をすると、今度は逆の問題が起きます。人間の体は、入ってくるカロリーが減ると、それに合わせて消費カロリーも減らす「省エネな体」になろうとします。食べなくなったのに痩せない、リバウンドしやすい体質になるのはこのためです。
人間の体は、良くも悪くも常に一定の状態(フラット)を保とうとします。例えば、摂取カロリーが極端に増えれば、肌荒れや炎症を起こしてでも消費カロリーを増やそうとしますが、その逆もまた然りなんです。
ーー運動と薬は、どう組み合わせるのが理想ですか?
世良院長
目指すべきは「体重を落とすこと」ではなく、「脂肪を落とすこと」です。薬の力を借りて食事(摂取カロリー)をコントロールしつつ、運動によって筋肉を維持・増強することが必要です。
筋肉が維持されていれば、基礎代謝や活動量が保たれます。その状態で摂取カロリーが減れば、体はエネルギー源として脂肪を使わざるを得ません。これが、健康的に「脂肪だけを落とす」ための正しいアプローチです。

今こそ知ってほしい「脂肪肝(MASLD)」|“沈黙の臓器”からのサインを見逃さない
整形外科のイメージが強い「せらクリニック」ですが、世良院長が今、内科分野で特に力を入れているのが「肝臓」の診療だと言います。
ーー最近、特に「肝臓」の診療に力を入れている理由を教えてください。
世良院長
ここ数年で、肝臓病の概念が世界的に大きく変わってきているからです。特に注目しているのが「脂肪肝」です。2023年から、代謝異常(糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満など)を伴う脂肪性肝疾患は「MASLD(マッスルディー)」という新しい定義になりました。日本人の成人(50歳以上)では約4割が該当するとも言われ、非常に身近な病気です。
ーー「脂肪肝」というと、お酒を飲む人のイメージでした。
世良院長
かつてはアルコールが原因とされていましたが、実際にはアルコールだけでなく、肥満や生活習慣病が大きく関係していることがわかってきました。脂肪肝の何が怖いかというと、「沈黙の臓器」と言われる通り、自覚症状がほぼないまま進行することです。脂肪がたまった状態が続くと肝臓が炎症を起こし(MASH)、やがて細胞が線維化して硬くなる。最終的には肝硬変や肝がんといった、命に関わる病気に進行するリスクがあります。
ーー健康診断では、どんな数値に注目すれば良いですか?
世良院長
AST、ALT、γ-GTPの値です。基準値内であっても、ASTとALTは30 U/l以下、γ-GTPは男性50 U/l以下、女性30 U/l以下に抑えたいところです。もし基準値を超えていなくても、これらの数値がやや高めの方は、一度エコー(超音波)検査をお勧めします。
健康診断の基本的な項目では、脂肪肝をはっきり見つけるのは難しい。だからこそ、「最近太ったな」と感じる方や、健診で指摘された方はもちろん、糖尿病や高血圧を指摘されている方は、ぜひ相談に来ていただきたいです。
ーーせらクリニックでは、肝臓に関してどのような検査や治療ができますか?
世良院長
当院では、腹部エコー検査はもちろん、腹部エコーのエラストグラフィーの機能を用いて、肝臓の線維化の程度を測定することができます。
面白いことに、体が痩せていく時、「脂肪肝の改善」→「内臓脂肪の減少」→「皮下脂肪の減少」という順番をたどることが多いんです。つまり、脂肪肝は生活習慣を見直すことで改善が期待できる、最初のサインとも言えます。「たかが脂肪肝」と放置せず、ご自身の状態を正確に知り、運動や食事管理を通じて一緒に改善を目指しましょう。

「健康を通じて、人々の夢や日常を応援する」|せらクリニックのこれからと読者へのメッセージ
最後に、クリニックの今後の展望と、健康に悩む読者へのメッセージをいただきました。
ーー複数の科を標榜されていますが、どんな患者さんに来てほしいとお考えですか?
世良院長
おかげさまで開業して1年が経ち、今は「整形外科のクリニック」というイメージが強くなっています。もちろん、膝・腰の痛みや四十肩、スポーツ障害などで来られる方も大歓迎です。
しかし、私が本当に実現したいのは、「日常の困りごと」を何でも相談できる場所であることです。内科に行き、整形外科に行き、と複数の病院に通われている方は非常に多い。当院であれば、一般的な日常の症状であれば、その両方を一度に完結できます。
「血圧が高くて、コレステロールも高くて、糖尿病の気もある。さらに膝も痛い」…そういう方こそ、ぜひ来ていただきたい。これらすべての悩みに、「運動」というアプローチが共通して関わってくるからです。

ーークリニックを今後、どのように発展させていきたいですか?
世良院長
クリニックを何院も増やしていく、という考えはあまりありません。むしろ、この「せらクリニック」という医療機関があるからこそできる、事業を広げていこうと思います。例えば、企業向けの運動器ドックや”Wellmoo”といったサービスで運動療法を広げる取り組みをしています。
結局、多くのクリニックが薬を出して終わり、になっている現状があります。それは患者さんにとっても、薬をもらうだけなので楽かもしれませんが、根本的な解決にはなっていません。私は、運動や生活習慣を変える「お手伝い」を通じて、人々が健康になるための“仕組み”や“コミュニティ”を作っていこうと思います。
ーー最後に、体の不調や悩みを抱える読者へメッセージをお願いします。
世良院長
私たちが夢や目標を立てる時、その土台には必ず「健康であること」が存在します。しかし、その健康は決して当たり前ではありません。当院では、「運動」「食事」「休養」「メンタル」という全ての面から、皆さんの健康を応援します。
「もう年だから」と諦めている痛みや不調も、必ず原因があります。内科だから、整形外科だから、と分けるのではなく、あなたという「個」を見て、最も良いと考えられる方法を一緒に考え、取り組んでいけば、きっと解決への道は見えてきます。
丁寧で心のこもった温かい医療を提供し、皆さんが健康な毎日を送れるようサポートしますので、どんな些細なことでも、まずは気軽に「お散歩がてら」ご相談ください。

池尻大橋せらクリニック
| 診療科目 | 整形外科、リハビリテーション科、 内科、肝臓内科、糖尿病内科、アレルギー科スポーツ医学、再生医療、成長促進外来、 健康診断、予防接種、自由診療 |
|---|---|
| 住所 | 〒153-0044 東京都目黒区大橋2-22-42No.R池尻大橋4階 |
| 診療日 | (月・火・木・金・土) 9:00〜12:30 / 13:30〜17:00 (水) 12:00〜15:30 / 16:30〜20:00 |
| 休診日 | 日曜・祝日 |
| 院長 | 世良 泰 |
| TEL | 03-6407-1697 |
| 最寄駅 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」北口より徒歩5分 |