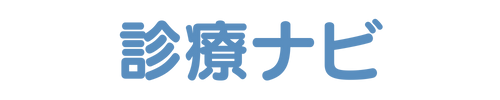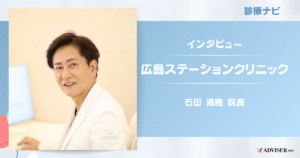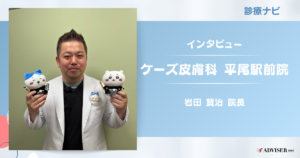2025年10月29日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「乳がん検診、受けなきゃとは思うけど、どこに行けばいいの?」
「もし、しこりが見つかったらどうしよう…」
「大学病院は待ち時間も長そうだし、敷居が高い…」
成城・世田谷区周辺にお住まいで、そんな不安やためらいを感じている女性は少なくないかもしれません。
乳がんは今や日本人女性の9人に1人がかかると言われる時代。
決して他人事ではないからこそ、信頼できて、気軽に相談できる「かかりつけ医」の存在が不可欠です。
今回は、2025年5月に成城学園前駅徒歩2分の地に開院した「成城乳腺クリニック」院長の志茂 彩華先生にお話を伺いました。
この記事では、志茂院長の診療にかける情熱から、高性能な医療機器による精密検査、乳がん治療と密接に関わる「リンパ浮腫ケア」「骨密度検査」、そして大学病院とのシームレスな連携体制まで、同クリニックついて徹底的に取材しました。
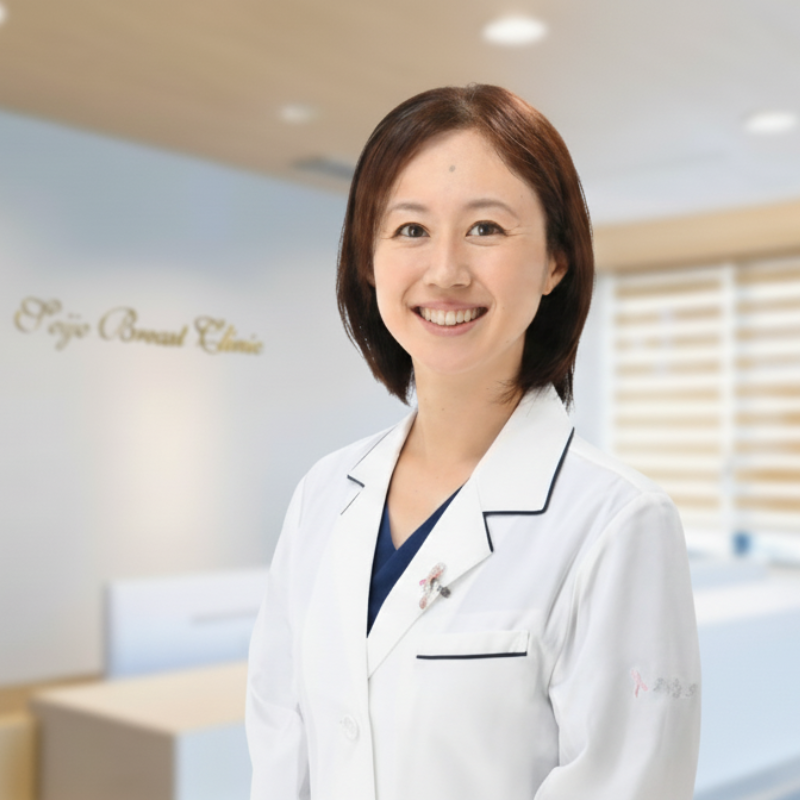
志茂 彩華
成城乳腺クリニック院長。聖マリアンナ医科大学医学部卒。日本乳癌学会 乳腺専門医・指導医、日本外科学会 外科専門医として、乳がん検診から精密検査、術後フォローまで一貫して対応し、リンパ浮腫ケアにも力を入れる。
詳細プロフィール
– 所属・役職:
成城乳腺クリニック 院長
聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンターで外来勤務
聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科 非常勤講師
– 専門領域:
乳癌
乳腺疾患
甲状腺・副甲状腺疾患
乳がん検診
精密検査
術後の経過観察
薬物療法
リンパ浮腫ケア
– 資格:
医学博士
日本外科学会 外科専門医
日本がん治療認定医機構 認定医
日本乳癌学会 乳腺専門医・指導医
検診マンモグラフィ読影認定医
乳がん検診超音波検査 実施・判定医
一般社団法人ICAA認定 リンパ浮腫専門医師
乳房再建用エキスパンダー/インプラント
– 学歴:
2005年 聖マリアンナ医科大学医学部 卒業
– 経歴:
聖マリアンナ医科大学医学部附属大学病院 乳腺・内分泌外科 入局
聖マリアンナ医科大学 外科学(乳腺・内分泌外科):助教/医長 → 講師
聖マリアンナ医科大学附属多摩病院 乳腺・内分泌外科:副部長
成城乳腺クリニック 開院・院長就任
– 学会・役職:
聖マリアンナ医科大学 非常勤講師
– 著書・論文:
『検診発見のDCISの亜型とKi67を含むバイオマーカーの検討』(日本乳癌検診学会 2014)CiNii
『早期原発性乳癌に対する凍結療法の前向き観察研究』(日本乳癌学会学術総会 2024)J-GLOBAL
『一次乳房再建における有害事象の危険因子について多施設共同研究(日本乳癌学会班研究枝園班)』(日本乳癌学会学術総会 2024)J-GLOBAL
その他多数執筆あり
志茂 彩華院長が語る「私が乳腺外科医として、成城の地を選んだ理由」
大学病院で乳がん検診、診断、手術、薬物治療、緩和医療まで、乳腺医療の最前線に20年近く携わってきた志茂 彩華院長。
その豊富な経験を持つ志茂院長が、なぜ今、この成城の地でクリニックを開いたのでしょうか。
その想いと、成城乳腺クリニックの開業に至るまでの経緯に迫ります。
ーー先生が医師を志し、数ある診療科の中から「乳腺外科」を専門に選ばれた経緯を教えてください。
志茂院長
母が看護師をしていたこともあり、医療という仕事がとても身近な環境で育ちました。「人の助けになる仕事に就きたい」と、ごく自然に医師の道を志しました。
大学で学ぶ中で、同じ女性として、女性に関わる科に進みたいという想いが強くなっていったんです。産婦人科やリウマチ内科など、女性の患者さんが多い科を中心に臨床実習を回る中で、乳腺外科に出会いました。
学生時代の勉強では、乳腺外科は比較的コアな分野なのですが、いざ臨床に出てみると、患者さんの数が非常に多く、その需要の高さに驚きました。今や日本人女性の9人に1人が乳がんになる時代です。特に40代、50代という、家庭でも社会でも非常に重要な役割を担っている世代の患者さんが多く、中には30代後半で、まだ小さなお子さんを抱えながら治療に臨まれる方もいらっしゃいます。
そうした方々が病気と向き合い、時には亡くなっていく姿を目の当たりにする中で、「こういう方々のためにこそ働きたい」という気持ちが強く芽生え、乳腺外科の道に進むことを決意しました。
ーー聖マリアンナ医科大学病院で、長く研鑽を積んでこられたのですね。
志茂院長
はい。聖マリアンナ医科大学医学部を卒業後、そのまま大学病院の乳腺・内分泌外科に入局しました。大学病院では、まさに乳腺医療のすべてを学び、経験させていただきました。乳がん検診から、マンモグラフィや超音波による診断、手術、術後の薬物治療(ホルモン治療や抗がん剤)、そして緩和医療まで、幅広い経験を積みました。年間100件以上の手術を執刀し、ブレスト&イメージングセンターでは精度の高い検査や最先端治療にも携わってきました。
乳腺外科の魅力は、患者さんと非常に長く寄り添えることです。他の外科ですと、手術は外科、術後の治療は内科や腫瘍内科、と担当医が変わることが少なくありません。もちろん、それはそれで多くの医師の目で見るという利点はあるのですが、患者さんにとっては「私の主治医は誰なんだろう」という不安につながることもあります。
その点、乳腺外科は診断から手術、術後のフォローまで、一人の医師が一貫して担当することが多いんです。乳がんの治療は10年に及ぶこともあり、その後も定期的な経過観察が続きます。一人の患者さんをずっと見続けることで、その方の性格や生活背景まで深く理解できる。それは私にとって、医師としての大きなやりがいでした。
ーー充実した大学病院での診療の中で、次第に「葛藤」も生まれてきたと伺いました。
志茂院長
そうですね…。大学病院に20年近く勤務する中で、特にここ数年、非常に強く感じるようになったのが、大学病院の「多忙さ」でした。
先ほどお話ししたように、乳がんの患者さんは増加の一途をたどっています。一方で、治療も進歩し、治療期間が長期化する方も増えました。大学病院は多くの患者さんを受け入れていますが、医師のマンパワーには限界があります。
毎日がとにかく忙しく、次の患者さんが待っていると思うと、どうしても一人の患者さんにおかけできる時間が限られてしまう。「もっとじっくりお話を聞きたい」「もっと相談に乗りたい」と思っても、時間に追われてしまう。患者さん側も、待合室の混雑を気遣って、早めに診察室を出ようとされてしまう…。
そんな状況に、「これは本当に、自分のやりたい医療なのだろうか」という疑問を、常に抱えるようになっていました。
ーーそれが、開業を決意された一番の理由ですか?
志茂院長
はい。大学病院の負担を軽減するという役割も担いつつ、「もっと患者さん一人ひとりに寄り添い、手厚い医療を提供したい」という想いが、開業を決意させた最大の動機です。大学病院では、リンパ浮腫(後ほど詳しくお話しします)に悩む患者さんも多くいらっしゃいましたが、なかなか専門的なケアを提供する受け皿がありませんでした。患者さんも私も困っている状況を見て、「それなら自分で専門の資格を取って、クリニックでケアできる環境を作ろう」と考えたのも、大きなきっかけの一つです。
「働き方改革」の影響もあり、大学病院の医師が疲弊していくのを間近で見てきたからこそ、地域のクリニックが専門性を持ち、大学病院としっかり連携することで、大学病院の医師には「大学病院でしかできない診療」に集中してもらう。そうやって、地域医療全体に貢献したいという想もありました。
ーーなぜ、開業の地に「成城」を選ばれたのでしょうか。
志茂院長
私は聖マリアンナ医科大学病院(川崎市宮前区)のほか、新百合ヶ丘にあるブレストセンターや、登戸にある川崎市立多摩病院でも長く診療と手術を担当してきました。ですので、小田急線沿線には非常になじみがあり、私が診てきた患者さんも多くいらっしゃいます。
もし開業するなら、そうした患者さんたちが引き続き通ってくださる可能性のある、小田急線沿線が良いと決めていました。中でも成城は、慣れ親しんだ歴史ある街で、自然が美しく、街並みもきれいで、どこかゆっくりと時間が流れていると感じます。この場所なら、患者さんが安心して、気軽に通い続けていただける「とまり木」のようなクリニックが作れるのではないかと思い、この地を選びました。
開業にあたっては、自治会の方々とも相談し、看板の色やロゴに至るまで、この美しい街並みになじむデザインを心がけました。地域コミュニティーの一員として、皆さんに愛されるクリニックでありたいと願っています。

成城乳腺クリニックの診療内容:「検診の入口」から「専門的な診断」まで
成城乳腺クリニックでは、乳腺に関する初期の悩みから、専門的な診断・検査まで、大学病院レベルの医療をワンストップで提供しています。
具体的な検査内容や、最新の医療機器について伺いました。
ーー乳腺の悩みというと、まず「乳がん検診」が思い浮かびます。どのような検査が受けられますか?
志茂院長
当クリニックでは、世田谷区の乳がん検診はもちろん、自覚症状のない方向けの自費検診も行っています。
検診の基本は、「マンモグラフィ(乳房X線検査)」と「超音波(エコー)検査」です。マンモグラフィは、乳房を圧迫してX線撮影し、しこりになる前の微細な「石灰化」を見つけるのに優れています。一方、超音波検査は、マンモグラフィでは白く写ってしまいがちな高濃度乳腺(若い方や授乳経験のない方に多い)の「しこり」を見つけるのが得意です。
それぞれ得意分野が違うため、両方を併用することで、より精度の高い検診が可能になります。
ーー最新の「3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)」を導入されているのですね。
志茂院長
はい。当クリニックでは、高性能な医療機器の導入に力を入れています。マンモグラフィは、「3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)」という最新の機器を導入しました。
従来の2Dマンモグラフィが乳房を1方向から撮影した「1枚の絵」だとすると、3Dマンモグラフィは、乳房を多方向から撮影し、そのデータを再構成して「複数の断層画像(スライス画像)」を得る技術です。
これにより、乳腺組織に隠れて見えにくかった小さながんを発見しやすくなったり、逆に乳腺の重なりをがんと見間違える(偽陽性)ことが減ったりと、より正確な診断が期待できます。

ーー「しこりがある」「痛みがある」「分泌物が出る」など、自覚症状がある場合はどうすればよいでしょう。
志茂院長
乳腺に何らかの自覚症状がある場合は、「検診」ではなく「保険診療」となります。まずは不安がらずに、お早めにご相談ください。
しこりや痛みといっても、その原因は乳がんだけではありません。良性の「乳腺症」や「線維腺腫」、「のう胞」などであることのほうが圧倒的に多いのです。
まずはマンモグラフィや超音波検査でその「しこり」の正体を確認することが大切です。当クリニックは院長をはじめ、検査を担当する放射線技師も、スタッフ全員が女性です。安心してご相談いただければと思います。
ーー検査の結果、精密検査が必要となった場合の「針生検」とは、どのような検査ですか?
志茂院長
画像検査で「しこり」が見つかり、良性か悪性(がん)かを経過観察だけでは判断が難しい場合、「針生検(はりせいけん)」という検査を行います。これは、局所麻酔をした上で、しこりに直接針を刺し、組織の一部を採取して顕微鏡で調べる検査(病理検査)です。
当クリニックでは、この針生検においても「吸引式針生検(マンモトーム生検など)」という、より確実な診断が可能な機器を導入しています。これは、通常の針生検よりも太い針を用い、組織を吸引しながら採取する方法です。
一度の穿刺で、より多くの組織を採取できるため、診断の精度が格段に上がります。大学病院などで行われることの多い検査ですが、これをクリニックレベルできる体制を整えています。
ーー検査結果は、当日にわかるのでしょうか?
志茂院長
マンモグラフィと超音波検査の画像診断の結果については、検査当日に私から直接ご説明します。ただし、針生検を行った場合の病理検査の結果は、専門の病理医が顕微鏡で詳細に調べるため、1〜2週間ほどお時間をいただきます。結果をお伝えする際は、非常に重要な局面になりますので、必要に応じて「ご家族の方もご一緒に来てください」とお声がけしています。診断結果や今後の治療方針など、お伝えすることが多くなるため、患者さんお一人で受け止めるのは大変な場合もあるからです。
女性の生涯に寄り添う「骨密度」と「リンパ浮腫ケア」という強み
乳がんの治療は、手術や薬物治療だけでなく、その後の人生とも密接に関わってきます。
成城乳腺クリニックでは、乳がん治療の副作用と関わりの深い「骨粗しょう症」と「リンパ浮腫」の専門的なケアに、特に力を入れています。
ーー乳腺クリニックで「骨密度検査」が重要視されるのは、なぜですか?
志茂院長
乳がんの治療、特にホルモン治療(女性ホルモンの働きを抑える治療)を受けている方は、その影響で骨密度が下がりやすく、骨粗しょう症になるリスクが高まることが知られています。また、女性は年齢とともに誰でも骨密度が低下しやすい傾向にあります。
骨粗しょう症は「サイレント・ディズィーズ(静かなる病気)」と呼ばれ、骨が弱くなっていても自覚症状がありません。そしてある日、転んだだけで骨折してしまい、そこから寝たきりになってしまう…ということも少なくないのです。
ですから、乳がんの治療中の方や経過観察中の方はもちろん、閉経後の女性は、定期的にご自身の骨密度をチェックし、予防していくことが非常に大切です。
ーーこちらの骨密度検査は、被ばくがなく、腰椎と大腿骨で測定できる「超音波」だと伺いました。
志茂院長
従来の骨密度検査は「デキサ(DXA)法」といって、腰椎や大腿骨(足の付け根)の骨密度をX線で測定する方法が主流でした。これが最も信頼性が高いとされています。
そこで当クリニックでは、クリニックでの導入はまだ珍しいとされる、超音波(レムス法)を用いた骨密度測定装置を導入しています。この装置の最大の利点は、被ばくが一切ないことです。そのため、妊娠中の方や、短期間で繰り返し測定したい方でも安心して検査を受けていただけます。
超音波でありながら、X線を使うデキサ法と同様に、最も重要な「腰椎」と「大腿骨」の骨密度を測定でき、デキサ法との高い相関性も認められています。もし骨密度が低下している場合は、お薬(カルシウム剤やビタミン剤)の処方や、骨密度を上げるための注射・点滴治療も当クリニックで一貫して行うことができます。
ーーもう一つの大きな特徴である「リンパ浮腫」のケアについて教えてください。
志茂院長
これは、私が開業する上で、どうしても実現したかったことの一つです。乳がんの手術では、がんの広がりによって、脇の下のリンパ節も一緒に切除(リンパ節郭清)することがあります。リンパ節は、リンパ液の流れをせき止める「関所」のような役割をしているため、これを取ってしまうと、腕から戻ってくるリンパ液の流れが滞り、腕や手がむくんでしまう「リンパ浮腫」という合併症が起こることがあります。
ーーリンパ浮腫は、一度発症すると治らないのでしょうか?
志茂院長
残念ながら、一度発症すると完治は難しく、生涯にわたるケアが必要とされています。最近は手術の方法も進歩し、リンパ節をなるべく取らない(センチネルリンパ節生検)ようになったため、発症する方は減ってきています。
しかし、中には何十年も前に手術を受けられ、ずっとリンパ浮腫に悩まされている方も多くいらっしゃいます。利き手がむくんで日常生活に支障が出たり、重くだるい感覚が続いたりと、そのお悩みは非常に深刻です。
それにもかかわらず、こうしたリンパ浮腫を専門的にケアしてくれる病院やクリニックは、実は非常に少ないのが現状でした。大学病院でも受け皿がなく、患者さんも私も困っていました。
ーーそこで、院長ご自身も資格を取得され、専門セラピストも常駐されているのですね。
志茂院長
そうです。「ないなら、自分で作ろう」と決意し、私自身も「一般社団法人ICAA認定リンパ浮腫専門医師」の資格を取得しました。
当クリニックには、私と同様に専門の資格を持った看護師が、リンパ浮腫専門セラピストとして常駐しています(2025年7月より常勤)。リンパ浮腫のケアは、複合的治療と呼ばれます。まず、腕や脚を圧迫するための「弾性スリーブ」や「弾性ストッキング」といった補助具の選び方や購入のサポート、正しい使い方の指導を行います。
さらに、専門セラピストによる「リンパドレナージ(リンパ液の流れを促すマッサージ)」や「多層包帯法」といった専門的な施術も行います。こうしたケアを通じて、患者さんがより良い日常生活を送れるよう、積極的にお手伝いしています。大学病院から、リンパ浮腫のケアだけをお願いしたいと、ご紹介いただくこともあります。
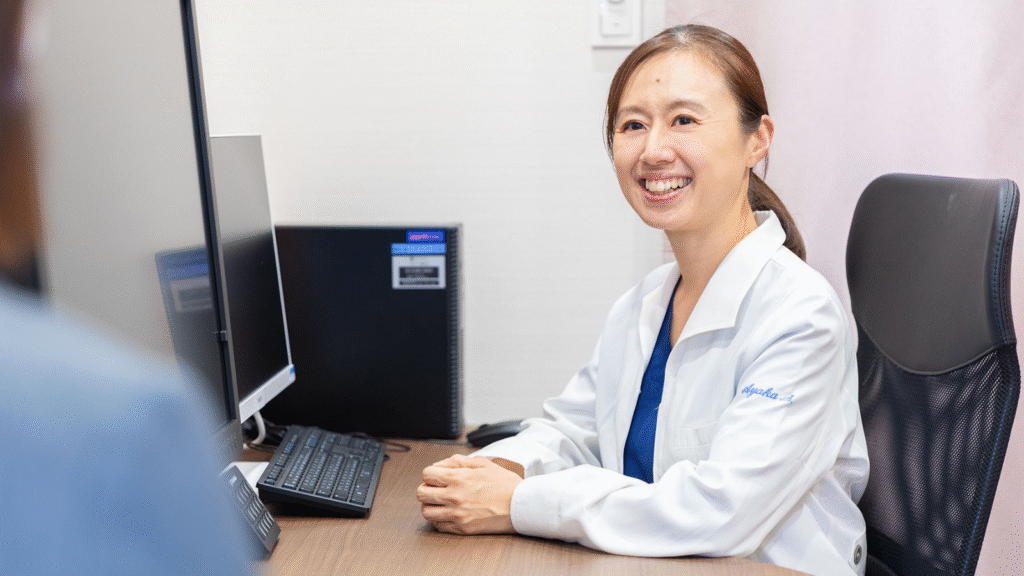
世田谷区の乳腺医療の「今」と、成城乳腺クリニックが果たす「地域の連携拠点」としての役割
乳がん患者が増加する一方で、地域の医療体制には様々な課題もあります。世田谷区の現状を踏まえ、成城乳腺クリニックが目指す「地域連携」の姿について伺いました。
ーー先生から見て、世田谷区の乳腺医療にはどのような特徴や課題があるのでしょうか?
志茂院長
意外に思われるかもしれませんが、世田谷区は人口が多い割には、大学病院がないんです。そして、乳がんの手術ができるような総合病院も、人口比で見ると決して多くはありません。
そのため、世田谷区で乳がんと診断された患者さんの多くが、区外の病院で治療を受けているのが現状です。ご自宅から通いやすい場所で治療を完結できないことは、患者さんにとって大きな負担になっている側面があると思います。
また、患者さんの数の割に、乳腺を専門とするクリニックの数も、内科や皮膚科などに比べるとまだまだ少ないのが実情です。
ーー大学病院の機能がパンクしてしまう、というお話もありました。
志茂院長
はい。乳がんの罹患率が上がり、治療が長期化することで、大学病院がすべての患者さんを抱えきれなくなってきている、という問題があります。治療が落ち着いた方の定期的な経過観察や薬の処方まで、すべて大学病院で請け負うと、本当に高度な医療が必要な患者さんへの対応が遅れてしまう可能性もあります。
だからこそ今、私たちのような地域の専門クリニックが、大学病院としっかり役割分担をして連携していくことが非常に重要になっています。
大学病院から「状態が落ち着いたので、あとは近くのクリニックで経過を見てください」と患者さんをご紹介いただくこともありますし、逆に私たちが「入口」となって検診や精密検査を行い、必要な方だけを大学病院にご紹介する。この「患者さんの振り分け」と「スムーズな連携」をうまく回していくことが、地域医療の質を保つ上で肝心な部分だと考えています。
ーー地域のクリニック同士の連携も活発なのですね。
志茂院長
とても大事です。私は世田谷区の医師会にも入っていますので、検診などで異常が見つかった方を、近隣の内科や産婦人科の先生から「専門的な検査をお願いします」とご紹介いただくことも頻繁にあります。
幸い、私の母校(聖マリアンナ医科大学)の卒業生は世田谷区内で開業されている先生も多く、いわば「知り合い」が多いんです。今日も近くのレディースクリニックの先生から患者さんをご紹介いただきました。日頃から顔の見える関係性を築けているので、先生同士とても仲が良いですし、お互いに信頼して患者さんを紹介し合える関係ができています。
もし乳がんと診断されたら?大学病院との「シームレスな連携」
読者の皆さんが最も不安に思われるのは、「もし、乳がんと診断されたらどうしよう」ということかもしれません。
成城乳腺クリニックでは、診断後の治療についても、大学病院や総合病院とシームレスに連携できる、万全のサポート体制を整えています。
ーー乳がんと診断された場合、患者さんはどうなるのでしょうか。
志茂院長
乳がんと診断した場合、まずはCTやMRIといった、より詳しい検査で全身への広がりなどを確認する必要があります。こうした精密検査は、当クリニックから連携している大学病院や、世田谷区内にある検査専門のクリニックにご紹介し、検査だけを受けてきていただきます。
検査結果は当クリニックに送られてきますので、結果のご説明や、それに基づいた治療方針のご相談は、すべて私が行います。あちこちの病院を行き来する負担が少なくなるよう配慮しています。
その上で、手術や抗がん剤治療が必要となった場合は、患者さんのご希望を伺いながら、聖マリアンナ医科大学病院をはじめとする連携先の大学病院や総合病院へ、責任を持ってご紹介します。
ーーかつて先生が感じた「大学病院の敷居の高さ」も、クリニックからの紹介ならスムーズなのですね。
志茂院長
その通りです。大学病院は今、紹介状がないと受診が難しくなっていますが、当クリニックで診断がつき、私からの紹介状を持って受診していただく形になるので、非常にスムーズに専門的な治療へと移行できます。
また、私自身が長年勤務していた大学病院ですので、どの先生がどの分野の専門家であるか、どのような治療を得意としているかを熟知しています。患者さん一人ひとりの病状やご希望に応じて、最適な先生にご紹介できるのも、当クリニックの強みだと思っています。
ーーさらに驚いたことに、院長先生ご自身が、他院で手術を担当されることもあると伺いました。
志茂院長
はい。これは、患者さんの「主治医が変わることへの不安」を少しでも解消したいという想いから、実現した体制です。
診断の結果、手術が必要になった場合、基本的には連携先の病院にご紹介します。しかし、患者さんから「先生にずっと診てほしい」「先生に手術してほしい」とご希望いただいた場合には、私が一貫して治療を担当することも可能です。
具体的には、私の夫が院長を務める三軒茶屋の「三軒茶屋ブレストセンター(青葉病院)」に手術室がありますので、私がそちらに出向いて手術を執刀します。そして、術後の経過観察や薬物治療は、また当クリニックに戻ってきていただき、私が継続して拝見します。
ーー診断から手術、術後のフォローまで、すべて志茂先生が主治医として見てくださるのですね。
志茂院長
大学病院では、担当医が異動したり、専門分野ごとに分かれたりして、主治医が変わってしまうことも少なくありません。しかし、特に乳がんのように長く病気と付き合っていく患者さんにとって、「ずっと同じ先生が見てくれる」という安心感は何物にも代えがたいものだと、私は考えています。
「あの先生なら、私の性格や今までの経緯も全部わかってくれている」。そう思える関係性が、治療を乗り越える上で大きな力になると信じています。
ーー連携先では、抗がん剤治療や乳房再建についても、手厚いサポートがあると伺いました。
志茂院長
はい。先ほどお話しした三軒茶屋ブレストセンター(青葉病院)は、乳腺外科だけでなく、形成外科や産婦人科も併設しています。そのため、乳房切除と同時に乳房を作り直す「乳房再建術」も、手術中に専門の形成外科医と連携して行うことができます。
また、抗がん剤治療の副作用で最もつらいことの一つに「脱毛」があります。連携先では、抗がん剤投与中に頭皮を冷却するヘルメットのようなものをかぶる「頭皮冷却療法」(自費診療)も導入しています。これにより、脱毛を完全に防ぐことは難しいですが、髪の毛が抜けるのを最小限に抑えたり、治療後の発毛が早くなったりすることが期待できます。こうした治療の選択肢もご提案できる体制を整えています。

院長が大切にする「患者さんの“これから”の人生」を支える診療
志茂院長が診療する上で大切にしているのは、病気を治すことだけではなく、「患者さんの人生そのもの」を見据え、その人らしい生き方をサポートすること。
その温かく、力強い診療スタイルに触れます。
ーー患者さんと接する上で、一番心がけていることは何ですか?
志茂院長
「乳がん」という診断は、患者さんにとって非常に衝撃的であり、深く落ち込んでしまうのは自然なことです。しかし、私は患者さんが必要以上に暗い気持ちにならないよう、お伝えの仕方を工夫しています。
まずは、「乳がんは、早く見つければ9割方治る(完治もめざせる)病気です。早い時期に見つけられて本当に良かったですね」と、希望を持てる事実をしっかりとお伝えします。
その上で、「これから治療が始まりますが、必ず終わりがあります。つらいこともあるかもしれませんが、一つ一つ一緒に乗り越えていきましょう」と、治療の全体像と見通しをお話しし、前向きに取り組めるよう励ましています。
外来でも、あまり暗い雰囲気にならないよう、時には世間話も交えながら、患者さんがリラックスしてお話しできる雰囲気づくりを大切にしています。大学病院時代には難しかった「余裕」が、今ようやく持てるようになったと感じています。
ーー診断を伝える際、ご家族の同席も勧められるのですね。
志茂院長
特に乳がんの診断を確定するために行う細胞診や組織診(針生検)の結果をお伝えするような重要な局面では、「ご家族の方もご一緒に」とお声がけしています。診断結果や治療方針、手術のこと、副作用のこと…一度にたくさんの情報をお伝えすることになるので、患者さんお一人では受け止めきれないことも多いのです。ご家族に同席していただくことで、ご本人も安心できますし、ご家族のサポートも得やすくなります。
ーー働く女性にとって「仕事と治療の両立」は大きな悩みだと思います。
志茂院長
乳がんの診断を受けた働く女性の多くが、「今の生活はどうしよう」「職場にどう伝えればいいの?」と深く悩まれます。
ですが、乳がんの手術は、再建術を同時に行わない場合、約1週間程度の入院で済むことが多く、数日のお休みで職場復帰できるケースも少なくありません。抗がん剤治療などで一時的に体調を崩し、副作用が出る場合でも、私たちは「お仕事は辞めないほうが良いですよ」とお伝えしています。なぜなら、仕事を辞めてしまうと、一日中、病気のことばかり考えてしまい、かえって気分が落ち込んでしまうことがあるからです。
治療後の長い人生も大切にしていただきたい。そのために、職場に提出する診断書の作成なども含め、患者さんが治療をしながらも「自分らしい生活」を続けられるよう、全力でサポートしていきたいと考えています。
ーー「治療が終わった後の人生も豊かに送ってほしい」という、先生の強い想いが伝わってきます。
志茂院長
私自身、患者さんの「その後」の人生を大切にしたいという思いが、医師としての原動力になっているのかもしれません。
先ほどもお話しした通り、日本人女性の9人に1人が乳がんになる時代です。ご家族に乳がんの方がいなくても、誰もが乳がんになる可能性を持っています。
しかし、乳がんは、きちんと治療すれば働きながらでも治療を進められる病気です。当クリニックが、患者さん一人ひとりに寄り添い、治療後の人生も豊かに送っていただくためのお手伝いができる存在でありたいと、心から願っています。

女性スタッフで創る、心穏やかな「アットホームな空間」
来院いただく方に悩みをご相談いただくため、そして、長く通い続けていただくために。
成城乳腺クリニックは、スタッフ体制から院内の空間づくりに至るまで、女性の心に寄り添う細やかな配慮に満ちています。
ーー院長をはじめ、スタッフ全員が女性であることも、患者さんにとっては大きな安心材料ですね。
志茂院長
当クリニックは、院長である私をはじめ、看護師、放射線技師、医療事務スタッフに至るまで、全員が女性です。
乳腺の悩みは、非常にデリケートな問題です。マンモグラフィ検査では胸を圧迫されますし、超音波検査では上半身裸になっていただく必要があります。同性である女性スタッフが対応することで、検査の際も診察の際も、余計な緊張や羞恥心を感じることなく、リラックスしていただけるのではないかと考えています。
スタッフの採用と研修にも力を入れ、全員が同じ想いを共有し、最高のチームで患者さんをお迎えできる体制を整えました。
ーー院内のデザインも、木目を基調とした温かい雰囲気で、まるでカフェのようです。
志茂院長
そう言っていただけると嬉しいですね(笑)。患者さんが安心して、そして気軽に立ち寄れるクリニックをめざし、院内は木目を基調として「おうち」にいるようなぬくもりを感じられる空間にしました。
治療が長期にわたる方や、他の病院で治療中の方が、ふと不安になった時に「いつでもここに戻ってこられる」と感じ、安心して相談できるような、アットホームな雰囲気を大切にしています。
待合室の窓からは、ウッドデッキに並べられた季節の花々を眺めることができます。もともとこの物件はオーナーのご自宅で、広々としたベランダがあったんです。このベランダをウッドデッキとして活用し、心癒される小さな庭をつくりました。大学病院のような慌ただしさを感じさせないよう、診察をお待ちいただく時間も、ゆったりと心穏やかに過ごしていただける空間づくりを心がけています。

ーー土曜日の診療やオンライン処方など、ライフスタイルに合わせた通院が可能な点も助かります。
志茂院長
お仕事をされている方や、平日は家事・育児で忙しい方にも通っていただきやすいよう、土曜日の午前中も診療を行っています。また、症状が落ち着いていて、定期的なお薬の処方のみが必要な方(定期的な外来通院も可能な方に限ります)には、ご希望によりオンライン処方も行っています。
遠方から転居されてきて通院先をお探しの方、ご自宅から通いやすく、適切な経過観察を行える施設をお探しの方など、様々なニーズにお応えできる体制を整えています。当クリニックは予約制としており、丁寧な検査と説明、スムーズな診察を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
成城の乳腺クリニックとして|地域と読者へのメッセージ
最後に、クリニックの今後の展望と、乳腺に悩みを抱える地域の読者に向けて、志茂院長から温かいメッセージをいただきました。
ーー先生はクリニックを開業された今も、大学病院での診療を続けられているのですね。
志茂院長
はい。現在も、クリニックの休診日を利用して、聖マリアンナ医科大学病院やブレスト&イメージング先端医療センター附属クリニックで外来診療を続けています。
これは、当クリニックに通ってくださる患者さんに、絶対的な安心感を持っていただきたいからです。万が一、病状が進行したり、再発したりして、「やっぱり大学病院での高度な治療が必要」となった時でも、「先生は大学病院とつながっているから大丈夫」と、安心していただきたいのです。
常に最新の知見をアップデートし続けるという意味でも、大学病院とのつながりは持ち続けていきたいと考えています。
ーー「地域医療と大学病院の架け橋」として、双方に貢献していきたい、と。
志茂院長
まさしく、その通りです。地域の患者さんには、検診から精密検査、治療後のフォローまで、安心して通い続けられるアットホームなクリニックとして。そして大学病院に対しては、私たちが地域のクリニックとして専門性の高い診療を行うことで、大学病院で働く医師たちの負担を少しでも軽減し、彼らには大学病院でしかできない、より高度な医療に集中してもらう。
「成城乳腺クリニック」が、地域の患者さんにとっても、大学病院にとっても、双方に貢献できる存在になれるよう、これからも努力していきます。
ーーお子さん連れでのご来院や、男性の乳腺診療も可能なのでしょうか。
志茂院長
もちろんです。お子さん連れでのご来院も大歓迎です。付き添いのご家族も、どうぞ気兼ねなくお越しください。また、乳がんは女性の病気と思われがちですが、頻度は非常に低いものの、男性も乳がんになる可能性はゼロではありません。「胸が膨らんできた」「しこりがある」といった症状(女性化乳房症など、良性の場合がほとんどです)でお悩みの男性もいらっしゃると思います。
当クリニックでは男性の患者さんの診療も行っておりますので、ご心配なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
ーー最後に、乳がん検診をためらっている読者や、乳腺の悩みを抱えている方へメッセージをお願いします。
志茂院長
世田谷区は、残念ながら乳がん検診の受診率が低いと言われています。その理由の一つは、おそらく「身近に受けるクリニックがなかった」ことではないかと感じています。この記事を読んで、「検診に行かなきゃ」と思ってくださった方。あるいは、しこりなどの自覚症状があるのに、「結果を聞くのが怖い」「精密検査になったらどうしよう」と、受診をためらっている方。どうか、怖がらないでください。
乳がんは、早く見つければ9割の方が治ると言われている病気です。むしろ、見つけることを怖がらずに、早く見つけることが何よりも大切です。当クリニックでは、もし検診で精密検査が必要になった時、その次にどのようなステップで検査を進めていくのか、患者さんがしっかりイメージできるよう、丁寧にご説明します。
そして、もし乳がんと診断されたとしても、治療の選択肢はたくさんありますし、私たちは患者さんの「これからの人生」を見据えて、明るい未来に向けて一緒に治療を継続していきます。乳腺に関するお悩みを、安心して気軽に相談できるクリニックとして、スタッフ一同、皆さまをお待ちしています。

成城乳腺クリニック
| 診療科目 | 乳がん検診、乳腺外科、乳腺内科 |
|---|---|
| 住所 | 〒 157-0066 東京都世田谷区成城5丁目8-1 成城クレストビル3階 |
| 診療日 | (月・水・木・金・土)9:00〜12:30 (月・水・木・金)14:00〜17:00 ※土曜日は13:00終了 |
| 休診日 | 火、土午後、日、祝日 ※第1,3,5火曜日/聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンターで外来 ※第2,4火曜日/三軒茶屋ブレストセンターで手術 |
| 院長 | 志茂 彩華 |
| TEL | 03-6411-3456 |
| 最寄駅 | 小田急線「成城学園前駅」西口より徒歩2分 |