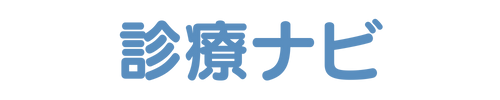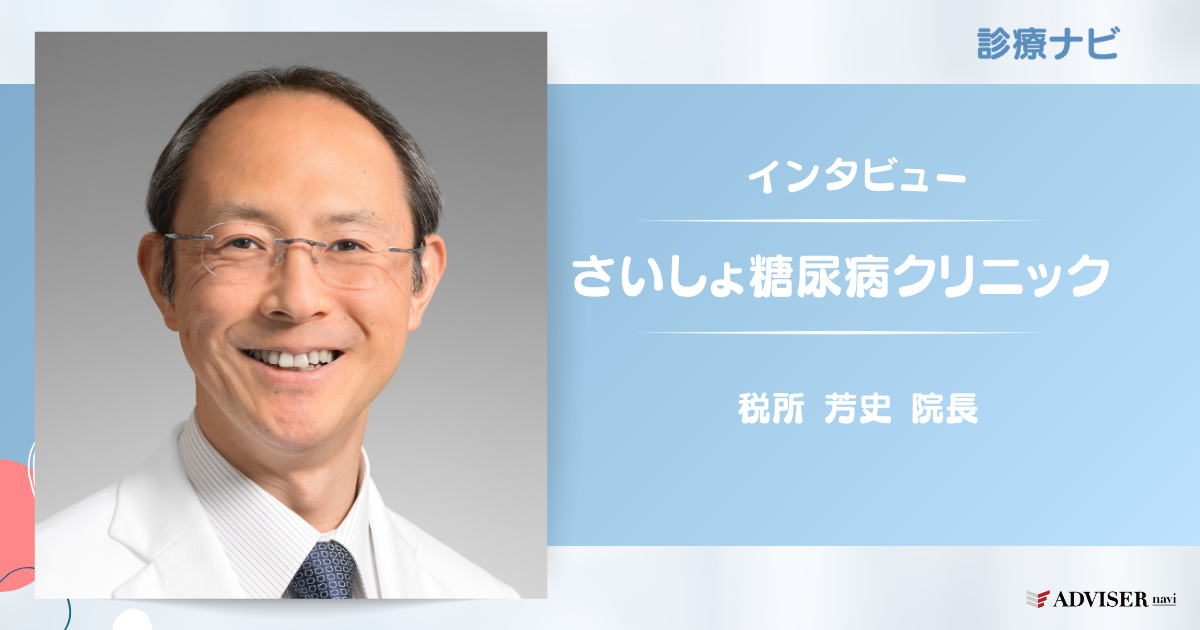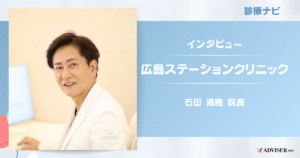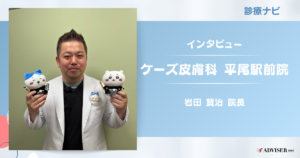2025年9月4日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「健康診断で血糖値の高さを指摘された…」
「食事も運動も頑張っているのに、なぜ良くならないんだろう…」
しかし、生活習慣病とも呼ばれる糖尿病は生活習慣だけが原因ではないと言います。
この記事では、中野駅近くにある「さいしょ糖尿病クリニック」の院長を務める税所 芳史(さいしょ よしふみ)先生にお話を伺いました。
税所院長は、大学病院で長年診療に携わり、米国UCLAへの留学で糖尿病発症の鍵を握る「膵β細胞」の研究をリードしてきたエキスパートです。
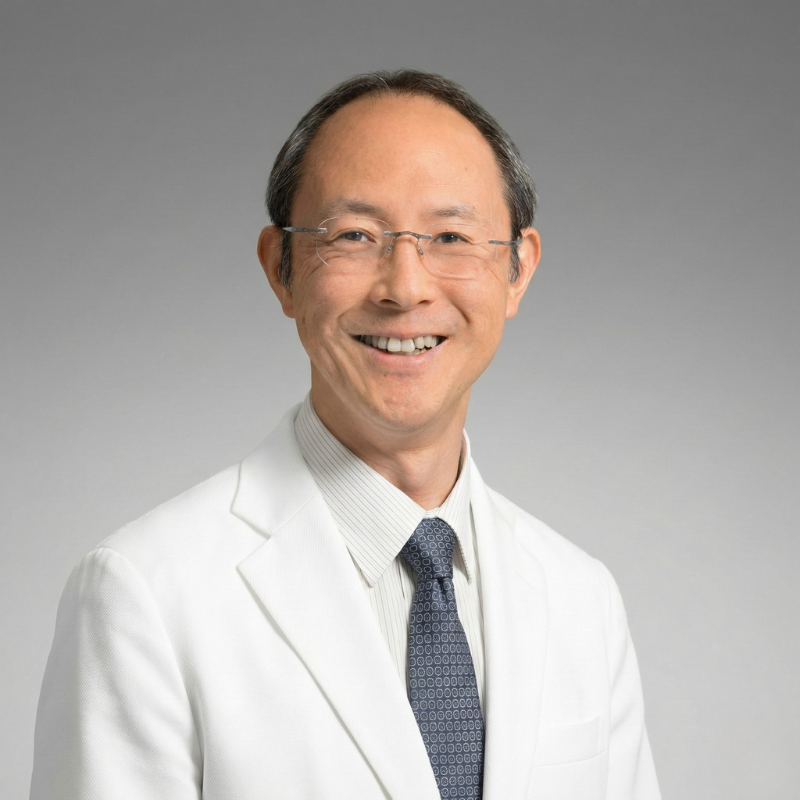
税所芳史
さいしょ糖尿病クリニック(東京都中野)院長。慶應義塾大学医学部卒、UCLA留学で膵β細胞研究に従事し医学博士。日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医、日本内科学会 総合内科専門医として、2型糖尿病のβ細胞障害を軸に診療・研究を行う。
詳細プロフィール
– 所属・役職:
さいしょ糖尿病クリニック 院長
慶應義塾大学医学部 非常勤講師
杏林大学医学部 臨床教育 准教授
国際個別化医療学会 理事
– 専門領域:
糖尿病全般(特に2型糖尿病における膵β細胞障害)、臨床糖尿病学
内分泌・代謝領域
一般内科
– 資格:
日本内科学会:総合内科専門医(2004取得)・指導医
日本糖尿病学会:糖尿病専門医(2005取得)・指導医・学術評議員
日本糖尿病協会:療養指導医(2013〜)
日本医師会認定健康スポーツ医
小児慢性特定疾病指定医
難病指定医
– 学歴:
慶應義塾大学医学部 卒業(1998)
医学博士(慶應義塾大学、2009)
– 経歴:
1998:慶應義塾大学医学部卒、内科学教室入局。関連病院で内科全般を研修
2002:腎臓内分泌代謝内科に所属し、糖尿病専門医として研修開始
2006:UCLA留学、膵β細胞研究に従事
2009:慶應義塾大学 助教として帰国
2015:専任講師(診療・教育・研究に従事)
2022:さいしょ糖尿病クリニック開設
– 学会・役職:
日本内科学会:認定問題作成委員、病歴要約査読委員 など
中野区医師会:新聞編集委員
日本糖尿病学会:総会演題選定委員 など
糖尿病療養指導士認定関連:試験委員会(委員長を含む)・認定委員会 など
糖尿病データマネジメント研究会(JDDM)会員
– 著書・論文:
『標準的医療説明-インフォームドコンセントの最前線』(医学書院 2021)医学書院
『今日の治療方針 2023年版』(医学書院 2023)医学書院
『臨床精神医学第54巻第4号』(アークメディア 2025)アークメディア
その他多数執筆あり
税所 芳史先生が医師を目指した理由と「糖尿病」との出会い
医師の家系に生まれ、自然と医療の道を志したという税所院長。
数ある専門分野の中から、なぜ「糖尿病」を選んだのでしょうか。
その原点には、患者さん一人ひとりの人生に深く寄り添う医療への強い想いがありました。
ーー先生が医師を志したきっかけについて教えてください。
税所院長
私の祖父は父方・母方ともに開業医で、父は大学病院の勤務医という、医師の家系で育ちました。物心ついた頃から家にはレントゲンや聴診器といった医療用具が当たり前のようにあり、医療は非常に身近な存在でした。体調を崩した時には父が病院で診てくれたのですが、その際に他の患者さんから感謝されている姿を目の当たりにして、「人の役に立てる、いい仕事だな」と感じたのが最初のきっかけだったかもしれません。もともと自然科学が好きで、「人間」という自然をとことん追求できる医師の仕事に魅力を感じ、医学部進学を決めました。
ーー数ある診療科の中で、なぜ「糖尿病内科」を専門に選ばれたのでしょうか?
税所院長
理由はいくつかありますが、研修医時代に初めて担当した患者さんが糖尿病を患っていたことも一つのきっかけです。
例えば胃のポリープなら切除すれば治療は完了しますが、糖尿病は一度発症すると生涯付き合っていくことになる病気です。治療の過程で他の病気を併発することもあり、医師は患者さんの人生に長く、深く関わっていくことになります。ただ病気を診るだけでなく、患者さんの生活背景や価値観にも触れ、心理的なアプローチも必要です。そんな全人的な医療に大きなやりがいを感じました。
また、患者さんと長期的に関わりながら、自分自身も成長できる点に強く惹かれたのが、糖尿病の専門医を目指した一番の理由です。
ーー研修医時代はどのようなご経験をされましたか?
税所院長
卒業後は慶應義塾大学病院に入り、2年間ですべての専門内科をローテーションする研修を受け、内科医として幅広い知識と経験をさせていただきました。その後、静岡や平塚の関連病院でさらに2年間研鑽を積み、そこでは主治医として一度に20〜30人の入院患者さんを受け持つこともあり、非常にハードな毎日でした。一睡もできない当直の翌日も通常通り診療を行うのが当たり前の時代で、今では考えられないような生活でしたが、この4年間で得た経験は、私の医師としての土台になっています。「あの時頑張れた」という経験が自信になっています。
「糖尿病はなぜ治らない?」探求の末にたどり着いた米国留学と“膵β細胞”
多くの患者さんと真摯に向き合う中で、税所院長は「なぜ真面目に治療に取り組んでいるのに、良くならない方がいるのだろうか」と感じたそうです。
その答えを求めて、渡米した税所先生は糖尿病に関する衝撃的な事実を目の当たりにします。
ーー大学病院での診療の中で、どのような疑問を抱かれたのでしょうか?
税所院長
糖尿病治療の基本は食事療法と運動療法です。ただ、教科書通りに指導し、患者さんも真面目に取り組んでいるにもかかわらず、血糖値が改善せず、かえって悪化してしまう方が一定数いらっしゃいました。なぜ糖尿病になるのか、そして、なぜ治らないのか。日々自問自答している中、ある論文に出会いました。それは、アメリカのカリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)のPeter C. Butler教授が発表したもので、「2型糖尿病患者では、血糖値を調節するインスリンを分泌する“膵β細胞”の量が減少している」という内容でした。この論文を読んだ時には、糖尿病治療の方向性を大きく変える可能性を感じました。
ーーその論文がきっかけで、UCLAへ留学されたのですね。
税所院長
はい。この研究を本格的に学びたい一心で、周囲のサポートも得ながら留学しました。幸運にもButler教授の研究室に受け入れていただき、2006年から3年間、膵β細胞の研究に没頭しました。この留学経験で、糖尿病の発症メカニズムを解明できたことは、私にとって非常に大きな成果です。確かなエビデンス(医学的根拠)のもと、患者さんと向き合えるようになったことは、医師としての大きな自信につながっています。
ーー先生の研究の要である「膵β細胞」とは、どのようなものなのでしょうか?
税所院長
私たちの体は、食事で糖質を摂ると血糖値が上がります。その上がった血糖値を正常に保つために、膵臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。このインスリンを作る唯一の細胞が「膵β細胞」です。インスリンは、血液中の糖を筋肉や脂肪、肝臓などに取り込ませることで血糖値を下げます。しかし、何らかの原因で膵β細胞の数が減ったり、働きが弱まったりしてインスリンが十分に出なくなると、血糖値が高いままの状態が続き、糖尿病を発症してしまうのです。
ーーなぜ、その大切な膵β細胞が減ってしまうのでしょうか?
税所院長
大きな原因の一つが、β細胞の「働きすぎ」だと考えています。肥満や過剰な栄養摂取が続くと、たくさんのインスリンを分泌して血糖値を下げようと、β細胞は常にフル稼働の状態になります。やがて頑張りすぎて疲弊し、機能が低下してしまう。私はこれを「細胞の過労死」と呼んでいます。さらに悪いことに、一度死滅してしまったβ細胞は、基本的に再生することが難しいのです。数が減ると、残ったβ細胞の負担がさらに増し、さらなる疲弊を招く…という悪循環に陥ってしまいます。糖尿病の患者さんは、皆さんこの膵β細胞がすでに減少してしまっている状態なのです。これが、糖尿病が簡単には「治らない」と言われる大きな理由です。
中野で開業した理由と「さいしょ糖尿病クリニック」の想い
大学病院での研究と臨床の最前線から一転、地域医療の現場へ。
税所先生は、より多くの患者さんに、より早く適切な医療を届けたいという想いから、2022年に「さいしょ糖尿病クリニック」を開業しました。
多くの患者さんがアクセスしやすいこの場所を選んだ理由と、クリニックに込めた理念についてお聞きしました。
ーー大学病院から開業医への道を選ばれました。また、開業にあたって、なぜこの「中野」という場所を選ばれたのでしょうか?
税所院長
生まれ育ったのが新宿で、勤務先も信濃町の慶應大学病院でしたので、中央線沿線は昔から馴染みのあるエリアでした。開業を考えた際、自分の専門性を生かすためには、地域の方だけでなく、より広域から患者さんに来ていただく必要があると考えました。そして、ターミナル駅を中心に場所を探していたところ、幸運にも、駅から徒歩3分というこの場所で、ビルを新築するタイミングでご縁をいただくことができました。ビルのオーナー様も地域貢献への想いが強い方で、私の理念に共感していただけたことも大きな決め手でしたね。
ーー「さいしょ糖尿病クリニック」というお名前には、どんな想いが込められていますか?
税所院長
一つは、私の苗字である「税所(さいしょ)」です。そしてもう一つは、「最初(さいしょ)の段階から、早期に適切な治療を始めたい」という想いです。大学病院では、どうしても症状が進行した患者さんを診ることが多くなります。頑張って治療しても、一度失われたβ細胞の機能などを元に戻すのは非常に難しい。だからこそ、検診で異常を指摘されたばかりの方や、少しでも不安を感じた方が、気軽に相談できる身近なクリニックが必要だと考えました。専門性を明確にするため、あえて「糖尿病クリニック」という名称にしています。
ーー確かに、駅から近く非常に通いやすい立地ですね。
税所院長
糖尿病は、治療を継続することが何よりも大切です。そのため、開業にあたって第一に考えたのは「患者さんの通いやすさ」でした。駅から近いという物理的なアクセスの良さはもちろん、待ち時間を短縮するための完全予約制や、自動精算機の導入といったハード面、そして、スタッフの親身な対応といったソフト面の両方を追求しています。
また、このビル内には婦人科や泌尿器科、歯科、近隣には眼科や皮膚科などもあり、糖尿病の合併症が懸念される際にも、各科の先生方とスムーズに連携できる体制が整っています。
ーー「清潔、笑顔、思いやり」をモットーに掲げていらっしゃいますね。
税所院長
これはクリニックを開業するにあたって、スタッフ全員で話し合って決めた、私たちの約束です。毎朝の朝礼で全員で唱和し、この気持ちを忘れないようにしています。糖尿病という病気は、一生付き合っていくものです。だからこそ、クリニックが「つらい」「行きたくない」と感じる場所であってはならない。患者さんに「またここに来ようかな」と思っていただけるような、温かく、信頼できるクリニックでありたいと常に考えています。
医師と患者がパートナーになる|さいしょ糖尿病クリニックが目指す糖尿病治療とは
糖尿病治療は、時に孤独な戦いになりがちです。
「あれもダメ、これもダメ」と制限ばかりが増え、モチベーションを維持するのが難しいと感じる方も少なくありません。
しかし、さいしょ糖尿病クリニックでは、患者さんが前向きに治療を続けられるための独自のサポート体制とアプローチを大切にしています。
ーー先生が治療において最も大切にしていることは何ですか?
税所院長
それは、「医師と患者さんが、対立するのではなく、同じ方向を向く」ということです。これまでの医療では、「生活習慣が悪いから直しなさい」と、医師が上から指導する形が主流でした。これでは、患者さんは追い詰められ、医者との間に溝が生まれてしまいます。私はそうではなく、「あなたの膵臓の中では今、β細胞が疲弊しています。この大切なβ細胞を、これ以上減らさないように一緒に守っていきましょう」とお話しします。そして、患者さんと一緒に膵β細胞の働きを維持することを目指した治療を行っています。そのため、食事や運動は、その目標を達成するための手段です。なぜ頑張る必要があるのかを心から納得できれば、患者さん自身の内側からモチベーションが湧いてくると信じています。
ーーチーム医療にも力を入れていらっしゃると伺いました。
税所院長
当院では、医師である私だけでなく、栄養指導を担当する管理栄養士、療養指導を担当する看護師、そして検査技師や医療事務スタッフまで、全員がチーム一丸となって患者さんをサポートします。患者さんの生活環境や食生活は一人ひとり全く異なります。ですから、きめ細やかなアドバイスのためには、それぞれの専門家の力が必要不可欠です。カウンセリングルームも設け、管理栄養士がじっくりと栄養相談に乗れる時間を確保しています。
ーーホームページでも、先生のお考えを詳しく発信されていますね。
税所院長
限られた診察時間だけでは、お伝えできることに限りがあります。特にβ細胞の話などは、初めて聞くと少し難しく感じるかもしれません。そこで、私の治療に対する考え方や糖尿病に関する正しい知識を、できるだけホームページに詳しく掲載するようにしています。事前に読んで来てくださる患者さんも多く、診察室でのコミュニケーションが非常にスムーズになります。患者さんがご自身のペースで情報を得て、ある程度納得した上で診察に臨んでいただくことで、ミスマッチが少なくなり、より深い信頼関係を築くことができると考えています。

糖尿病治療の最前線と知っておくべきこと
「糖尿病は一度なったら治らない、古い病気」そんなイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかし、その治療法は近年目覚ましい進歩を遂げています。
ここでは、最新の治療薬や、世間に広まる誤解など、患者さんが知っておくべき“今”の情報について、専門医の視点から解説していただきました。
ーー糖尿病の治療法は、昔と比べて新しくなっているのでしょうか?
税所院長
はい。この10〜15年で、糖尿病治療は進歩しています。特に、新しいお薬が次々と登場しているのが大きな特徴です。インスリン注射などで血糖値を下げようとすると、逆に下がりすぎて「低血糖」を起こしてしまうリスクが常にあります。これが糖尿病治療を行う上での大きなジレンマでした。しかし、最近の薬は血糖値が高い時にだけインスリンの分泌を促すなど、非常に賢い働き方をします。低血糖のリスクを抑えながら、効果的に血糖値を正常化できるようになってきました。
ーー最近「マンジャロ」という薬が話題ですが、先生はどのようにお考えですか?
税所院長
これは非常に画期的な糖尿病治療薬の一つだと考えています。この薬はGLP-1受容体作動薬とも呼ばれていますが、中でもすごいところは、先ほどお話しした「血糖が高い時だけインスリン分泌を促す」という作用に加え、食欲を抑えて体重を減少させる効果が期待できる点です。これまでの糖尿病治療薬には、むしろ体重が増えやすいという欠点がありました。体重が減れば、それだけで血糖値は改善しやすくなります。この薬の登場により、外科的な肥満手術に頼らずとも、大幅な体重減少と血糖値の正常化、いわゆる「寛解」を目指せる可能性があると私は感じています。
一方で、痩せ薬として自由診療で不適切に使用されるケースが問題視されていますが、これは保険診療の適用の問題が絡む非常にデリケートな話です。私たちはあくまで糖尿病患者さんの健康を守るために、メリットとデメリットを慎重に見極めた上で、必要な方に処方しています。危険な薬というイメージだけが先行するのは、非常に残念なことですね。
ーー「生活習慣病」という言葉が、患者さんを追い詰めている側面もあるように感じます。
税所院長
おっしゃる通りです。その言葉が、「あなたの生活習慣がだらしないから病気になった」という自己責任論につながり、患者さんに不要な劣等感を抱かせてしまっている面は否めません。しかし、糖尿病は遺伝的な体質が非常に強く関わっています。両親が糖尿病の場合、お子さんが発症する確率は70%にも上ると言われています。インスリンを出す膵β細胞の力の強さは、ある程度遺伝で決まっているとされています。
さらに言えば、現代社会そのものが糖尿病を増やしているとも言えるでしょう。実は、第二次世界大戦前まで、2型糖尿病は非常に稀な病気でした。しかし、戦後の高度経済成長を経て、社会が豊かになり「飽食の時代」になったことで、患者数は爆発的に増えました。これは個人の責任というより、社会環境の変化がもたらした結果だと考えています。
自分のからだを大切にすることが社会と地球の未来につながる
税所院長の視点は、個人の健康の改善だけに留まりません。
糖尿病という病気と真摯に向き合うことが、いかにしてより良い社会、そして地球環境の未来につながっていくのでしょうか。
ーー先生は、糖尿病治療が社会貢献やSDGsにもつながるとお考えなのですね。
税所院長
はい、そのように考えています。例えば、食べ過ぎを防ぎ、車を使わずになるべく歩くといった生活習慣の改善は、ご自身の膵臓への負担を減らすだけでなく、フードロスの削減や車社会がもたらす環境負荷の是正にも貢献できるはずです。大量消費によって健康を害するような行動を避けることは、結果的に無駄な資源を使わないことにつながります。
ーー健康に良い選択が、地球にとっても良い選択になるということでしょうか。
税所院長
「自分のからだに過度の負担をかけない」という意識は、「社会や地球環境への負担を減らす」ことにも直結します。一人ひとりがご自身の健康を意識して正しい行動を取ることが、巡り巡って環境保護にも貢献する。そんな大きな視点を持つことで、治療へのモチベーションもまた変わってくるのではないかと考えています。個々の健康の先にある、より良い未来の実現に少しでも貢献できれば嬉しいですね。
税所院長から糖尿病と向き合うあなたへ
最後に、糖尿病のことで悩んでいる方、これから受診を考えている方へ向けて、税所院長から温かいメッセージをいただきました。
ーーこの記事を読んでいる読者の方へ、メッセージをお願いします。
税所院長
まず知っていただきたいのは、糖尿病は決して「だらしない人」がなる病気ではないということです。むしろ、真面目に仕事や生活に取り組んでいる、ごく普通の方が発症します。そして、その原因はあなたのせいだけではなく、遺伝的な体質や、今の社会環境も大きく影響しています。
大切なのは、正しい知識を身につけ、ご自身の体の状態を正確に理解すること。そして、信頼できるパートナー(医師)を見つけ、できることから一歩ずつ始めていくことです。糖尿病は「予防できる」「悪化を防げる」病気でもあります。
当院では、なぜ治療が必要なのか、その目的を患者さん自身に深く納得していただくことを何よりも大切にしています。「膵β細胞を大切にする」という共通の目標を持てば、治療は決して苦しいだけのものではありません。健康診断で異常を指摘されたり、少しでも不安なことがあったりしたら、どうか一人で抱え込まず、専門医に相談してください。

さいしょ糖尿病クリニック
| 診療科目 | 糖尿病内科、内科 |
|---|---|
| 住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野5-67-5SKGT長谷部3階 |
| 診療日 | (月・火・水・金)9:00〜12:30/14:30〜18:00 (木・土)9:00〜12:30 |
| 休診日 | 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日 |
| 院長 | 税所 芳史(さいしょ よしふみ) |
| TEL | 03-5942-9393 |
| 最寄駅 | JR中央・総武線、東京メトロ東西線「中野駅」北口より徒歩3分 中野駅北口バス停より徒歩1分 |