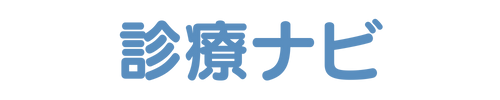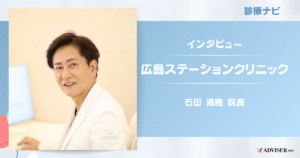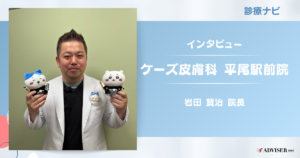2025年10月15日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「乳がん検診、受けなきゃいけないのは分かっているけど、なんとなく後回しにしてしまう…」
「マンモグラフィって痛いって聞くし、なんだか怖い…」
「仕事や育児が忙しくて、自分のことはつい後回しになってしまう…」
そんな風に感じていませんか?
日本人女性の9人に1人1が罹患するといわれる乳がんは、私たちにとって最も身近ながんの一つとされています。
しかし、その一方で検診へのハードルが高いと感じている方が多いのも事実。
この記事では、そんな女性たちの不安な心に優しく寄り添っている「ピンクリボンブレストケアクリニック表参道」の島田 菜穂子院長にお話を伺いました。
日本のピンクリボン運動を黎明期から牽引してきた島田院長が、なぜこれほどまでに女性のブレストケアに情熱を注ぐのか。
その想いの源泉から、検診の「怖い・痛い・忙しい」を解消するための徹底したクリニックづくり、そして万が一の時にも安心のサポート体制まで、インタビュー形式でご紹介します。
「なぜ、もっと早く…」日米差に対する驚き|島田 菜穂子院長とピンクリボン運動の軌跡
今や日本でも広く知られるようになった、乳がん啓発活動のシンボル「ピンクリボン」。
その活動を日本で根付かせるために尽力してきた第一人者が、島田 菜穂子院長です。
放射線科医としてキャリアをスタートさせ、乳がん診療の専門性を高めていく中で目の当たりにした”ある現実”が、彼女を啓発活動の道へと突き動かしたと言います。
ーー島田先生が医師という仕事を志されたのには、何か特別なきっかけがあったのでしょうか?
島田院長
原体験としてあるのは、中学生の時に父が若くして亡くなったことです。入院していた父のそばに付き添う中で、昼夜を問わず駆けつけて治療にあたってくださるお医者様や看護師さんの姿を間近に見て、「なんてありがたい存在なんだろう」と強く感じました。その時の感謝の気持ちが、漠然とですが「いつか人の役に立つ仕事がしたい」と考えるきっかけになったと思います。
その後、進路を考える中で、何か資格を持って人と深く関わる仕事がしたいという想いと結びつき、医師の道へ進むことを決めました。
ーー数ある診療科の中から、なぜ「放射線科」、そして「乳腺科」を専門に選ばれたのですか?
島田院長
大学の臨床実習で様々な診療科を回る中で、放射線科に強く惹かれました。最新のCTやMRIといった機器を駆使して得られた画像から病気の原因を突き止め、他の診療科の医師たちとのカンファレンスを主導していく。主治医が想像もしていなかった病気の可能性を指摘し、治療の方向性を指南する「ドクターズ・ドクター(医師に頼られる医師)」の姿が、本当にかっこよく見えたんです。もともと機械や画像が好きだったこともあり、自分の興味と一致したこの分野に進むことに迷いはありませんでした。
放射線科医として働き始めると、超音波(エコー)検査など、患者さんと1対1で向き合う機会も多くありました。キャリアの浅い若い女性医師ということで、最初は頼りなく思われることもありましたが、検査を進めるうちに、特に女性の患者さんが、男性の主治医には話していないような症状の詳細や不安な気持ちを、私にだけ打ち明けてくださることが多いのに気づきました。
実は、患者さんからどれだけお話を引き出すことができるかが診断の精度を上げる上で非常に重要なんです。また「女性だからこそ得られる情報がある。女性である自分が役に立てる分野があるかもしれない」と強く感じました。その時、特に多く担当していたのが乳腺の検査でした。これが、私が乳がん診療に深くのめり込んでいく大きなきっかけになりましたね。

ーーその後、アメリカへ留学されていますが、そこで何が変わったのでしょうか?
島田院長
幸いにも上司や同僚に恵まれ、勤務していた東京逓信病院に放射線科医としては異例の「乳腺外来」を開設させてもらい、診療に没頭していました。しかし、当時は進行した状態で見つかる患者さんが後を絶たず、「もう少し早く来てくれていれば…!」と悔しい思いをすることが少なくありませんでした。
そんな中、乳がん先進国であるアメリカへ留学する機会をいただきました。医療技術そのものに大きな差は感じませんでしたが、衝撃を受けたのは、患者さん自身の乳がんに対する意識の高さでした。私がいたセントルイスはアメリカ中西部ののんびりした田舎町でしたが、そこに住むごく普通の人々が、「乳がんは身近な病気であること」「早期発見すれば治る可能性が高いこと」「そのためには定期的なマンモグラフィ検診が重要であること」を当たり前に知っていたのです。
日本では、健康意識が高いはずの東京の都心でさえ、手遅れに近い状態で来院される方がいる。でもアメリカの田舎町では、症状がないうちから検診を受け、ごく早期のがんが見つかる人がたくさんいる。この違いは一体何なんだと、愕然としました。
その答えは、病院の外にありました。街中の看板やジュースのパック、シャンプーのボトルにまでピンクリボンがあしらわれ、「Mammogram saves your life.(マンモグラフィがあなたの命を救う)」というメッセージが常に流れている。誰もが、いつでもどこでも乳がんに関する正しい情報に触れられる環境が作られていたのです。
ーーそれが、日本でピンクリボン運動を始めようと思った直接の理由なのですね。
島田院長
その通りです。「病院の中でただ患者さんを待っているだけでは、日本は変わらない。大切な情報は伝わらない」と痛感しました。日本中の女性に、そして男性にも知ってもらいたいことが山ほどある。この溢れる思いを胸に、帰国してすぐに啓発活動のための団体を結成しようと奔走しました。
そして帰国翌年の2000年、奇しくも日本でマンモグラフィ検診が国の事業として推奨され始めた「マンモグラフィ元年」に、同じ志を持つ医師たちとNPO法人「乳房健康研究会」を立ち上げ、日本でのピンクリボン運動を始動させたのです。当時は「ピンクリボンって何?」というところからのスタートで、何もかもが手探りでしたが、あの時の一歩がなければ今はなかったと思っています。

「忙しい」「恥ずかしい」は卒業しよう|ピンクリボンブレストケアクリニック表参道が徹底する”受診のハードルを下げる”5つの工夫
多くの女性が乳がん検診をためらう理由を知り尽くした島田院長。
その知見は、2008年に開院した「ピンクリボンブレストケアクリニック表参道」の隅々にまで活かされています。
「どうすれば、もっと気軽に、安心してクリニックに足を運んでもらえるか」。
その一心で実現された、徹底して患者目線に立つクリニックづくりの秘密をご紹介します。
ーーなぜ、この表参道という場所にクリニックを開院されたのですか?
島田院長
啓発活動を続ける中で、女性たちの意識が高まっても、実際に検診を受けるには様々な障壁があることに気づきました。特に、日本人の乳がんは海外に比べて発症年齢が若く、30代後半から増え始め、40代〜50代の働き盛りの世代でピークを迎えます。
だからこそ、私がクリニックを開くなら、仕事やプライベートで忙しい若い女性たちが、お買い物のついでや仕事帰りにでも立ち寄りやすい場所にしたいという強い想いがありました。通うこと自体が少しでも気分が上がるような、ポジティブなイメージのある場所にしたかったのです。表参道は、まさにそのイメージにぴったりの場所でした。

ーー夜間や土日も診療されているのは、やはり働く女性のためでしょうか。
島田院長
はい。平日の日中に時間を確保するのが難しい方は本当に多いです。現役世代の方が、仕事を休んだり、誰かにお子さんを預けたりすることなく受診できるように、火曜・水曜は20時まで、月曜・金曜は19時まで診療していますし、土日も開院しています。
特に、患者さんが多く来院される土曜日は医師を増員して二診制にするなど、できるだけ多くの方を受け入れられる体制を整えています。セカンドオピニオンを求めて、地方から泊りがけでいらっしゃる方もいます。そうした方々のニーズにも、できる限り応えたいと考えています。
ーー「人目が気になる」「男性医師は苦手…」という方への配慮が徹底されていると伺いました。
島田院長
デリケートな分野ですので、プライバシーの保護には最大限配慮しています。まず、医師・看護師・放射線技師・臨床検査技師・受付スタッフに至るまで、全員が女性です。
また、院内は個室を多く設けています。例えば、待合室を通らずに直接入れる個室もあり、告知などでご主人と一緒に来られた際などに利用いただいています。診察や検査もすべて個室で行いますし、お着替えも術後の方も気兼ねなく着替えられるように、女性更衣室といったような大部屋ではなく、試着室のようなお一人ずつ使える個室の更衣室をご用意しました。人目を気にせず、リラックスして過ごしていただけるよう、空間づくりには特にこだわっています。

ーー予約や問診も非常にスムーズだと聞きました。
島田院長
忙しい現役世代の方々の時間を少しでも無駄にしないため、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)は早い段階から積極的に取り入れています。
ご予約は、お電話だけでなく24時間いつでもスマートフォンやPCから可能なWeb予約システムを導入しています。また、ご来院いただく前にWeb上で問診票を入力していただくことで、クリニックでの待ち時間を短縮し、すぐに検査やカウンセリングにご案内できます。入力されたデータはそのまま電子カルテに連携されるので、受付での煩わしい手続きもありません。少しでも便利で、面倒くさくないと感じていただけると嬉しいですね。
ーー乳がん検診だけでなく、婦人科の検診も一緒に受けられるのですね。
島田院長
はい、乳がん検診と子宮がん検診を同じ日にまとめて受けていただくことが可能です。「レディース検診」として複数のコースをご用意しており、多くの患者さんにご利用いただいています。
実は、乳腺科と婦人科は非常に密接な関わりがあります。例えば、乳がんのホルモン療法薬の副作用で子宮体がんのリスクが上がることがありますし、逆に更年期障害のホルモン補充療法で乳がんのリスクが上がることもあります。また、近年注目されている「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」の方は、その名の通り乳がんと卵巣がんの両方のリスクが高いため、両科の連携によるきめ細やかなフォローが不可欠です。
女性の健康をトータルでサポートするという観点から、この2つの診療科が連携することは非常に重要だと考えています。

3Dマンモグラフィで「痛くない・見逃さない」検診へ|検査の不安を取り除くために行うピンクリボンブレストケアクリニック表参道の工夫
検診をためらう最大の理由として挙げられる「痛み」と「不安」。
その両方を解決するため、ピンクリボンブレストケアクリニック表参道では、最新鋭の医療機器の導入と、それを扱うスタッフの技術力向上に余念がありません。
検査の不安を安心に変えるための、クリニックの工夫についてお聞きしました。
ーーやはり「マンモグラフィは痛い」というイメージが根強く、敬遠する方も多いのではないでしょうか。
島田院長
そうですね、胸を挟んで圧迫するという検査方法から、「痛そう」というイメージが先行してしまっている面はあると思います。しかし、検査機器も年々進化しており、当院で導入しているマンモグラフィは、撮影時の痛みを軽減できるデザインになるなど、様々な工夫が凝らされています。実際に受けていただいた方からは、「想像していたよりずっと平気だった」というお声も多くいただきます。
また、痛みを和らげるコツとして、受診するタイミングも重要です。排卵後から生理が始まる直前は乳房が張りやすく、痛みを感じやすいため、この時期は避けるのが無難です。生理が終わってから1週間後くらいが、最も乳房が柔らかく、痛みを感じにくいベストタイミングです。

ーー日本人は「高濃度乳房」の人が多く、マンモグラフィではがんが見つかりにくいと聞きました。
島田院長
高濃度乳房(デンスブレスト)とは、乳腺組織の割合が多く、マンモグラフィの画像で白く映るタイプの乳房のことです。乳がんのしこりも白く映るため、乳腺組織に隠れてしまい、がんが見つかりにくいことがあります。
そこで当院では、3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)を導入しています。これは、乳房を様々な角度から断層撮影することで、乳腺としこりの重なりを分離して観察できる最新の技術です。これにより、従来では見つけにくかった小さな病変や石灰化も鮮明に捉えることが可能になり、診断の精度が格段に向上しました。
さらに、超音波(エコー)検査を組み合わせることで、マンモグラフィの弱点を補い、より小さな兆候も見逃さない、精度の高い検診を実現しています。

ーー検査を行うスタッフの方々も、非常に専門性が高いそうですね。
島田院長
乳腺診療においては、医師だけでなく、検査を行う診療放射線技師や臨床検査技師にも高度な専門性が求められます。当院の技師は皆、マンモグラフィや超音波検査の技術はもちろん、乳がん診療全般について専門的に学んでおり、豊富な知識と経験を兼ね備えています。検査や診断、検査機器の質を高く保つために、日本乳がん検診精度管理中央機構2が行っている認定試験に合格した医師、技師、検査機器で診療を行い、定期的に院内勉強会を開いて症例検討を行ったり、フィードバックの機会を持ったりと、常に自己研鑽を重ねています。
また、受付担当者も含めた全スタッフが「ピンクリボンアドバイザー」の資格を取得してます。お電話などで検査や病気についてお問い合わせいただいた際にも、一人ひとりが正しい知識をもとに、患者さんの心に寄り添った対応ができるよう心がけています。
ーーそもそも、乳がん検診は何歳くらいから受け始めるのが良いのでしょうか?
島田院長
一般的に、自治体などが行う対策型検診は40歳から推奨されています。しかし、ご家族に乳がんや卵巣がんになった方がいるなど、遺伝的なリスクが高い場合は、より若い年代での発症の頻度が高いことが分かっており、自治体検診のご案内が来るより早い年齢からの検診が必要です。アメリカでは、ご家族が乳がんと診断された年齢のマイナス10歳から検診を始めることが推奨されています。
乳がんの発症のリスクや遺伝的なリスクや服薬歴、生活習慣などによっても異なるため、大切なのは、画一的な基準に当てはめるのではなく、ご自身がいくつからどのような検診を受けるのが良い状態なのかを知り、生涯の検診プランを立て、適切な検診を受けることです。そのためにも、まずは20代、30代のうちに一度乳腺専門クリニックなどで検査を受けて、ご自身のリスクや乳房の状態を把握し、自分自身の検診プランを相談することをお勧めします。
乳がんは他の臓器のがんに比べ若い年代から発症する傾向がありますが、最近は年齢が高い方の乳がん発症が増え70代の乳がん発症も珍しくありません。乳がんは女性のもっともなりやすく、長い年代にわたり乳がん検診を心がける必要があります。年齢を重ねても「もう大丈夫だろう」とやめてしまうのではなく、生涯にわたってご自身の乳房に関心を持ち続ける「ブレスト・アウェアネス」の意識を持っていただきたいですね。

患者だけでなくスタッフも輝ける場所へ|専門家集団によるチーム医療と、女性が輝き続けるためのクリニックづくり
ピンクリボンブレストケアクリニック表参道の強みは、最新の医療設備だけではありません。
そこで働く「人」、そして「チーム」としての力こそ、「女性のためのクリニック」を体現するものだと考えられます。
ここでは、患者に寄り添う専門家集団としての取り組みと、女性医療者がキャリアを諦めることなく輝き続けられる場所でありたいという、島田院長のもう一つの熱い想いについて語っていただきました。
ーー医師だけでなく、看護師や技師の方々にも高い専門性が求められるのですね。
島田院長
精度の高い診断のためには、医師の読影力はもちろんですが、質の高い画像を撮影する診療放射線技師の技術や、病変を正確に捉える臨床検査技師の超音波検査の技術が不可欠です。当院のスタッフは皆、それぞれの分野で専門性を高めるための自己研鑽を常に続けています。
先ほども少しお話ししましたが、定期的に院内勉強会を開き、判断に迷った症例などをチーム全員で検討する機会を設けています。個々のスキルアップだけでなく、チーム全体の診断レベルの底上げを図り、クリニック全体で一人の患者様を多角的に見る、という意識を常に共有しています。
ーーチームとして患者様と向き合う上で、大切にしていることは何ですか?
島田院長
患者様がリラックスして、何でも話せる雰囲気を作ることです。そのために、受付での最初のご挨拶から、看護師によるカウンセリング、技師による検査、そして医師による診察まで、すべての場面で患者様の不安に寄り添うことを心がけています。
特に、初診時のカウンセリングでは看護師がじっくりとお話をお伺いします。医師を前にすると緊張して言いたいことが言えなくなってしまう方もいらっしゃいますから。そこで不安や疑問を解消していただくことで、その後の検査や診察もスムーズに進みます。やはり、スタッフ全員が「ピンクリボンアドバイザー」の資格を持っていることも、患者様の心に寄り添う上で大きな力になっていると感じます。
ーー先生は、このクリニックを「女性医療者が働き続けられる場所にしたい」とも考えていらっしゃるそうですね。
島田院長
医師や看護師、技師といった医療の世界は、昔から女性が多く活躍していますが、残念ながら出産や育児などを機にキャリアを中断せざるを得なかったり、第一線から離れてしまったりするケースが今でも少なくありません。
特に乳腺外科の分野は、外科系ということもあり男性医師の割合が多いのが現状です。スキルと情熱を持った女性医療者が、ライフステージの変化によってそのキャリアを諦めることなく、専門性を維持しながら働き続けられる。当院が、そんな女性たちの受け皿のような存在になれたらと考えています。患者様が安心して頼れるクリニックであるためには、まずそこで働くスタッフ自身が、やりがいを持って輝き続けられる場所でなければならないと思っています。

「知る」ことが、あなたと大切な人を守る力に|ピンクリボンアドバイザーという輪の広がり
島田院長は、クリニックという枠を越え、社会全体に対する啓発活動にも積極的に携わっています。
その中心にあるのが、日本におけるピンクリボン運動の推進です。
25年にわたる活動の中で見えてきた課題と、それを乗り越えるために始めた取り組み「ピンクリボンアドバイザー制度」について伺いました。
ーーピンクリボン運動を25年続けてこられて、どのような変化を感じますか?また、課題は何でしょうか?
島田院長
私が認定NPO法人乳房健康研究会を立ち上げ、活動を始めた2000年当初、乳がん検診の受診率はわずか7%ほどでした。今では認知度も高くなり、受診率も40%台まで上がってきました。これは大きな進歩ですが、欧米の先進国では70%以上の女性が受診していますし、特に福祉先進国のフィンランドでは80%以上が受診していることを考えると、まだまだ道半ばです。
なぜ受診に繋がらないのか。アンケート調査をすると、「自分はがんにならない」「症状がないから大丈夫」といった思い込みや、「どこで受ければいいかわからない」高そう、時間がない「痛そう、怖い」といった漠然とした不安が、依然として大きな壁になっていることがわかります。この最後の「もう一歩」を後押しする何かが、まだ足りていないのです。
ーーその「もう一歩」を後押しするために始められたのが「ピンクリボンアドバイザー制度」なのですね。
島田院長
はい。調査をさらに進めると、検診を受けた方のきっかけで非常に多かったのが、「家族や友人など、身近な人からの勧めや声掛け」だったのです。「実際に受けたら痛くなかったよ」「すぐ終わったよ」「この病院が良かったよ」という具体的な経験談が、何よりも意識を行動にかえる後押しになるのだと気づきました。
そこで、乳がんに関する正しい知識を持ち、自信を持ってその大切な一言を身近な人に伝えてくれる人を増やそう、と考えたのがこの制度です。2013年に認定試験をスタートし、今では全国で約2万人ものアドバイザーが誕生しています。主婦の方から学生、医療関係者まで、様々な方が自分のため、そして誰かのために学び、活動の輪を広げてくれています。
ーーアドバイザーの方々は、具体的にどのような活動をされているのですか?
島田院長
活動は様々です。ご自身の家族や友人に検診を勧めてくださることも立派な活動ですし、全国の中学校や高校でがん教育の授業を行ったり、地域でピンクリボンイベントを企画・開催したりと、非常に多岐にわたります。
大切なのは、一人ひとりが「自分にできること」を考え、行動に移してくれることだと思います。この草の根の運動が、少しずつですが着実に、乳がんと闘うすべての人にやさしい社会、検診を受けやすい雰囲気につながるはずだと確信しています。

もし「異常あり」と診断されたら…?|乳がんの確定診断から治療、その後の人生まで寄り添うためのサポート体制
万が一、検査で異常が見つかった時、ピンクリボンブレストケアクリニック表参道はどのように対応してくれるのでしょうか?
ーー検査の結果は、いつ、どのようにして伝えられますか?
島田院長
症状があって受診された方や精密検査を進められて受診した方などには、検査を受けたその日のうちに、医師から直接結果をご説明します。 診察室の大きなモニターにマンモグラフィや超音波の画像を映し出し、一緒にご覧いただきながら、「なぜこの症状が起きているのか」「どこに異常の疑いがあるのか、あるいは異常はなかったのか」を、専門用語を避けて分かりやすくお伝えすることを心がけています。
診察が終わってお帰りになる際には、医師が説明した内容をまとめた結果報告書をお渡しします。結果用紙をその日にお渡しするのは、心配で頭がいっぱいの時にはなかなか診察室でお話したが記憶に正しく残らなかったりすることがありますから、お渡しする結果をご自宅でじっくり読み返したり、ご家族と情報を共有したりして正しく理解し定期的な受診を促すことにも役立てていただきたいからです。患者さんの疑問や不安をその日のうちに解消し、すっきりとした気持ちでお帰りいただくことを何よりも大切にしています。検診で受診された方は様々なメニューがあるのでお急ぎの方は検査だけ当日行い結果は後日郵送することもできます。検診はご自身が都合がよいと思えるメニューを選ぶことが継続できるコツです。

ーー精密検査が必要になった場合、どのような流れになるのでしょうか?
島田院長
画像検査でがんが疑われる所見があった場合は、その組織の一部を採取して良性か悪性かを調べる「生検(せいけん)」という精密検査を行います。当院では、超音波で確認しながら行う「コアニードル生検」や、マンモグラフィで石灰化を狙って組織を採取する「ステレオガイド下マンモトーム生検(VAB)(いわゆるマンモトーム)」といった、高度な精密検査を院内で受けていただくことが可能です。
採取した組織は、乳腺病理診断を専門とする信頼のおける病理医に診断を依頼し、より確実な確定診断につなげています。
ーーがんと診断された場合、その後の治療はどうなりますか?
島田院長
もし乳がんと診断された場合は、まず患者さんと一緒に、今後の治療をどこで、どのように進めていくかを相談しながら決めていきます。患者さんの病状やご希望、お住まいの地域などを考慮し、乳腺の専門的な治療を安心してお任せできる連携先の医療機関を複数ご提案させていただいています。病院が決まれば、そこへの予約や受診のサポートも当院で行いますのでご安心ください。
手術が終わった後は、多くの場合、ホルモン療法や抗がん剤治療といった薬物療法が長く続きます。その際の通院は、手術を行った大きな病院と当院とで連携する「二人主治医制」をとることが多いです。普段の通院やお薬の処方は通いやすい当院で行い、年に1回程度、大きな病院でもチェックを受ける、という形です。患者さんの負担を軽減しながら、切れ目のない手厚いフォローアップを心がけています。
ーー治療後の生活や、精神的な不安についても相談できますか?
島田院長
もちろんです。診断後や治療中に感じる様々な不安や疑問に寄り添うカウンセリング体制を整えています。看護師による相談や医師によるカウンセリング、あるいは他の医師の意見を聞きたい場合のセカンドオピニオンなど、患者さんが前向きに治療に取り組めるよう、多方面からサポートします。
状態が安定している方に対しては、オンライン診療にも対応していますので、遠方の方や体調が優れない時でも、ご自宅から相談していただくことが可能です。治療のことだけでなく、下着やウィッグの選び方など、日常生活のお悩みにもきめ細かく対応しています。

島田院長からのメッセージ「自分を後回しにしないで。あなたの輝く未来のために、今できること」
インタビューの最後に、島田院長からこの記事を読んでくださっているすべての女性へ、温かく、そして力強いメッセージをいただきました。
ーー先生が患者さんと向き合う上で、最も大切にされていることは何ですか?
島田院長
二つあります。一つは、「患者さんの疑問や不安は解決できたか」と常に自問自答することです。病気の有無を告げるだけでなく、なぜその症状が起きたのか、今後どうすれば良いのかをしっかりご説明し、納得していただくこと。そして、検査や診察に対して嫌な思いや疑問を残さず、異常がなかった方にはまた検診を続けていただき、異常があった方には前向きに治療に取り組んでいただけるように導くこと。これを何よりも大切にしています。
もう一つは、「自分が患者だったら受けたい医療を提供する」ということです。これは私自身だけでなく、スタッフ全員に毎月のミーティングで必ず伝えていることです。医療レベルの向上はもちろんのこと、快適な環境や温かい心遣いも含め、安心して受診していただけるための努力を、これからも積み重ねていきたいと思っています。
ーー乳がんのリスクを少しでも下げるために、日常生活でできることはありますか?
島田院長
確実な予防法がないのが現状ですが、乳がんになるリスクと再発のリスクを有意に下げることが科学的に証明されているのが「運動習慣」です。ある研究では、運動習慣がある方はそうでない方に比べて、リスクが25%も下がることが示されています。運動は乳がんだけでなく、メンタル不調や生活習慣病、ロコモの予防や、更年期障害の軽減だけでなく、乳がんになった場合の再発リスクを下げる、お薬の副作用を軽減するなど、様々なメリットがありますので、ぜひ日常生活に取り入れてほしいですね。
そしてもう一つ、毎月のセルフチェック(自己検診)を習慣にしていただきたいです。お風呂で体を洗うついでや、お風呂上がりにボディクリームを塗るついででも構いません。普段から自分の乳房の状態を知っておくことで、小さなしこりや引きつれといった「いつもと違う」変化に気づきやすくなります。ブレストアウエアネス(乳房を意識する生活習慣)これが早期発見への第一歩です。
ーー最後に、検診を受けることを迷っている読者へメッセージをお願いします。
島田院長
女性は、妻、母、娘、そして社会の一員として、たくさんの役割を担い、自分のことを後回しにしてしまいがちです。でも、あなたが健康で輝き続けることこそが、あなたの大切な人たちの幸せにもつながるはずです。どうか、ほんの少しの時間でいいので、ご自身の体を慈しむための時間を作ってあげてください。
かつては、治療によってキャリアや出産といった夢を諦めなければならない、という時代もありました。しかし、医療は日々進歩しており、今では一人ひとりのライフプランに合わせた治療を選択できるようになっています。出産を望む方には、治療前に産める準備をあらかじめ行う(妊孕性の温存)こともできますし、また手術で失われた乳房を取り戻す乳房再建手術も今や治療の一連として保険適応となり当たり前に行われる治療となりました。乳がんは、早期に発見し、適切な治療を受ければ、再び自分らしい日常を取り戻せる「闘える病」です。
検診を受けるのは、少し勇気がいることかもしれません。どうぞ、気軽にクリニックの扉を叩いてくださいね。

ピンクリボンブレストケアクリニック表参道
| 診療科目 | 乳腺科、放射線科、乳がん検診、 マンモグラフィ検査、子宮がん検診 |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目3番13 FPG links OMOTESANDOⅢ |
| 診療日 | (月・金) 10:00〜14:00 / 15:30〜19:00 (火・水) 10:00〜14:00 / 15:30〜20:00 (木) 10:00〜14:00 / 15:30〜17:30 (土・日) 9:30〜13:00 / 14:00〜18:00 |
| 休診日 | 第1木曜日・祝日 |
| 院長 | 島田 菜穂子 |
| TEL | <ご予約> 03-3401-7700 <お問い合わせ> 03-3401-7707 |
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」A2出口より徒歩1分 |