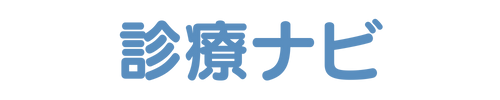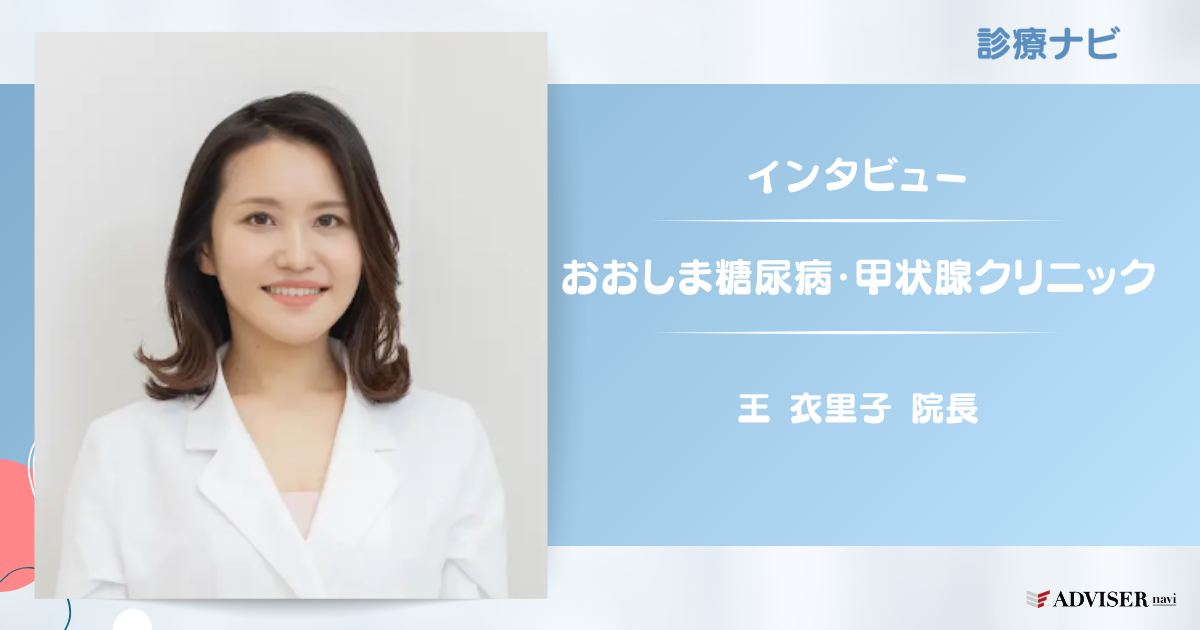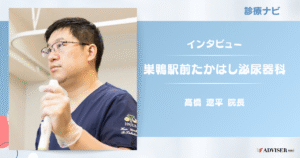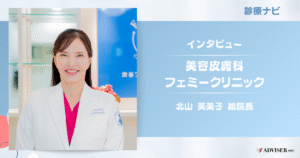2025年11月18日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「最近、なんとなく体がだるい」
「健康診断で血糖値を指摘されたけれど、どこに行けばいいかわからない」
そんな漠然とした不安を抱えていませんか?糖尿病や甲状腺の病気は、初期症状が乏しく、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。
今回取材に伺ったのは、阪急電鉄京都本線「総持寺駅」からすぐの場所に位置するおおしま糖尿病・甲状腺クリニック。院長を務めるのは、糖尿病専門医としての豊富な経験を持つ王 衣里子(おう えりこ)先生です。
「患者さまに適切な医療を、適切に届けたい」と語る王院長。地域医療の枠を超えた充実した診療体制について、たっぷりとお話を伺いました。
王 衣里子 院長の医師としての原点
まずは、王院長がどのような経緯で医師を目指し、なぜ現在の専門分野を選ばれたのか。
その原点と人柄に迫ります。
ーー先生は、幼い頃から医師を目指されていたのですか?
王院長
いえ、実は幼い頃は全然医師になろうとは思っていなかったんですよ(笑)。私が進路について真剣に考え始めたのは、高校2年生から3年生にかけての時期でした。それまでは中高一貫校に通っていて、勉強よりもクラブ活動に熱中する毎日でしたね。
ただ、私の父が整形外科医として働いていて、姉も医学部に通っていたんです。そうした家族の姿を身近で見ていたことと、高校生になって「将来どうしようか」と考えた時に、「このままではいけない、何か人の役に立つ仕事がしたい」と強く思うようになりました。クラブ活動を辞めて、覚悟を決めて受験勉強に専念したのはそこからですね。
ーー高校生での大きな決断だったのですね。医学部を経て、数ある診療科の中から「糖尿病内科」「甲状腺内科」を選ばれた理由は何だったのでしょうか?
王院長
医学部で様々な科を回る中で、自分の適性を考えたんです。私は外科のように手術で瞬発的に処置をするよりも、内科のように患者さまの病態や診断についてじっくり頭で考え、お薬の選択などを検討していくスタイルのほうが合っていると感じました。救急のような瞬発的な対応よりも、じっくりと考えて治療方針を組み立てる方が、自分の性格に合っていると思ったのです。
その中でも、研修医時代に一番「楽しい」「やりがいがある」と感じたのが糖尿病内分泌の分野でした。糖尿病は「生活習慣病」と言われる通り、患者さまの日々の生活に密接に関わっています。単に薬を出して終わりではなく、その方のライフスタイルや背景に寄り添って治療を進めることで、予後(病気の見通し)が改善することがあるんです。「他の病院では血糖値が下がらなかったけれど、先生のところで診てもらってすごく良くなった」など、患者さまからそう言っていただけた時に、この道を選んで本当によかったなと感じますね。
ーーじっくり考えるのがお好き、という点は今の丁寧な診療スタイルにも繋がっていますね。
王院長
そうかもしれませんね。糖尿病も甲状腺疾患も、長く付き合っていく病気ですから、患者さまとじっくり向き合うことが何より大切だと考えています。糖尿病専門医を取得した後、甲状腺専門クリニックでの勤務も経験し、多くの患者さまを診させていただきました。その経験が今の診療のベースになっています。
常に最新の医学知識を学び続け、お一人おひとりに最適な治療を提供すること。それが私の医師としての信念です。
おおしま糖尿病・甲状腺クリニックを開院した理由とクリニックの特徴
2024年に総持寺駅前に開院されたおおしま糖尿病・甲状腺クリニック。
なぜこの場所で開院したのでしょうか?
ーーこの茨木市・総持寺駅前という場所で開業されたきっかけを教えてください。
王院長
もともと、このビルの2階で父が整形外科を開業していたんです。私が父のクリニックを手伝いに行っていた時に感じたのが、「この地域には、糖尿病や甲状腺を専門的に診られるクリニックが少ない」ということでした。
整形外科に来られる患者さまの中にも、実は糖尿病や甲状腺のトラブルを抱えている方がたくさんいらっしゃいます。でも、近くに専門の病院がないから、わざわざ遠くの大きな病院まで通われている。「もし、父のクリニックと同じビルに内科があれば、患者さまの移動の負担も減らせるし、より専門的な医療を提供できるのではないか」と考え、このビルの3階での開業を決めました。
ーーお父様が整形外科、そしてご主人が泌尿器科を担当されていると伺いました。家族で異なる専門性を持っているというのは、患者さまにとってどのようなメリットがあるのでしょうか?
王院長
そうですね、これは当院の非常に大きな強みだと思っています。実は、糖尿病・甲状腺・整形外科・泌尿器科というのは、互いに深く関連し合っているんです。
例えば、整形外科に通われている骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の患者さま。骨が脆くなる原因の一つに、実は糖尿病や甲状腺機能亢進症(バセドウ病)が隠れていることがあります。逆に、糖尿病の患者さまは骨折のリスクが高まることも知られています。
また、リウマチなどの自己免疫疾患をお持ちの方は、同じく自己免疫疾患である甲状腺の病気(橋本病など)を併発していることも珍しくありません。
ーーなるほど、病気は繋がっているのですね。泌尿器科との連携はいかがですか?
王院長
夫が担当する泌尿器科とも、密に連携しています。
糖尿病の合併症の一つに「神経障害」がありますが、これが原因で排尿障害(おしっこが出にくい、回数が多いなど)やED(勃起不全)に悩まれる男性患者さまは非常に多いんです。また、女性の方でも頻尿や膀胱炎を繰り返す方がいらっしゃいます。
通常なら、「内科に行って、そのあと別の泌尿器科に行って…」となるところを、当院なら同じビル内ですぐに専門的な診察が受けられます。「平日には私が内科を診て、土曜日には夫が泌尿器科の専門外来を行う」といった連携もスムーズです。カルテや情報を共有しながら、「家族みんなで一人の患者さまを支える」 という体制が取れるのは、地域医療として理想的な形ではないかなと思っています。

早期発見・早期治療のカギとなる「糖尿病内科」の取り組み
ここからは、メインの診療科目である「糖尿病」について深掘りします。
クリニックならではの「スピード検査」や「合併症対策」、そして患者さまが抱える治療への不安について伺いました。
ーー糖尿病は「自覚症状がない」まま進行すると聞きます。どのような症状があったら受診すべきでしょうか?
王院長
糖尿病は初期段階ではほとんど自覚症状がありません。それが一番怖いところなんです。ただ、血糖値が高い状態が続くと、体からのサインとして次のような症状が出ることがあります。
・以前よりも喉が渇く、水をよく飲む
・トイレの回数が増えた
・尿の匂いが気になる
・食べているのに体重が急に減った
・全身の倦怠感が強い
・手足の痺れやむくみがある
もしこれらに当てはまる場合や、健康診断で「血糖値が高め」「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が高い」と指摘された場合は、放置せずにすぐにご相談いただきたいですね。
ーー「すぐに結果を知りたい」という患者さまも多いと思いますが、おおしま糖尿病・甲状腺クリニックでは検査体制にこだわりがあるそうですね。
王院長
はい、そこは非常にこだわりました。一般的なクリニックですと、血液検査の結果が出るのに数日から1週間かかり、「結果はまた来週聞きに来てください」となることが多いですよね。でも、患者さまからすれば、不安な気持ちを抱えたまま1週間過ごすのは辛いですし、治療のスタートも遅れてしまいます。
当院では、糖尿病の診断に不可欠な「HbA1c(過去1〜2ヶ月の血糖の状態を示す数値)」や「血糖値」を、その日のうちに院内で測定できる機器を導入しています。来院されて検査を行い、その日の診察の中で「今の状態」をお伝えし、必要であればその場でお薬の調整や治療方針を決めることができます。
「今日結果がわかるから助かる」「仕事が忙しいから何度も通わなくて済むのは嬉しい」と、患者さまからも大変喜ばれていますね。
ーー糖尿病と診断されると「一生薬を飲み続けなければならない」「インスリン注射は怖い」と不安に思う方も多いと思います。実際はいかがでしょうか?
王院長
そういった不安をお持ちの方は本当に多いと思います。まずお伝えしたいのは、「糖尿病=一生薬漬け」とは限らないということです。初期の段階で発見し、適切な食事・運動療法を行えば、お薬なしで血糖値を良好に保てるようになる方もたくさんいらっしゃいます。また、一時的にインスリン治療が必要になっても、膵臓の機能が回復すれば飲み薬に戻せるケースもあります。
インスリン治療に対しても「最後の手段」「一度始めたらやめられない」という誤解がありますが、実は早めに導入することで膵臓を休ませ、機能を温存するための有効な手段なんです。当院では、患者さまの「怖い」「不安だ」という気持ちにしっかりと耳を傾けます。その上で、医学的な必要性と患者さまのライフスタイルを照らし合わせ、「納得できる治療法」を一緒に探していきます。決して一方的に治療を押し付けることはありませんので、安心してください。
ーーそれは心強いです!しかし、 糖尿病といえば「合併症」も怖いです。
王院長
そうですね。糖尿病治療の最大の目的は、血糖値を下げることそのものではなく、その先にある「合併症を防ぐこと」にあります。私たちはよく「しめじ」という言葉を使って説明するのですが、ご存知ですか?
ーー「しめじ」ですか? 初めて聞きました。
王院長
糖尿病の3大合併症の頭文字をとった覚え方なんです。
「し」…神経障害(手足のしびれ、痛み、感覚の麻痺など)
「め」…目の障害(糖尿病網膜症。進行すると失明のリスクも)
「じ」…腎臓の障害(糖尿病腎症。悪化すると透析が必要に)
さらにこれらに加えて、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる動脈硬化のリスクも高まります。当院では、こうした合併症を未然に防ぐために、定期的な検査(尿検査、血液検査など)はもちろん、神経障害のチェックや動脈硬化の検査も院内で行える体制を整えています。「ただ血糖値を測るだけ」ではなく、「全身の状態を守る」という視点で診療を行っています。
ーー治療については、やはり厳しい食事制限などが必要になるのでしょうか?
王院長
いえ、決して「あれもダメ、これもダメ」と厳しく制限するわけではありません(笑)。治療方法は、患者さま一人ひとりの生活スタイルや希望によって「オーダーメイド」で決めていく必要があります。
例えば、お薬一つとっても、食欲を改善させて体重を減らす薬、尿から糖を出す薬、インスリン分泌を促す薬、インスリンの効きを良くする薬など、今は非常に多くの選択肢があります。「1日3回飲むのは忘れそうだから1回が良い」「注射には抵抗があるから飲み薬が良い」といったご希望も尊重します。
医学的に「これがベスト」という治療法を押し付けるのではなく、患者さまが「これなら続けられそう」と思える方法を一緒に探していく。それが私の診療ポリシーです。
無理なく続ける「栄養指導」と、注目の「肥満症外来」について
糖尿病治療やダイエットにおいて重要な「食事」。
そして最近話題の「GLP-1ダイエット(肥満症治療薬)」についても、専門医の視点からお話を伺いました。
ーー食事療法というと「先生に怒られる」というイメージを持つ方もいるかもしれません…。
王院長
当院に関しては、その心配は全く無用です。院内には管理栄養士が在籍していて、栄養指導を行っているのですが、診察室にいると、栄養指導室から患者さまとスタッフの大きな笑い声がよく聞こえてくるんです。
「先生、実はこないだケーキ食べちゃって…」と私には言いにくいことでも、管理栄養士には「実はね…」と正直に話してくださる患者さまも多いですね。私たちの栄養指導は、患者さまを責めるものではありません。「コンビニ食が多いなら、この組み合わせにしてみましょう」「食べる順番をこう変えるだけで血糖値が上がりにくくなりますよ」といった、ライフスタイルに合わせた現実的なアドバイスを行っています。
「先生は怖いかも」と構えず、健康のパートナーとして頼っていただければ嬉しいです。
ーー笑い声が聞こえるような栄養指導、素敵ですね。最近では「痩せる薬」として「マンジャロ」などが話題ですが、こちらのクリニックでも「肥満症外来」を行っているのでしょうか?
王院長
はい。当院では、なかなか痩せられない方や、健康診断で体重・血圧などを指摘された方のために「肥満症外来(自由診療含む)」を開設しています。
おっしゃる通り、最近は「マンジャロ」や「ウゴービ」といったGLP-1受容体作動薬が注目されていますね。これらはもともと糖尿病の治療薬ですが、食欲中枢に働きかけて食欲を自然に抑えたり、胃の動きを緩やかにして満腹感を持続させたりする効果があり、高い減量効果が期待できます。
ーー具体的にはどのような方が対象になるのでしょうか?
王院長
まず、糖尿病の診断がついている方で、肥満がありインスリンの効きが悪くなっているような場合には、保険適用で「マンジャロ」などを使用することがあります。一方で、糖尿病ではないけれど肥満にお悩みの方には、自由診療(自費)での対応となりますが、同じ成分を含む「ゼップバウンド」や「ウゴービ」などの処方が可能です。
ただし、誰にでも処方するわけではありません。当院では、医学的な適応(BMIの数値や合併症の有無など)をしっかり判断した上で処方しています。
ーーやはり、医師の管理下で行うことが大切なんですね。
王院長
その通りです。非常に効果が高いお薬ですが、適応のない方が安易に使うと、吐き気などの副作用が強く出たり、必要な栄養まで摂れなくなったりするリスクがあります。「ただ痩せればいい」ではなく、「健康的に、安全に痩せる」ことがゴールです。
当院では、お薬の力だけでなく、先ほどの管理栄養士による食事・生活習慣のサポートも組み合わせて、リバウンドしにくい体作りをお手伝いしています。「健康診断で痩せなさいと言われたけれど、どうすればいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
女性に多い「甲状腺疾患」|見逃されがちなサインとは
糖尿病と並んで専門とされている「甲状腺内科」。
特に女性に多い病気ですが、その症状は分かりにくく、発見が遅れることも多いといいます。
ーー甲状腺の病気は、どのような症状が出るのでしょうか?
王院長
甲状腺は、のどぼとけの下にある蝶ネクタイのような形をした臓器で、全身の代謝をコントロールするホルモンを出しています。このホルモンのバランスが崩れると、本当に様々な症状が出るのですが、どれも「よくある不調」に似ているため、見逃されやすいんです。
例えば、甲状腺ホルモンが出すぎる「バセドウ病(甲状腺機能亢進症)」の場合は、代謝が良くなりすぎて、以下のような症状が出ます。
・動悸がする、脈が速い
・暑がりになり、汗を大量にかく・食べているのに体重が減る
・イライラする、手が震える
更年期障害と間違われることも多いですね。
逆に、ホルモンが不足する「橋本病(甲状腺機能低下症)」の場合は、
・寒がりになる
・むくみが出る、体重が増える
・やる気が出ない、眠気が強い
・皮膚が乾燥する、髪が抜ける
といった症状が現れ、こちらは「うつ病」や「ただの疲れ」と誤診されてしまうこともあります。
ーー「なんとなくしんどい」の原因が甲状腺だった、ということもあるのですね。
王院長
そうなんです。「最近疲れが取れないな」と思って受診したら、実は甲状腺の病気だったというケースは非常に多いです。特に甲状腺疾患は20代〜50代の女性に多く見られます。また、遺伝的な要素も強いため、「母親や姉妹が甲状腺の病気を持っている」という方は要注意です。
もしご自身で首元(のどぼとけの下あたり)を触ってみて、「なんとなく腫れている気がする」と感じたら、一度検査を受けてみてください。ただ、自分でわかるほど腫れているときはかなり大きくなっている場合もあるので、気になる症状があれば早めの受診をおすすめします。
ーー甲状腺の検査も、やはり当日に結果がわかるのでしょうか?
王院長
はい。糖尿病と同様に、甲状腺ホルモンの血液検査も院内で即日結果が出ます。また、超音波(エコー)検査も私がその場で行いますので、甲状腺の大きさや、腫瘍(しこり)ができていないかどうかも、その日のうちに診断可能です。
ーー女性の患者さまが多いとのことですが、妊娠や出産といったライフイベントとの関わりについても教えてください。
王院長
とても大切なポイントですね。甲状腺ホルモンは、妊娠の成立や赤ちゃんの成長に深く関わっています。甲状腺の機能に異常があると、不妊の原因になったり、流産のリスクが高まったりすることがあります。しかし、適切にお薬でコントロールすれば、妊娠・出産も問題なく可能ですし、健康な赤ちゃんを授かることができます。
実際に「なかなか妊娠しないと思っていたら、甲状腺の病気が見つかった」という方も少なくありません。当院では、妊娠を希望される方や、妊娠中の甲状腺管理もしっかりサポートしています。女性医師として、そうしたデリケートなお悩みにも親身になって寄り添いたいと考えていますので、「将来妊娠を考えている」という方も、ブライダルチェックのような感覚で一度検査を受けていただければと思います。
忙しい現役世代も安心|「通いやすさ」を追求した環境づくりと女性医師としての視点
クリニック選びにおいて、医療の質と同じくらい大切なのが「通いやすさ」です。
王院長がこだわったクリニックの環境づくりについて伺いました。
ーー働き盛りの世代にとって、通院の時間は大きなハードルです。待ち時間対策などはされていますか?
王院長
はい、そこは非常に重視しています。私自身も働く身ですし、「病院での待ち時間がいかに大変か」は痛いほど分かりますから(笑)。当院では、患者さまの貴重な時間を無駄にしないよう、Web予約システムを導入しています。事前に予約をしていただくことで、スムーズにご案内できるよう工夫しています。
また、お会計の待ち時間も短縮できるよう、自動精算機やキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネーなど)に対応しています。さらに、「クロンスマート決済」というシステムも導入しており、診察が終わればお会計を待たずにそのまま帰宅し、後で自動引き落としにすることも可能です。「仕事の合間に来たい」「子供のお迎えがあるから急いでいる」という方にも、ストレスなく通っていただける環境を整えています。
ーー先生ご自身が女性医師であることも、患者さまにとっては安心材料の一つだと感じます。
王院長
そう言っていただけると嬉しいです。甲状腺の病気は女性に多いですし、糖尿病の悩みも、生活習慣や家族の食事作りなど、女性ならではの悩みとリンクすることが多々あります。
「男性の先生にはちょっと話しにくいな…」と感じるような体の不調や、デリケートな悩みも、同性として共感しながらお聞きできるのが私の強みかもしれません。クリニック全体としても、スタッフ一同が優しく、話しやすい雰囲気づくりを心がけています。「病院は緊張する場所」ではなく、「地域の保健室」のような感覚で、気軽に頼っていただければ幸いです。
患者さまへのメッセージと、おおしま糖尿病・甲状腺クリニックが目指す未来
ーー開院から少し経ちましたが、これからのクリニックの目標を教えてください。
王院長
まだ開院したばかりですが、まずは「糖尿病と甲状腺といえば、おおしまクリニック」と地域の方々に信頼していただける存在になりたいですね。今はネットで検索して来てくださる方も多いですが、通りがかりに「あ、ここに専門の先生がいるんだ」と知って来院される方も増えています。
今後は、地域のニーズに合わせて、診療の幅も少しずつ広げていきたいと考えています。保険診療をベースにしつつ、今回お話しした肥満症外来のような、地域の皆さまが潜在的に求めているような医療サービスも提供していけたらと思っています。
ーー最後に、この記事を読んでいる読者の方へメッセージをお願いします。
王院長
病院に行くとき、「こんな些細なことで行っていいのかな」「怒られたらどうしよう」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。私たちは決して怖い場所ではありません。
糖尿病も甲状腺も、早期発見ができれば、その後の人生を健康に楽しく過ごすことができます。「喉が渇く」「体重が変わった」「なんとなくしんどい」そんなちょっとした体の変化が、体からの重要なサインであることもあります。
私たちが目指すのは、「すべての患者さまに適切な医療を、適切にご提供すること」。お一人おひとりのライフスタイルに寄り添い、無理なく続けられる治療を一緒に考えていきます。ご家族のことで気になることがある場合も、どうぞお気軽に相談にいらしてください。スタッフ一同、笑顔でお待ちしております。
おおしま糖尿病・甲状腺クリニック
| 診療科目 | 糖尿病内科・甲状腺(代謝内科・内分泌科)・泌尿器科 |
|---|---|
| 住所 | 〒567-0806 大阪府茨木市庄2丁目19-14 3階 |
| 診療日 | (月・火・水・木・金)9:00〜14:00 (土)9:00〜17:00 ※第1土曜日は内科診療、第2、第3、第4、第5土曜日は泌尿器科担当医師による診察となります。 ※土曜日の内科初診をご希望の方は電話でご相談ください。 ※ワクチンと検診は完全予約制ですので、事前にお電話でご予約ください。 |
| 休診日 | 日曜・祝日 |
| 院長 | 王 衣里子 |
| TEL | 072-646-6816 |
| 最寄駅 | 阪急電鉄京都本線「総持寺駅」西出口から徒歩約1分 |