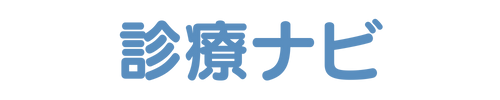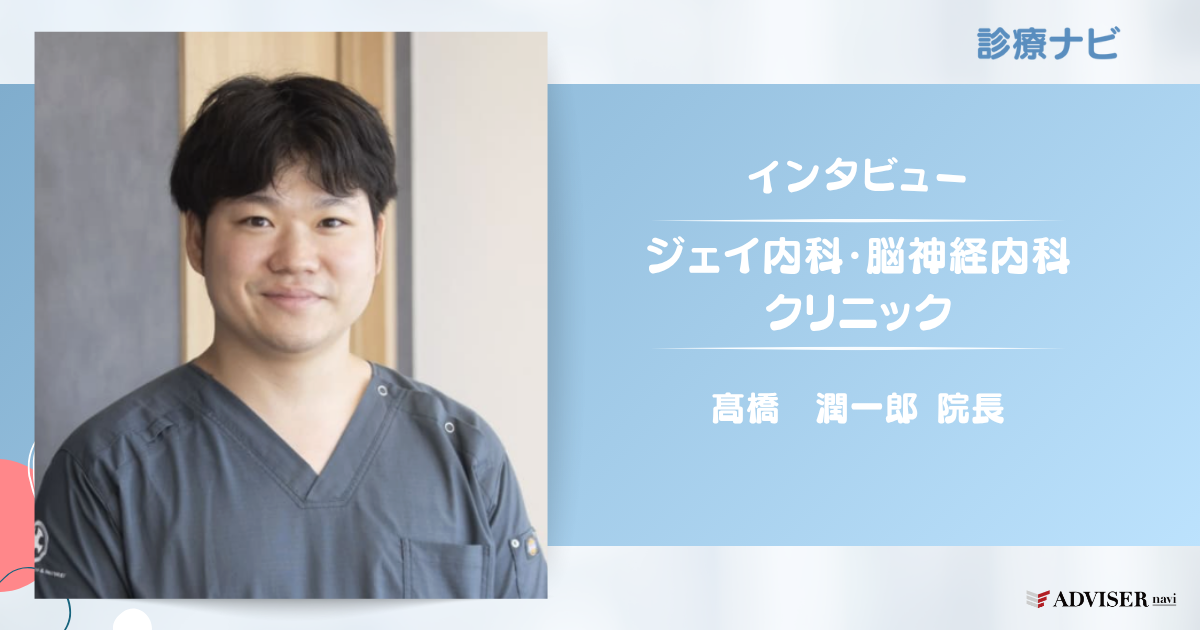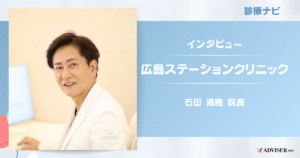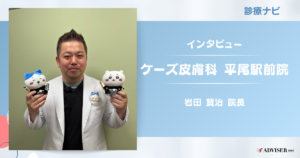2025年10月31日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「最近、物忘れがひどくなった」
「手足が震えて、うまく力が入らない」
「歩きにくくなって、よく転ぶようになった」
ご自身やご家族のそんな症状を、「もう年だから仕方ない」と諦めていませんか?
その不調は、もしかしたら加齢によるものではなく、「脳神経内科の病気」かもしれません。
しかし、症状が進むと通院自体が難しくなり、専門的な医療を諦めてしまうケースも少なくありません。
今回は、「通院が困難な方にこそ、専門医療を届けたい」という信念のもと、我孫子市・柏市で「脳神経内科医による訪問診療」に力を注ぐ、「ジェイ内科・脳神経内科クリニック」の髙橋潤一郎院長にインタビューを実施しました。
今、脳神経内科医が在宅医療に必要な理由や先生の情熱やビジョンについて伺いました。
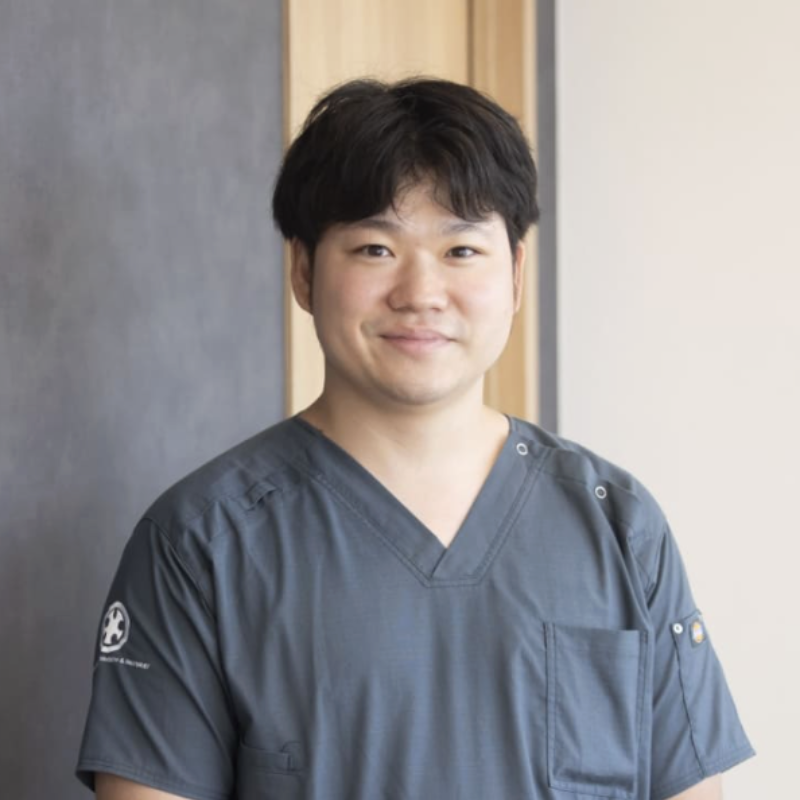
髙橋 潤一郎
ジェイ内科・脳神経内科クリニック院長。東京慈恵会医科大学卒。日本内科学会認定内科専門医・日本神経学会認定神経内科専門医として、脳卒中・パーキンソン病・認知症・頭痛などの診療に加え、脳神経内科医による訪問診療にも注力する。
詳細プロフィール
– 所属・役職:
ジェイ内科・脳神経内科クリニック 院長
医療法人社団 J-group
– 専門領域:
脳卒中
パーキンソン病
認知症
頭痛
脳神経内科医による訪問診療・訪問リハビリ
– 資格:
日本内科学会認定 内科専門医
日本神経学会認定 神経内科専門医
日本脳神経超音波学会認定 脳神経超音波検査師
脳卒中療養指導士
ボトックス療法認定医
Japanese Medical Emergency Care Course(JMECC)
– 学歴:
2017年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業
– 経歴:
2017年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業
2017年〜 東京慈恵会医科大学附属病院・第三病院・国立精神神経医療研究センターなどで脳神経内科分野の研鑽
2023年 ジェイ内科・脳神経内科クリニック 開院
– 学会・役職:
日本内科学会
日本脳卒中学会
日本神経学会
日本脳神経超音波学会
日本頭痛学会
日本認知症学会
– 著書・論文:
『頸部帯状疱疹罹患後に皮疹を認めた皮膚分節より広範囲な多発脳神経・髄節障害を呈した73歳男性例』(臨床神経学 2022)J-STAGE
『Ratio of lymphocyte to monocyte area under the curve as a novel predictive factor for severe infection in multiple sclerosis』(Front Immunol 2023)frontiers
『Diagnostic Yield of Chilaiditi’s sign in Advanced-Phase Late-Onset Pompe Disease』(J Neuromuscul Dis 2022)Journal of Neuromuscular Diseases 9
『Serum arachidonic acid levels is a predictor of poor functional outcome in acute intracerebral hemorrhage』(Clin Biochem 2021)sciencedirect
『“Frog Sign”: Uncovered Condition of Long-term Non-invasive Positive Pressure Ventilation in Late-onset Pompe Disease』(Clin Image Case Rep J 2022)literaturepublishers
『Pseudo-porencephaly Mimicking Multiple Intracerebral Hemorrhages』(Intern Med 2021)J-STAGE
『Hyperadrenergic Orthostatic Hypotension With Pure Peripheral Sympathetic Denervation Associated With Sjogren’s Syndrome』(Cureus 2021)Cureus
「脳神経内科医こそ、訪問診療を行うべき」|髙橋 潤一郎院長が抱いた強い使命感
東京慈恵会医科大学を卒業後、同大学病院や国立精神・神経医療研究センターといった第一線で研鑽を積んでこられた髙橋院長。
ご経歴は、まさに脳神経内科のエキスパート。
そんな髙橋院長が、なぜ若くして開業し、専門性の高い「訪問診療」の道を選んだのでしょうか。
ーー先生が医師を目指した理由について教えていただけますか?
髙橋院長
子どもの頃から「人の心と体のつながり」に漠然とした興味がありました。大学で臨床神経学に触れたとき、脳という臓器が、人間の思考、感情、行動のすべてを司る“中枢”であることに、あらためて深い感動を覚えたんです。
脳神経内科は、いわば「目に見えない世界を扱う医学」とも言えます。MRIなどの画像や血液検査の数値だけで判断するのではなく、患者さんの表情や声のトーン、話し方、歩き方、ちょっとした仕草の変化から、疾患のサインを読み取っていく。診断用のハンマー(打腱器)ひとつで、体の中のどこに異常があるのかを突き止めていく。そうした医師の「人を観る力」が深く問われる領域であることに、強く惹かれました。
ーーその中でも、「脳神経内科」という専門分野に惹かれた理由は何ですか?
髙橋院長
脳に関する病気は、実は非常に多く、身近なものです。例えば認知症は、90歳を超えると7割以上の方の脳にアルツハイマー型の変化が見られるとも言われ、誰もがいつかは向き合う可能性のある疾患です。他にも、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害、そしてパーキンソン病など、人間の根幹に関わる重要な病気が数多くあります。
そうした脳の医学を追求したいという想いに加え、キャリアの選択肢が広いことにも魅力を感じ、医師という職業を選びました。大学病院で臨床や研究の最前線に立つ道もあれば、私のように開業する道、あるいは厚生労働省の医系技官として政策に関わる道、iPS細胞の研究のように基礎研究に没頭して人類の医学に貢献する道もあります。幅広いキャリアの選択肢があるからこそ選んだのかもしれませんね。
ーー大学病院での研究の道を、なぜ若くして「開業」という道を選んだのですか?
髙橋院長
大学病院に残り続けてキャリアを積むというのは、多くの場合「教授」を目指すことを意味します。もちろん、大学での研究活動自体は非常に楽しく、やりがいのあるものでした。論文を書くことも好きでしたし、最先端の知見に触れられる環境は刺激的でした。
ただ、ふと「このまま研究を続ける道」と「自分でビジネスとして医療を展開してみる道」を天秤にかけたとき、後者に強く惹かれている自分に気づいたんです。大学の勤務医では味わえない、例えばクリニックのコンセプトを考え、マーケティングを行い、PDCAサイクルを回し、資金を管理し、人を採用する…そういった「経営」という未知の領域に挑戦してみたいという気持ちが強くなりました。まだ30代前半ですが、思い切って早めに開業の道を選んだのは、そうした理由からです。
ーー開業するにあたり、なぜ「訪問診療」、しかも「脳神経内科専門」という、珍しい分野を選んだのでしょうか?
髙橋院長
これは、大学病院での臨床と並行して、週に1回ほど訪問診療の現場で働いていた経験が大きく影響しています。
まず気づいたのは、「訪問診療を必要としている患者さん=ご自身で通院できない方」というのは、その原因のほとんどが脳神経内科の病気である、という厳然たる事実です。例えば、脳梗塞や脳出血の後遺症で体が動かせない方。パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィーなどで徐々に筋力が衰え、歩けなくなった方。認知症が進行し、外出が難しくなった方。これらはすべて、脳神経内科の専門領域です。
ーーということは、まさにニーズの核心を突いていますね。しかし、実際には脳神経内科の先生が訪問診療を行うケースは少ないのでしょうか?
髙橋院長
その通りです。それが最大の問題だと感じました。訪問診療のニーズがそこにあるにもかかわらず、その現場には専門家であるはずの脳神経内科医がほとんどいませんでした。
今の日本の医療は、専門性の高い医師ほど大学病院や大きな研究センターに集まる傾向があります。一方で、開業医の先生や訪問診療を主に行う先生方は、もちろん素晴らしい医療を提供されていますが、どちらかといえば「なんでも屋」というか、広く浅く診るジェネラリストであることが多い。そんな中、私が訪問診療の外勤で目の当たりにしたのは、パーキンソン病やALSといった非常に専門性が高い病気を、残念ながら脳神経内科の十分な知識がないまま先生が診ているという現実でした。
脳神経内科医の数は、他の科と比べてもともと少ないんです。だから、知識がないまま診ざるを得ない状況が生まれ、結果として、患者さんにとって大きな不利益が生じているケースをかなりの頻度で見てきました。「この患者さん、専門医がちゃんと診れば、もっと症状が良くなるのに…」と、何度も悔しい思いをしました。
だからこそ、「これは誰かがやらなければならない」「脳神経内科医こそが訪問診療の現場に出るべきだ」と強く感じたんです。専門医である自分がやることで、救える患者さんが大勢いるはずだと確信し、このクリニックを開設しました。

ジェイ内科・脳神経内科クリニックの診療|脳神経内科専門医だからこそできる「全身を診る」こと
「脳神経内科医が診る」ことは、患者さんにとって具体的にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
髙橋院長が徹底してこだわる「専門性」と、その診療スタイルについて詳しく伺いました。
ーー脳神経内科の専門医が診ると、何が違うのでしょうか?具体的に教えてください。
髙橋院長
一言でいえば、「患者さんの満足度が圧倒的に違う」と自負しています。例えばパーキンソン病という一つの病気をとっても、私たち専門医は、圧倒的な数の患者さんを診てきた経験があります。症状の微妙な進行具合、薬の効き方、副作用の出方、リハビリの適切なタイミング…そうした無数のデータを蓄積しています。
一般の方から見れば「パーキンソン病は、どの医者が診ても同じ」と思われるかもしれませんが、実際はまったく違います。診断の精度、処方する薬のさじ加減、患者さんへの説明、そのすべてにおいて、知識と経験の差が明確に出ます。
当院には、「他のクリニックで訪問診療を受けていたけれど、パーキンソン病の症状が全然良くならない」という方が、ケアマネジャーさんからの紹介やご家族の口コミで移ってこられるケースが非常に多いです。そして、私たちが診療を引き継ぎ、薬の調整やリハビリの計画を見直すことで、症状の改善が見られることも少なくありません。開業して数年経ちますが、「やはり、やっていることは間違っていなかった」と日々実感しています。
ーー例えば「認知症」の診断では、どのような違いがありますか?
髙橋院長
認知症の診断は、私のような脳神経内科医が最も得意とする分野の一つです。まず大前提として、「加齢による生理的な物忘れ」と「認知症という病気」は全く異なります。髪が白くなるのと同じで、年齢と共に物覚えが悪くなること自体は心配ありません。しかし「認知症」は疾患であり、放置すれば進行してしまいます。
そこでまず、私たちは、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やMoCA-Jといった複数の認知機能検査を組み合わせて、「認知症の疑いがあるか」を評価します。ただ、重要なのは、その次です。「認知症であるなら、何の認知症なのか?」を厳密に追求すること。これが専門医の腕の見せ所です。
認知症と一口に言っても、アルツハイマー型、レビー小体型、前頭側頭型など、多くの種類があります。そして、種類によって治療薬や対処法が異なるのです。しかし、残念ながら専門外の先生だと、安易に「アルツハイマー型認知症でしょう」という診断、いわば“ゴミ箱診断”がなされてしまうことが少なくありません。
例えば、正常圧水頭症(脳脊髄液が過剰にたまる病気)や、ビタミン欠乏症、甲状腺機能低下症などが原因で認知症のような症状が出ている場合、これらは早期に適切な治療を行えば、回復が期待できるのです。また、パーキンソン病に関連する認知症も、専門的な診断が必要です。
私たちは、こうした「治せる認知症」や、専門的な治療が必要な認知症を見逃さないよう、MRIや脳血流シンチグラフィーといった画像検査(※連携医療機関にて実施)の結果も参考にしつつ、最終的には患者様の症状、診察所見から厳密な診断を行います。ご高齢の方だからと諦めるのではなく、治療の可能性がないかを徹底的に探る。それが私たちの役目だと考えています。
ーー先生の診療スタイルは「頭からつま先まで、全身をとことん診る」ことだそうですね。
髙橋院長
はい。それが脳神経内科医の基本です。私たちの診療は、エックス線や採血といった検査機器がなくても、極端な話「身一つ」で多くのことが分かります。
先ほどお話しした打腱器で手足の反射を見たり、目の動きを細かく観察したり、筋肉の緊張度合いを触って確かめたり…。そうした丁寧な神経診察(症候学)によって、パズルを解くように「脳や神経のどこに異常があるのか」を突き止めていきます。
例えば、原因不明の遺伝性疾患と診断されていた方でも、改めて全身をくまなく診察すると、実はまったく違う病気が隠れていた、ということもあります。だからこそ、頭の先からつま先まで、徹底的に診る。それが私の診療スタイルです。ご自宅というリラックスした環境だからこそ、患者さんの普段の様子をより深く観察できるというメリットもあります。

ーー通院が難しい患者さんにとって、訪問診療と外来の線引きはどこにあるのでしょうか?
髙橋院長
これは「ご自身で通院できるかどうか」という点で、法律(健康保険法)によって明確に決められています。クリニックに通える体力のある方は、基本的に外来診療の対象となります。
一方で、例えばパーキンソン病で体の動きが悪く、クリニックに来るまでに転んでしまう危険がある方や、ALSなどで筋力が低下し、自力での外出が困難な方。そうした「通院困難」な方が訪問診療の対象です。
脳神経内科の疾患、特にパーキンソン病やALS、進行した認知症の患者さんの多くは、残念ながら症状の進行とともに通院が難しくなるため、必然的に訪問診療を選ばざるを得ない状況になります。私たちは、そうした方々がご自宅で安心して専門的な医療を受け続けられるよう、体制を整えています。
訪問リハビリから嚥下障害まで|チームで支えるジェイ内科・脳神経内科クリニックの在宅療養
ジェイ内科・脳神経内科クリニックの強みは、医師の診察だけにとどまりません。
経験豊富な理学療法士や、志を同じくする看護師といったスタッフが一丸となり、患者の在宅療養を多角的にサポートしています。
ーー訪問診療では、具体的にどのような症状を相談できるのでしょうか?
髙橋院長
脳神経内科に関連するあらゆる症状に対応しています。
「物忘れがひどく、ご家族が対応に困っている」
「認知症で怒りっぽくなったり、暴れてしまったりする(BPSD:周辺症状)」
「パーキンソン病の手足の震えや体のこわばりが強い」
「脳梗塞の後遺症で手足が突っ張って痛い(痙縮)」
「食事がうまく飲み込めず、むせやすくなった(嚥下障害)」
「歩きづらい、転びやすくなった」
「手足に力が入らない、痺れる」
「腰が曲がってきた、首が下がってきた」
など、気になることがあれば何でもご相談ください。
特に痙縮に対しては、筋肉の緊張を和らげるボツリヌス毒素製剤の注射なども、ご自宅に伺って行うことが可能です。
ーー特に「訪問リハビリテーション」にも力を入れているそうですね。
髙橋院長
はい。当院では、必要に応じて経験豊富な理学療法士がご自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。実はここでも、脳神経内科医の視点が重要になります。
例えば「歩く」という行為は、単純な筋力だけではなく、バランス感覚、そして「足の感覚」の3つが揃って初めて可能になります。私たちは普段、土の上でも、アスファルトの上でも、いちいち地面を見なくても歩けますよね。これが「足の感覚」です。もし、この足の感覚に問題があるのに、筋力を鍛えるリハビリばかりしても、歩けるようにはなりません。
私は、患者さんが「なぜ歩けないのか」「なぜ転びやすいのか」を脳神経内科医の見地からきちんと評価し、その原因に基づいた適切なリハビリテーション計画を理学療法士と共に立てています。
ーー食事がむせやすくなる「嚥下障害」も、脳神経内科の専門分野なのですか?
髙橋院長
その通りです。嚥下障害も、脳神経内科と非常に関連が深いです。まず、「食べ物だ」と認識して口に運ぶという行為自体が、認知機能と関わっています。そして、食べ物を飲み込む際には、のどの筋力や、それに関連する神経が正常に働かなくてはなりません。
認知症の進行や、パーキンソン病、脳卒中後遺症などによって、これらの機能が低下すると、うまく飲み込めなくなり、「むせ」が起こります。患者さんの嚥下機能に合っていない食事(例えば、サラサラすぎるお茶や、硬すぎる固形物など)は、誤って気管に入り、誤嚥性肺炎という命に関わる病気の原因となります。
当院では、医師やスタッフが訪問時に嚥下機能を評価し、その方に合った食事の形態(とろみをつける、きざみ食にするなど)をご家族や介護スタッフの方へご提案しています。
ーー採用にも非常にこだわっていると伺いました。どのようなチームで患者さんを支えているのですか?
髙橋院長
スタッフの質は、医療の質に直結します。私は採用には本当にこだわっていて、面接もかなりの数を行っています。例えば、看護師を採用する際は、70人くらい面接して、たった1人しか採用しなかったこともあります。
その甲斐あって、手前味噌ですが、当院には本当に優秀で、志の高いスタッフが揃っていると自負しています。開業してから常勤で辞めたスタッフはまだ一人もいません。この「ジェイ内科・脳神経内科クリニック」の理念に共感してくれた「粒ぞろい」のチームだからこそ、患者さんに質の高い医療を届けられているのだと思っています。
ジェイ内科・脳神経内科クリニックの挑戦|医療DXと教育で、介護業界の「非効率」を打ち破る
髙橋院長は、自院の医療だけでなく、連携する介護業界全体に対しても警鐘を鳴らしています。
専門医であり、若き経営者でもある院長が指摘する「業界の課題」と、その解決策についてお聞きしました。
ーー医療だけでなく、「介護業界」にも強い課題意識をお持ちだと聞きました。
髙橋院長
非常に強い課題意識を持っています。当院はクリニックとは別に、訪問リハビリ、訪問看護、そしてケアマネジャー(居宅介護支援)といった介護保険事業も運営しているのですが、医療業界以上に、介護業界の“遅れ”を痛感しています。
それは、IT化やDX化といったテクノロジーの遅れもさることながら、働く人々の「社会的スキル」の面での課題です。
例えば、私たち医師との情報連携において、緊急性が高い情報をすぐに伝えず、逆にどうでもいい情報を電話してきてしまう。あるいは、ビジネスライクな関係性であるにもかかわらず、馴れ馴れしい言葉遣いになってしまう。もちろん全員ではありませんが、そうした「いつ、誰に、何を、どう伝えるか」という基本的なビジネスマナーや情報ハンドリングのスキルが、業界全体としてまだ成熟していないと感じる場面があります。
ーーその課題を、どのように解決しようとお考えですか?
髙橋院長
なぜそうした非効率なことが起きるのか。それは、一言でいうと「時間軸のずれ」と、それによる「生産性の低さ」だと考えています。私たち医師、特に私のような世代は、常に「どうすれば効率よく、ミスなく仕事ができるか」を考えています。
しかし、介護業界ではいまだに紙ベースでのやり取りが多く、情報の共有に膨大な時間がかかっています。「あの紙、どこにいった?」と探している間に、本来できるはずの仕事が進まない。厳しい言い方かもしれませんが、普通の人が1時間で100できる仕事が、非効率な働き方によって20しかできていない。だから、「給料が上がらない」と嘆くことになる。私は、給料が上がらないのではなく、「給料が上がるだけの仕事ができていない」状態なのだと言いたいです。
この構造的な問題を解決するために、私は今後、医療現場の効率的な仕事のノウハウを介護業界に伝える「教育事業」にも力を入れていきたいと考えています。例えば、当院が運営する訪問看護や訪問介護事業を通じて、私たちが実践しているDX化やタスク管理術をスタッフに徹底的に教え込む。そうすれば、一人の看護師や介護士が診られる患者さんの数を、5人から15人に増やすことも可能かもしれません。そうなれば、事業所としての収益が上がり、スタッフの給料も上げられる。患者さんにとっても、質の高いサービスが効率的に受けられるようになる。そんな「良い循環」を、介護業界にも作っていきたいんです。
ーー先生のような若い世代の医師が、DX化や効率化を進める意義は大きいですね。
髙橋院長
そうかもしれません。開業医の先生方の平均年齢は一般的に40代、50代の方が多いのですが、私の世代はChatGPTのようなAIツールも日常的に使いこなします。テクノロジーに対するアレルギーのようなものが無いぶん、業務のDX化は自然な流れでした。
介護業界の課題も、こうした新しいツールや考え方を取り入れることで、解決できると信じています。他のクリニックがデジタル化に踏み切れない中、私たちが先進的な取り組みを実践することで、業界全体のスタンダードを引き上げていきたいとも考えています。

脳神経内科領域における訪問診療のパイオニアとして|我孫子・柏から全国へ
介護業界への提言と並行し、髙橋院長は自らが開拓した「脳神経内科医による訪問診療」という医療モデルを、さらに発展させようとしています。
ーー開業から数年経ち、専門医による訪問診療のニーズをどう感じていますか?
髙橋院長
想像以上に強いニーズがあると、日々痛感しています。先ほどもお話ししたように、他のクリニックや病院で「良くならない」と言われていた患者さんが、当院の診療に切り替えるケースが後を絶ちません。これは、私たちが「脳神経内科専門」と標榜し、その専門性に見合った医療を提供し続けてきた成果だと感じています。「あのクリニックは、神経の病気を専門に診てくれるらしい」という認識が、地域のケアマネジャーさんや患者さんのご家族の間で広まってきている証拠であり、「やってきたことは間違っていなかった」という何よりの答え合わせになっています。
高齢化が進むにつれて、パーキンソン病や認知症といった神経疾患の患者さんの絶対数は、今後も増え続けていきます。私たちの役割は、ますます大きくなっていくでしょう。
ーー先生のようなクリニックは、今後増えていくのでしょうか?
髙橋院長
結論から言うと、難しいと考えています。確かに、「脳神経内科医がやる訪問診療はニーズがある」と気づいて参入しようとする医師はいるかもしれません。しかし、先ほども申し上げた通り、そもそも脳神経内科医の絶対数が少ない。これが非常に高い「参入障壁」になっています。同じようにやろうとしても、担い手がいなければ、爆発的に増えることはないでしょう。
ーーそれでは、先生ご自身が脳神経内科の訪問診療を広げていくのでしょうか?
髙橋院長
はい。私一人がこのクリニックで頑張っていても、診られる患者さんの数には限界があります。そこで私は、自分がパイオニアとなって、「脳神経内科医による訪問診療が、ビジネスとしてもしっかり継続できる」ことを証明したいと考えています。
その上で、私のビジョンに共感してくれる若い脳神経内科医の仲間を集めたい。そして、最終的には「神経内科専門の訪問診療グループ」として全国に展開していきたいと考えています。医師が単なる臨床家としてだけでなく、経営者としてこの医療モデルを引っ張っていく。それが私の描く未来像です。
「年だから」と諦める前に|髙橋 潤一郎院長からのメッセージ
医療の最前線から、業界全体の未来まで考えている髙橋院長の情熱は尽きることはありません。
最後に、クリニックの新たな取り組みと、読者へのメッセージをいただきました。
ーー今後、クリニックとして新たに取り組みたいことはありますか?
髙橋院長
これまでは保険診療を中心に行ってきましたが、今後は予防医療にも力を入れていこうと考えています。具体的には、「脳ドックプログラム」を検討しています。
例えば、特殊な遺伝子(アポイー遺伝子)を調べることで、将来アルツハイマー型認知症に「なりやすいかどうか」のリスクを評価する検査があります。これは現在、保険適用外です。こうした遺伝子検査や、頭部MRI検査、専門医による診察を組み合わせることで、認知症の兆候を早期に発見し、予防につなげる取り組みを始めていきたいと考えています。
ーー最後に、ご自身やご家族の症状に悩んでいる読者へメッセージをお願いします。
髙橋院長
年齢を重ねると、物覚えが悪くなったり、足腰が弱ったりと、誰もが心と体の衰えを感じます。しかし、多くの方が「もう年だから」と諦めているその症状には、脳神経内科の病気が隠れていて、治療できる可能性が残っていることが本当に多くあります。今までの訪問診療を通じて、背景にある脳神経内科の病気が見過ごされ、適切な治療やリハビリを受けられていない患者様を、私は少なからず目の当たりにしてきました。
私たちは、脳神経内科の専門家として、治療の可能性がないのかを見極めるチャンスを、ご自宅までお届けします。すべての方に「年だから」と言わせない。その気持ちで、私たちは日々診療にあたっています。どうぞ、お気軽に私たち「ジェイ内科・脳神経内科クリニック」にご相談ください。
ジェイ内科・脳神経内科クリニック
| 診療科目 | 内科、脳神経内科 |
|---|---|
| 住所 | 〒270-1151 千葉県我孫子市本町2丁目3-3 星野ビル4階 |
| 診療日 | (月・火・水・木・金) 9:00〜13:00 / 14:00〜18:00 ※臨時往診は24時間365日対応 |
| 休診日 | 土・日・祝 |
| 院長 | 髙橋 潤一郎 |
| TEL | <訪問診療・脳神経内科外来の方> 080-2619-8157 <訪問リハビリテーションの方> 070-1365-3345 |
| 最寄駅 | JR常磐線「我孫子」駅 南口ロータリー前より徒歩0分 |