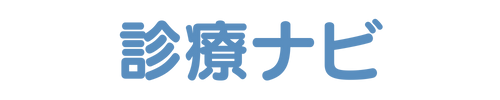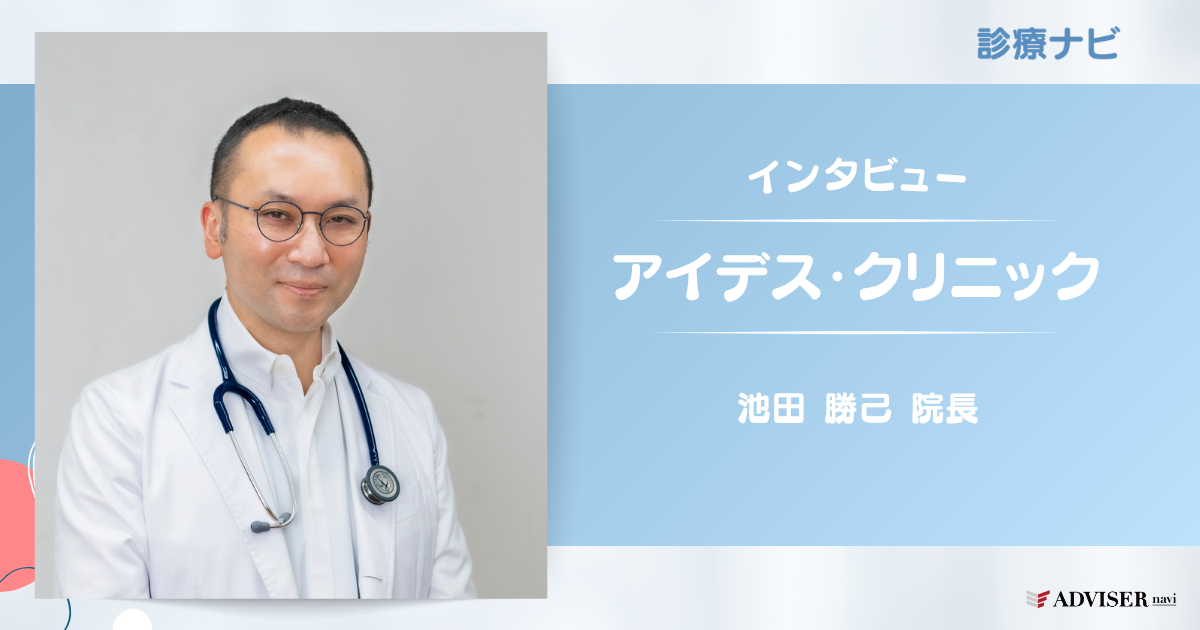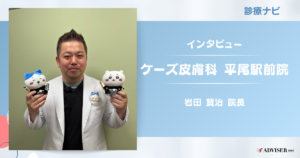2025年10月2日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「あなたのお子さんは、発達障害です」――。
ある日突然、そう告げられたときの衝撃や不安は、計り知れないものがあると思います。
「これから、この子はどうなってしまうのだろう」「親として、何をしてあげられるのだろう」と悩んでおられるのではないでしょうか。
この記事では、ご自身も発達障害を持つお子さんの父親であり、救急医から発達支援の道へと進んだ異色の経歴を持つ「アイデス・クリニック」院長、池田 勝己(いけだ かつき)先生にお話を伺いました。
医師として、そして父として。池田院長と「栄養療法」との出会い
救命救急の最前線でキャリアを積んでこられた池田院長。
しかし、ご自身のお子様との出会いを機に、大きな転換点を迎えたそうです。
医師として、そして一人の父親として、どのように発達障害と向き合い、現在の「アイデス・クリニック」の基礎となる治療法にたどり着いたのでしょうか。
ーー先生はもともと、救急医としてご活躍されていたのですね。
池田院長
はい。1999年に聖マリアンナ医科大学を卒業後、救命救急センターなどで働かせていただきました。救急医として重症患者さんの集中治療などを行う傍ら、学生時代から興味のあった予防医学や抗加齢医学などの研鑽も個人的に進めていました。医師を志したのも、祖父の代から続く医師の家系で、祖父や父の働く姿を見て育ったのが自然なきっかけでしたね。
ーーそこから、なぜ発達障害のお子さんを支援する道へ進まれたのでしょうか。
池田院長
一番のきっかけは、私の長男が発達障害(知的障害を伴う自閉スペクトラム症)だと診断されたことです。2010年に生まれた長男が、2歳の時にそう診断され、そこから私たちの歩みが始まりました。当時は今ほど情報もなく、「治療法は特になく、療育がメインです」と言われるがまま、地域の療育施設に通う日々が始まりました。
しかし、「本当にこれしかないのだろうか?」という思いが常にありました。何か他の治療法はないかと模索する中で、ヒントを求めてアメリカの米国先端医療学会に参加したんです。そこで、「栄養療法」という発達障害へのアプローチ法に出会いました。
ーー海外で最先端の治療法に出会われたのですね。
池田院長
はい。その学会で「日本から来たので、この治療法を日本でやりたい。やり方を教えてほしい」と伝えたところ、「日本にもうやっている医者がいるから紹介するよ」と、本当に軽い感じで言われまして(笑)。
その先生というのが、当時私が勤務していた病院から電車で15分ほどの場所で開業されており、さらに驚いたことに、その先生のお嬢さんは、私が研修医時代に指導した後輩だったんです。すごいご縁ですよね。その先生に長男を診ていただき、栄養療法を実践したところ、目に見えて症状が良くなっていきました※1。この経験から、「同じように悩んでいる他のご家族の力にもなりたい」と強く思うようになり、この道を本格的に歩むことを決意しました。
※1)個人の感想であり、効果を保証するものではありません。
医療だけでは足りない?アイデス・クリニックとキッズプレイスたかなわだいを同時に立ち上げた理由
ご自身の経験から、発達障害のお子さんとご家族が本当に必要としている支援の形を見出した池田院長。
クリニックの設立だけでなく、療育施設を併設するという独自のスタイルに辿り着きます。
なぜ医療と療育、両輪でのサポートが必要だったのでしょうか。
ーーアイデス・クリニックの開業に至る経緯を教えてください。
池田院長
長男の治療でお世話になった先生のご厚意で、2015年頃から、恵比寿にある「満尾クリニック」さんの一角をお借りして、「発達支援外来」という形で診療を始めました。そこで多くのお子さんやご家族と接するうちに、二つの大きな課題が見えてきました。一つは、悩んでいるご家族が非常に多いこと。そしてもう一つは、支援の受け皿となる療育施設が圧倒的に足りていないことでした。
特に、私たちが実践する栄養療法や食事指導に特化した療育施設は、当時は皆無でした。他の施設にお願いしても、「うちではそこまで対応できない」と言われてしまうことが多くて。幸い、うちの長男が通っていた施設は理解があり協力的でしたが、誰もが同じ環境に恵まれるわけではありません。「それなら、無いのなら自分たちで作ろう」と。そう決意し、2018年に児童発達支援・放課後等デイサービス「キッズプレイスたかなわだい」と、この「アイデス・クリニック」を同時にスタートさせました。
ーーまさに、必要とされている場所を一から作られたのですね。
池田院長
はい、もともとクリニックとデイサービスはセットでやるつもりで始めました。実際に施設を立ち上げると、すぐにお子さんで定員が埋まってしまい、待機リストがどんどん長くなっていきました。それだけ、皆さんがこういう場所を望んでいたのだと実感しましたね。そのニーズに応えるため、すぐに2つ目の施設「キッズプレイスたかなわだいⅡ」も開設しました。今でも関係各位から「3つ目はどう?」と聞かれるくらい、この地域のニーズは大きいんです。
ーー高輪台という場所を選ばれたのには、何かこだわりがあったのでしょうか。
池田院長
私たちが実践しているような専門的な治療には、近隣の方だけでなく、遠方からも患者さんがいらっしゃいます。そのため、アクセスの良さは非常に重要でした。ここは品川駅に近く、新幹線や飛行機を使われる方も来やすいですし、都内・都外どちらからも通いやすいだろうと考えました。北海道や九州、沖縄から、コロナ禍以前は海外から来られる方もいました。
もう一つの理由は、とてもシンプルですが、私の自宅が近所だったからです(笑)。これなら仕事が終わって、学童に通う自分の子どもたちを迎えに行くのもスムーズにできるだろうと。仕事と子育てを両立するための、現実的な選択でもありました。
「使えるものは何でも使う」|アイデス・クリニックが実践する統合的発達サポートとは
「希望がない、やりようがない、と考えているご家族に、『そんなことはない』と伝えたい」と語る池田院長。
その言葉を支えるのが、救急医時代の経験から生まれた「バンドル」という考え方。
医療、栄養、教育、テクノロジーなど、有効な手段を束ねて多角的にアプローチする、アイデス・クリニック独自の支援の全貌に迫ります。
ーー診療において、先生が大切にされていることは何ですか?
池田院長
基本的な方針は「使えるものは何でも使う」ということです。これは、救急医時代に培われた「バンドル」という考え方が基になっています。バンドルとは「束」のことで、科学的根拠のある対策を一つひとつ単独で行うのではなく、複数まとめて実践することで改善する確率を高めていくアプローチです。
ですから、当院では医療の力はもちろん、教育の力、相談支援のような社会的な支援、そして将来的にはテクノロジーの力も活用し、お子さんとご家族を総合的にサポートすることを目指しています。この構想を、「アイデス(IDSS)」と名付けています。IDSSとは「Integrative Developmental Support System(統合的発達サポートシステム)」の略称で、その名の通り、あらゆる角度からお子さんとご家族を支えることを目的としています。
ーーその中でも中核となる「栄養療法」について、具体的に教えていただけますか?
池田院長
栄養療法は、脳の正常な発達と機能に不可欠な栄養素を補い、同時に発達を阻害する可能性のある物質を避けることを基本とします。具体的には、タンパク質を中心とした食事を心がけていただいたり、添加物の少ない食品を選んでいただいたりします。
また、「水」も非常に重要です。脳の発達に悪影響を与える可能性のある有害重金属や農薬などを避けるため、ご家庭で使うお水、特に飲み水や炊事に使う水は、逆浸透膜(RO)で浄水した水か蒸留水をおすすめしています。さらに、水銀が多く含まれることがあるマグロやカツオといった大型回遊魚は、なるべく控えるようにお願いしています※2。これらに加え、体内に溜まってしまった有害重金属を排出する「キレーション療法」を組み合わせることもあります。
※2)一部の食材には注意が必要とされる場合がありますが、最終的な食事内容は医師の診断や指導に基づきます。具体的な自由診療の内容については、リスク・副作用等も含め医療機関までお問い合わせください。
ーー食事の管理はご家族にとって大変な面もあるかと思いますが、すべてを完璧にこなす必要があるのでしょうか?
池田院長
もちろん、ご家庭でできる範囲で、というのが大前提です。最初からすべてを完璧にやろうとすると、かえってご家族のストレスになってしまいますからね。何から始めるべきか、何がそのご家庭にとって優先度が高いのかを一緒に考え、できることから一歩ずつ進めていくことが大切です。当院が運営している「こども食堂」では、栄養バランスを考えた食事のモデルを提示するような活動も行っています。レシピをYouTubeで公開したりもしているので、参考にしていただければ嬉しいです。
ーー薬を使った治療については、どのようにお考えですか?
池田院長
私は、薬を全く使わないというのはナンセンスだと考えています。もちろん栄養療法は基本ですが、衝動性が非常に強くて集団生活が困難な場合など、使うべき時には薬を適切に使うべきです。最近は良い薬もたくさん出てきていますから、それらを上手く活用することも、お子さんの生活の質を上げるための重要な選択肢の一つです。
「うちの子、もしかして…」と感じたら?保護者が知っておくべきこと
わが子の発達について、漠然とした不安や違和感を抱えながらも、「どこに相談すればいいのか分からない」「こんなことで相談していいのだろうか」と、一人で悩みを抱え込んでしまう保護者の方は少なくないと思います。
専門家として、そして同じ子どもを持つ親の立場として、池田院長からアドバイスをいただきました。
ーーどのような症状や悩みがあったら、クリニックに相談するのが良いでしょうか?
池田院長
大前提として「気になったらいつでも来てください」とお伝えしたいです。具体的には、夜眠れない・朝起きられないといった生活リズムの乱れ、極端な偏食、友達とすぐに喧嘩してしまう、かんしゃくがひどい、学校に行きしぶる、といったお子さんの困りごと。そして何より、お父さんやお母さんが「子育てしづらいな」と感じること。それらがすべて、相談に来ていただく立派な理由になります。
一人で悶々と悩んでいる時間は、もし治療や介入が必要な場合、その貴重な時間を失うことになります。逆に、何も問題がなければ「大丈夫ですよ」という言葉があるだけで、心の負担が軽くなることもあります。ですから、どうかためらわずに、まずは相談してほしいと思います。
ーー実際に、どのようなお悩みで来院される方が多いですか?
池田院長
本当に様々です。コミュニケーションが苦手なお子さん、衝動性が強くて授業中に座っていられないお子さん、特定の学習分野(読み・書き・計算など)に困難を抱えるお子さん、そして知的な遅れがあるお子さんなど、多岐にわたります。
最近増えているのは、受験をきっかけとした学習に関するご相談ですね。また、他院で一度診断を受け、「これ以上はやりようがない」と言われて、インターネットなどで調べて当院にたどり着く、というケースも非常に多いです。
ーー発達障害と診断され、将来を悲観してしまうご家族も多いと聞きます。
池田院長
多くの方が「発達障害=治らない、将来は終わりだ」という絶望を感じられることが多いと思います。私自身も、自分の子どもが診断された時、そう思ってしまったこともありました。ただ、私が一番伝えたいのは、「やりようは、ある」ということです。完璧な方法ではないかもしれない。でも、決して打つ手がないわけではないんです。その可能性を、諦めないでほしいと思います。
子どものため」が「家族のため」に|アイデス・クリニックが見つめる家族全体の幸せ
お子さんの発達に向き合う日々は、時に保護者自身の心と体をすり減らしてしまうこともあります。
アイデス・クリニックでは、お子さんだけでなく、支えるご家族全体が健やかであることを目指しています。
ここでは、池田院長が考える「家族のサポート」について伺いました。
ーー子どもの治療を進める上で、親自身のケアも重要になってくるのでしょうか?
池田院長
もちろんです。私たちは、お子さんだけでなく、ご家族全員が心身ともに健康になることを目指しています。お子さんのことで悩むあまり、お母さんやお父さんご自身のメンタルや体調が不安定になってしまうケースは少なくありません。当院では、栄養療法や心療内科的なアプローチを用いて、保護者の方の健康相談にも応じています。ご家族が笑顔でいることが、お子さんにとって何よりの安心材料になりますから。
ーー先生は、どのように親御さんと向き合っているのでしょうか?
池田院長
まず、頭ごなしに何かを言うことは絶対にしません。多くの方が、悩みに悩んで、不安を抱えてここに来られます。その気持ちに寄り添い、一方的に治療方針を押し付けるのではなく、「一緒に考えていきましょう」というスタンスを大切にしています。発達障害と診断され、絶望的な気持ちでいらっしゃるご家族に、「でも、やりようはありますよ」と、具体的な選択肢を示しながら希望を持ってもらう。それが私の役割だと考えています。
ーー親子関係だけでなく、夫婦関係も子どもの状態に影響するものなのでしょうか?
池田院長
それは、大いにあると考えています。お子さんの問題だと思っていたことが、実はご夫婦の関係性に起因するストレスから来ている、というケースもあります。もちろん、すべてのケースがそうだというわけではありませんが、ご家庭がお子さんにとって安心できる場所であるためには、まず保護者の方々、特にご夫婦の関係が安定していることが望ましいのは事実です。お子さんのためにも、時にはご夫婦で対話の時間を見つめ直すことが、時には状況を改善する糸口になることもある、とお伝えしています。
「学校に行けない」が「御三家合格」へ?アイデス・クリニックに通う子どもたちの成長事例
池田院長から「やりようはある」という力強いメッセージを繰り返しいただきました。
ただ、それは決して絵空事ではなく、実際にクリニックを訪れた多くの子どもたちが、自分らしい成長をしているそうです。
ーーこれまでの診療で、特に印象に残っている患者さんのエピソードがあれば教えてください。
池田院長
本当にたくさんの出会いがありましたが、どのお子さんも印象深いです。例えば、学校に行くのも辛い状況だったお子さんが、治療を通じて少しずつ元気を取り戻し、中学受験にチャレンジして、いわゆる「御三家」と呼ばれる難関校に合格したケースがあります。また、不安が強くて集団生活が苦手だったお子さんが、無事に高校を卒業し、自分の行きたい大学に進学していったという報告を聞くと、自分のことのように嬉しくなりますね。
ーー先生ご自身の長男さんも、診断された当時からは大きく変化されたそうですね。
池田院長
はい、これはレアケースなのかもしれませんが、知的障害を伴うASDと診断された長男も、今では中学3年生の生活を自分なりに楽しんでいます。特に数学が好きで、「コラッツ予想」を証明したいと言って、一人で黙々と勉強したり数学オリンピックへ挑戦しています。ピアノも好きで、学校の合唱コンクールで伴奏ができるくらいには上達しました。診断された当時は想像もできなかった姿です。
ーー素晴らしいですね。ただ、すべてのお子さんが、同じように劇的な改善を見せるわけではない、という不安を持つ親御さんもいらっしゃると思います。
池田院長
おっしゃる通りです。すべてのお子さんが同じような結果になるわけではありません。しかし、たとえ劇的な変化ではなかったとしても、その子なりに人生を楽しめる方法、社会と折り合いをつけて生きていく術を身につけているお子さんは本当にたくさんいます。大切なのは、他の誰かと比べるのではなく、その子自身のペースで、昨日より今日、今日より明日、少しでも生きやすくなるためのお手伝いをすることだと考えています。だからこそ、「やりようがない」と諦めてほしくないのです。
子どもたちの才能が花開く社会へ|アイデス・クリニック 池田院長が描くこれから
「すべての子どもたちが、それぞれの才能を発揮し、自立して生きていける社会を作りたい」。
池田院長に、発達障害の支援とテクノロジーの融合、そして社会全体への願いについて伺いました。
ーー先生が今後、特に力を入れていきたいと考えていることはありますか?
池田院長
もちろん、栄養療法を主軸とした日々の診療や療育施設の運営を地道に続けていくことが基本です。その上で、もう一つ挑戦したいのが、テクノロジーの活用です。実は10年以上前から構想しているのですが、発達障害のお子さんを支援するための「対話型AIアプリ」を開発したいと考えています。
特性のあるお子さんは、スマートフォンやアプリといったデジタルなものに強く惹かれる傾向があります。この特性を活かし、例えば騙されやすいお子さんの防犯や非行防止に役立てたり、コミュニケーションの練習相手になったりするようなアプリが作れないかと。ようやく時代と技術が追いついてきたので、今、様々な専門家の方に相談しながら、実現に向けて動いているところです。
ーー先生が思い描く、理想の社会とはどのようなものでしょうか。
池田院長
発達障害のお子さんの中には、いわゆる「ギフテッド」と呼ばれるような、突出した才能を持つ子もいます。しかし、今の日本の社会では、その才能が理解されずに潰されてしまうことが少なくありません。そうした特異な才能をしっかりと伸ばし、発揮できる社会を作りたい。それが私の大きな夢です。
もちろん、それはギフテッドの子に限った話ではありません。すべての子どもたちが、それぞれに合った形で自分の力を発揮し、誰かの助けを借りながらでも、自立して楽しく生きていける。そんな社会を目指して、これからもお子さんとご家族に寄り添い続けていきたいと思っています。やりようがないわけじゃない。そのことを、これからも伝え続けていきます。
アイデス・クリニック
| 診療科目 | 発達支援外来、受験栄養外来、不登校相談外来 |
|---|---|
| 住所 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-6-23 エステート高輪102B |
| 診療日 | (木・土) 9:00〜12:00 13:00〜18:00 ※その他の平日は、電話やメールでのお問い合わせに対応しております。 ※電話受付時間:月曜日から土曜日まで(10:00〜18:00) |
| 休診日 | 月・火・水・金・日 |
| 院長 | 池田 勝己 |
| TEL | 03-5860-2290 |
| 最寄駅 | 都営浅草線「高輪台駅」A1出口より徒歩4分 JR山手線「五反田駅」東口より徒歩15分 JR線・京急線「品川駅」高輪口より徒歩13分 |