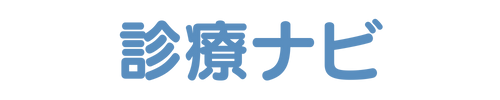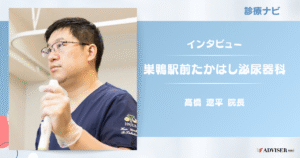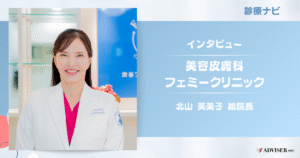2025年9月3日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「忙しくて、自分の体はつい後回しにしてしまう」
「デリケートな症状の相談先がわからない」
ビジネス街・八丁堀では、こうした声が珍しくありません。
今回紹介するのは、朝8時から診療、土曜も対応の「イサナクリニック」。
泌尿器科・消化器内科・一般内科・健康診断を担い、キャッシュレス決済やAIを用いたカルテ自動作成支援などを導入。限られた時間でも医療の質を下げない受診体験を追求しています。
今回は、理事長兼総院長の杉野 智啓(すぎの ともひろ)医師に、開院の思い、診療のこだわり、働く世代への伴走についてじっくりと伺いました。
ユニークな経歴を持つドクター|杉野 智啓 医師
杉野理事長のことを調べると、非常に珍しい経歴が多く出てきました。
医師でありながら技術経営学(MOT:Management of Technology)を修め、自衛隊から米国海兵隊への留学も経験。異色のキャリアは、どのように形作られていったのでしょうか。
その原点には、文学への造詣と、新しい世界への探究心がありました。
ーー医師を志す原点に、手塚治虫の『ブラック・ジャック』があったそうですね。
杉野理事長
私は地方の公務員家庭に生まれたマンガ好きの文学少年でした。ご本人も医師であった手塚治虫の作品、とりわけ『ブラック・ジャック』が影響を与えています。『火の鳥』もそうですが、作品を通じた生命倫理をめぐる問いは、私の原動力になっています。また、防衛医科大への進学を決めた際には、陸軍軍医トップの軍医総監まで務めた文豪・森鴎外への憧れもありました。『高瀬舟』で描かれる普遍的な医療倫理のテーマは、心の奥に残り続けています。同級生との思い出話では、数学の授業中にトールキンの『指輪物語』を机の下でずっと読んでいた、と語られました。そういえばトールキンも英国の陸軍軍人でしたね。精神科医である帚木蓬生の『閉鎖病棟』も医療倫理に訴えかける作品です。吉村昭の医学系の歴史小説も好きでしたが、憧れの森鴎外の描かれ方は衝撃でした。
崇高な思いや医師家庭の原体験のある諸先輩方と比べると小さな出発点ですが、文学的な原体験は、病気やデータだけを見るのではなく、患者さん一人ひとりの物語に耳を傾けたい、という診療姿勢に直結しています。ブラック・ジャック先生のようなすご腕外科医になる夢はまだかなっていませんが。
ーー防衛医大を卒業後、自衛隊医官としてキャリアをスタートされていますが、アメリカ海兵隊へ留学されたご経験もあるとか。どのような経緯だったのでしょうか?
杉野理事長
学生時代、あまり優等生ではなく、卒業間近までバレーボール部と趣味のフルマラソンに明け暮れ、試験はいつもギリギリの体育会系と化し、文学少年の面影はどこかへいってしまいました。自衛隊時代に海外留学のチャンスをいただいたのですが、ドクターとしての派遣ではなく「元気な医官をアメリカ海兵隊に行かせてみる」抜擢でした。
当時所属していた感染症対策を専門とする医療部隊で、対テロというテーマが重視されていた時期です。コロナ禍ではダイヤモンド・プリンセス号の対応にあたった部隊です。そこで、有り余る体力と、最低限の英語力の私に声がかかり、アメリカ海兵隊の対テロ部隊に日本人第一期生として送られました。特に医官の医療行為はせず、みんなで丸太担ぎ、がれきの下に酸素ボンベを背負って潜入、ロープで降下、射撃訓練など、異色の経験をしました。優等生ではない私でも、元気に挑戦していれば面白い道が開けると実感しました。
ーー医療の現場から一転、ビジネスやテクノロジーの世界である東京工業大学の大学院で「技術経営学」を学ばれたのはなぜですか?
杉野理事長
自衛隊で総合臨床医、退官後は泌尿器科専門医、内科や在宅医療を経て、「地域に根差した総合診療を、自分の手で形にしたい」想いが強くなりました。経営のことなど医学の外側の実力不足も感じるなか、普通のクリニック開業が自分のやり方と思っていませんでした。自分の興味を深掘りした結果、「新しい医療技術や経営手法が、どのように患者さんと地域社会の幸せに結びつくか」、その答えを実地で示したいと考えるようになったのです。
そこで、東京工業大学(現・東京科学大学)の大学院、仙石教授の研究室の門をたたき、技術経営、MOT(Management of Technology)修士をおさめ、現在は博士課程に在籍中です。MOTはよく理系のMBAと言われ、技術立国の日本を題材にした興味深い研究も多い奥の深い経営学です。東工大のビジネススクールにおいて医師出身は異質で、社会常識を周りのビジネスパーソンから教えていただいてばかりの刺激的な環境でしたね。他者と違う強みの掛け合わせが欲しいと奔走した経歴です。この経験で、テクノロジーと経営、そして医療を融合させる視点を得たのが、イサナクリニックの運営の礎になっています。

八丁堀に誕生した「イサナクリニック」|その根底にある想いとは
異色の経歴を持つ杉野理事長が、運営するイサナクリニック。
その背景には、最先端の知見と、地域医療への熱い情熱があります。
なぜ八丁堀という場所を選んだのか、そしてクリニックの成長を支える独自の哲学に迫りました。
ーー数ある場所の中から、この八丁堀の地で開業された理由を教えてください。
杉野理事長
八丁堀は伝統あるビジネス街であり、近隣にはファミリー層やご高齢の方も多い。多様な背景が交錯する場所で「地域に根差した総合診療」を実現したいと考えました。このエリアには、新しいものへの感度が高いビジネスパーソン、アーリーアダプターが多くいらっしゃいます。そうした方々に、テクノロジーを活用した医療を提供し、価値を実感していただく。そんな挑戦の場として、八丁堀は魅力的です。出社前や退社後、昼休憩、外回りの最中に立ち寄れるよう、朝8時から診療、ランチタイムも可能な日は通し営業、平日は仕事や学校という方に土曜日も開院する受診機会の最大化で、地域の「健康のパートナー」を目指しています。
ーー「イサナ」というクリニック名には、どのような願いが込められていますか?
杉野理事長
「イサナ」とは、万葉集にも登場するクジラの古い呼び名「勇魚(いさな)」に由来します。クジラのような大型哺乳類は体サイズに比し発がん率が低いという説があり、健康長寿の象徴とされています。この「病気を予防する」クジラのイメージがクリニック名に込められています。がんの早期発見や生活習慣病対策を大切にして、地域の皆さんがクジラのようにいつまでも大海を泳ぎ回り、健やかに歳を重ねてほしい。そんな願いが込められています。クリニックのロゴマークにもクジラをあしらっています。
ーー先生が経営者として本格的にクリニックの舵を取るようになってから、半年で患者さんの数が2倍に増えたと伺いました。何が変わったのでしょうか?
杉野理事長
私が診療と経営を統合する人材としてイサナクリニックを陣頭指揮し始めたのは2025年2月です。もともと当院は、「早期発見・予防の力で世界から大腸がん死を根絶する」ビジョンで医療AIの開発を手掛けるスタートアップ「Boston Medical Sciences株式会社(以下BMS社)」と強い協力関係で、同社と協調して新しい技術を社会実装する使命がありました。同社CEOの岡本氏と私杉野は、かつて同じ病院で研修を積んだ10年来の友人で、その後のビジネスシーンでも協力してきた間柄です。BMS社と協調する将来像を目指す一方で、地域医療に新技術をどう活かし、どのような患者さんに来ていただき、成長していくか、というクリニック独自の経営の足元が定まる途上でした。
私がプレイングマネージャーとして入ったあとは、「イサナクリニックの強み」「患者層とアプローチ方法」を分析するPDCAサイクルを高速で回しました。周辺の泌尿器科不足に着目し、専門医としての私の背景を、地域の皆さんに最大限提供する方向に舵を切ったのが転機と考えています。医師の土台から現場を支え、経営の視点からクリニックを俯瞰し、改革を進めたことが、多くの患者さんにご支持いただき急成長できた理由の一つかもしれません。
ビジネスパーソンが信頼を寄せる「対話」と「透明性」
イサナクリニックが多くの患者さん、特に情報感度の高いビジネスパーソンから支持される最大の理由は、その徹底した「対話」重視の姿勢と、医療の「透明性」にあります。
杉野理事長が考える、「患者満足度」とは一体何なのでしょうか。
ーー診療において最も大切にされていることは何ですか?
杉野理事長
第一に「わかりやすい説明」と「徹底した対話」です。患者さんはご自身の時間もお金も大切にされています。限られた時間で、自分が受ける検査や治療の意味、費用、期待効用、それらを納得して診察を受けたい切実な要望をお持ちです。医療者が一方的に医学的な正しさを押し付けないよう、「症状や心配事に、このような予算感で、検査と治療はいかがでしょう?」というリスクコミュニケーションを行います。クラウド型の電子カルテは、検査費用がリアルタイムで表示できるので、そうした対話が行えます。「透明な医療」を目指し、患者さんが納得感を持って治療に臨む。それが満足度に繋がると信じています。
ーー患者さんの満足度を測るために、先生独自の指標があると伺いました。
杉野理事長
はい、満足度という主観を、客観的な経営データから代替指標として見いだすため、私の中にいくつか指標があり、重視するひとつが「同一医師継続(再診)率」です。これは、一度来てくださった患者さんが、引き続き同じ医師を受診してくださる割合です。予約導線やワークフローを整備することで、この内部指標を95%以上の水準に引き上げました。その患者さんを理解した医師が均一な医療を提供し、同じ医療体験を続けることで、また同じ医師にかかる満足度につながると考えます。
もう一つは、「納得して検査と治療を受けているか」という各種の検査稼働率のデータから導く、国際的に実績ある経営学指標を分析し続けています。特にイサナクリニックでは、超音波(エコー)検査や上部内視鏡検査(胃カメラ)の院内稼働率が、満足度と連動していると感じています。
ーー超音波検査は対面診療ならではの強みですね。
杉野理事長
はい。オンライン診療も導入していますが、現状は対面での診療を希望される患者さんにお応えするので手一杯です。理由の一つに、超音波検査のような対面でしか提供できない価値があるからです。泌尿器科や消化器内科では、超音波検査との相性がとても良いのです。痛みもなく、腎臓や膀胱、前立腺などを観察でき、その場で結果を伝えられます。健康診断でも同じように検査は行われていますが、あとから結果が送られてくると、その後の医療体験に谷間が生じがちです。私は検査をしながら、画像を患者さんと一緒のモニターで見ながら説明します。「あなたの体の中は今、こういう状況です」とリアルタイムにお話しすると、患者さんの理解は深まります。
この「対話が生まれる検査」には満足いただいていると感じています。私にとっても、画像検査の豊富な情報を得ながら患者さんの不安をすぐに相談できる、Win-Winな時間と考えています。オンライン診療で得られない対面ならではの価値を大切にしていきたいですね。
最先端テクノロジーが支える、これからのイサナクリニック
杉野理事長が目指すのは、人の温かみある対話「情理」と、最先端のテクノロジー「論理」が融合した新しいクリニックの形です。
その象徴が、AI(人工知能)の活用。
未来の医療を現実のものとする、イサナクリニックの先進的な取り組みに迫ります。
ーー診察にAIが導入されているというのは本当ですか?
杉野理事長
はい。私の診察室では、生成AIが私と患者さんとの会話をテキスト化し、カルテ作成を支援してくれています。これは私が2018年頃から運営と編集に携わった「医療×AI」のメディアで続けてきたテーマを、自身で実践している形です。音声認識も、文脈を理解するAIの補正で精度が高まる。もちろんAIを利用する上で、個人情報とプライバシーの取り扱いには最大限配慮し、医師が最終責任で内容を監督しますが、カルテ作成の手間をAIが担ってくれます。
ーーAIを活用することで、診療はどのように変わるのでしょうか?
杉野理事長
最大のメリットは、私が患者さんとの対話に集中できることです。通常、医師は診察しながら電子カルテに視線を落とし、タイピングしなければなりません。しかしAIがその作業を肩代わりしてくれるおかげで、私はできる限り患者さんの顔を見て、お話を聞くことができる。これが、先ほどお話しした「対話」の質を向上させ、満足度に繋がると考えています。
よく「AIは人間の仕事を奪う」と言われますが、私の考えとは違います。AIはあくまでパートナーです。AIの仕事のループ中に人間が介在し、協働する「ヒューマン・イン・ザ・ループ」という考え方があり、予測していた未来像を診療で実践しています。ヒトは良くも悪くもモノの見方のバイアス(偏り)が避けられない生き物で、できるだけフェアで倫理的にふるまうAIらしい客観的な視点と組み合わせることで、医師の経験や直感を活かした質の高い医療が提供できるはずです。
ーーお話にありましたが、医療機器開発スタートアップや大学研究室とも連携されているそうですね。
杉野理事長
イサナクリニックは、新しい技術や機器の導入を進める「実証の場」の役割も担っています。医療業界は良くも悪くも保守的で、新しいものを導入する抵抗感が強い傾向にあります。しかし、本当に良い技術ならば、積極導入し、患者さんに還元すべきです。そのためには、新技術や変化を取り入れる経営トップの意思が必要と技術経営学でも示されています。技術経営学の知見を活かし、院内のスタッフと対話を重ね、新技術を受け入れられる環境を整える。それも私の重要な役割だと考えています。理論の正しさだけを押し付けるのではなく、人の心に寄り添いながら変化を促していく。それは患者さんとの関係づくりと共通ですね。
これらの考えは、私が現在博士課程で所属する東京科学大学(旧・東工大)の仙石研究室で研究を続けている「ELSI(エルシー):新しい科学技術を社会に導入するときに、倫理・法律・社会への影響をあらかじめ考える視点」や、「RRI:研究やイノベーションを社会と対話しながら進め、望ましい未来に結びつけるための枠組み」と呼ばれる専門分野で磨き続けています。
泌尿器科から消化器内科まで|悩める現代人のための幅広い診療
イサナクリニックは、泌尿器科、消化器内科、一般内科という3つの柱で、現代人が抱える様々な健康問題に対応しています。
特に、悩みを抱えながらも相談できずにいる多くのビジネスパーソンにとって、頼れる駆け込み寺のような存在となっています。
ーーイサナクリニックの主な診療内容について教えてください。
杉野理事長
当院では、泌尿器科、消化器内科、一般内科の3つの領域で幅広い診療を提供しています。
泌尿器科では、泌尿器科専門医として、尿路感染症や性感染症、夜間頻尿といった排尿障害など、デリケートな症状に専門的な診療を行います。前立腺がんや腎臓がんの精密検査・フォローアップも可能です。
消化器内科では、ストレスが原因となりやすい逆流性食道炎や過敏性腸症候群、ピロリ菌感染などの治療にあたります。内視鏡専門医による、負担の少ない鼻からの胃カメラ検査も実施しています。
一般内科では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病から、花粉症などのアレルギーまで幅広く対応します。また、各種健康診断も充実しており、健診で異常が見つかった場合の精密検査やフォローアップも当院で一貫して行えるのが強みです。
ーー特に泌尿器科の患者さんが増えているそうですが、どのような悩みが多いですか?
杉野理事長
当院に来られる患者さんは、年齢層の中央値が40代前半と比較的若い特徴があります。私が患者さんの代表的なペルソナ(属性)として想定しているのが、「悩める現役世代のビジネスパーソン」、この年代は、下半身とおなかに関する悩みが少なくありません。ちょっとした違和感や心配事が、気になりだすと仕事に集中できないほど大きくなり、パフォーマンスを落とす。出張や単身赴任も多く、なかなか落ち着いて医療を受けられない。そうした悩みに、ビジネスへの共感意識も持ちながら、プライベートとのバランスを追求する丁寧な説明を心がけています。
その他に意識する層として、「八丁堀に馴染みのあるシニア層」、かつて現役、まだ現役として頑張っている、このエリアに長く関わってこられた方々が、歳を重ねて基礎疾患が増え、トイレのトラブルも増えた。しかし、ビジネス街にかかりつけ医を持っていない、探している。そんな人生の先輩方の末長い活躍を支えるのもイサナクリニックの大事な役割です。
また、「湾岸エリアのファミリー層」、便利な生活拠点で職住近接していますが、受けたい医療、泌尿器科や消化器内科のかかりつけが見つけられない。特に泌尿器科過疎地の存在を私たちは意識しています。そんな患者層が近隣の橋を渡って来ていただくケースも増えています。
最後に「インバウンド・国際色豊かな患者層」、特に東京駅近くの立地から、出張・テーマパーク・観光地帰りに、言葉の壁を越えていらっしゃっています。海兵隊仕込みの英会話は錆びついて申し訳ないですが、幸い生成AIの技術進化が良質な翻訳と安心の説明を可能にしています。
ーー保険診療と自由診療の線引きについては、どのようにお考えですか?
杉野理事長
まずは、保険診療の価値と密度を最大化することに挑戦しています。新技術の採用には積極的な姿勢ですが、当院の自由診療はこれからの課題として慎重に捉えています。自身のライフワークで、研究テーマの「医療倫理」が不可欠です。行動経済学の研究でも指摘されるように、医療が安易に数字を追い求めると、モラルが崩壊しやすくなります。
そして、私たち医療機関や医療従事者は、社会の皆さんと持続可能性を共に考える公共財を意識したいです。例えば、自由診療で体重管理目的のGLP-1受容体作動薬のような薬は、社会的関心の先行から市場へ浸透したケースです。
泌尿器科では体重管理が排尿症状の改善に寄与する可能性があり、保険診療でカバーできない側面への期待もあります。しかし、診療が不十分で不適切な処方や、利益を追い求め過ぎたマーケティングは、モラルハザードと紙一重です。もし自由診療を積極的に行うならば、患者さんと社会のためになるか倫理面の検討や、取り扱いに十分な組織内のガバナンスを整備するのが私の役割です。患者さんにわかりやすい情報提供で誤解を避け、透明性を担保して提供すべきでしょう。そのようなリスクコミュニケーションこそ、技術経営での学びの実践です。
【医師 × 経営者】医療業界の新たなロールモデルを目指して
医師として臨床の前線に立ちながら、経営者としてクリニックを成長させ、さらに研究者として医療の未来を見据える杉野理事長。
その視線の先には、どのような景色が広がっているのでしょうか。
日本の医療が抱える課題と、自らが目指す「メディカル・アントレプレナー」像について伺いました。
ーー先生のように、臨床と経営の両方に深く関わる医師はまだ少ないのでしょうか?
杉野理事長
もちろん、多くのドクターはご自身の専門分野を深く追求し、医療の本分に集中されています。それは非常に尊いことです。ただ、私はどうやらそちらのタイプではなかったかもしれません。「組織を良くするにはどうすればいいか」「新しい技術をどう社会に活かせるか」を想像してきました。実は、私が大学院で修士を修了した時のテーマは「メディカル・アントレプレナー」、つまり新しい事業を興す医療者の研究でした。今の経営人材としての活動は、その頃から研究し続けてきたことの実践です。
ーーなぜ、医療業界では新しいことに挑戦する「メディカル・アントレプレナー」が増えにくいのでしょうか?
杉野理事長
根深い課題ですが、単純にプレイヤー、挑戦者が少ないのも事実です。また、医学部の教育カリキュラムに、経営や新事業の起こし方の視点が十分に組み込まれているわけではありません。私自身も、誰かの経歴を目標として今があるわけではなく、時流に乗って手探りでやってきました。医療業界には、優等生ではなかった私よりもっと潜在能力の高い優秀な人材がたくさんいます。しかし、「この人のようにやってみよう」と思える身近なロールモデルが少ないことも、挑戦をためらう一因かもしれません。
ーー先生ご自身が、そのロールモデルになろうとされているのですね。
杉野理事長
大それたことを言うつもりはありませんが、私のユニークな経験が、誰かの背中を押すきっかけになれば嬉しいですね。自衛隊や海兵隊での経験や、東工大での技術経営学。すべての経験が今の私に繋がっています。例えば、大学院では「技術経営と安全保障」というテーマが、かつての自衛隊での経験と結びつき、再び私の研究範囲になって追いついてきました。異分野の知見や経験を掛け合わせることで、これまでになかった新しい価値が生まれる、これは技術革新、イノベーションの入り口です。そのことを、私自身も証明したい。そうすることで、医療の未来に少しでも貢献できればと考えています。
悩みを抱えるすべての方へ|杉野理事長からのメッセージ
インタビューの最後に、杉野理事長からこの記事を読んでいる方々へのメッセージをいただきました。
そこには、誠実で温かい人柄と、医療に対する揺るぎない信念が込められていました。
ーーどのような方にイサナクリニックへ来てほしいですか?
杉野理事長
先端の技術経営学という「論理」で武装しながら、人の情けや泥臭い対話という「情理」を何よりも大切にする。そんなイサナクリニックの思いに共感してくださる方には、きっとうまく「ハマる」と思います。医療や技術の理解、リテラシーに自信のある方はもちろん、そうしたことが苦手な方も、決して置いてきぼりにしない温かい医療体験を約束します。私のプロフィールを見て、「東工大の医師?」「技術経営学ってなに?」「元自衛官で海兵隊留学?」と面白がって来てくださる方も大歓迎です(笑)。他のクリニックでは聞けない話ができるかもしれません。どんなきっかけであれ、このクリニックの扉を叩いていただければ嬉しいです。
ーー最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
杉野理事長
イサナクリニックは、八丁堀近隣にお住まいの方や、ビジネス街で働く皆さんが、どんな些細なことでも気軽に相談でき、安心して検査・治療を受けられるクリニックを目指しています。特に忙しい毎日を送るビジネスパーソンの方々にとって、受診機会は貴重です。私たちは、AIなどを活用して効率的な診療を提供しながらも、一人ひとりとの対話は妥協しません。むしろ、テクノロジーがあるからこそ、より深く、丁寧に皆さんと向き合えると信じています。泌尿器科、消化器内科、一般内科を軸に、皆さんの健康とQOL(生活の質)を向上させるため、スタッフ一同、全力でサポートいたします。気になる症状や、誰に相談すべきか分からない悩みがあれば、一人で抱え込まず、気軽にご来院ください。
イサナクリニック
| 診療科目 | 泌尿器科・内科・消化器内科・各種健康診断 |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目6−5 キスワイヤ八丁堀ビル 4階 |
| 診療日 | (月・水・金・土) 8:00~12:00/12:00~18:30 ※終日、昼休みなし (火・木) 8:00~12:00/13:00~18:30 |
| 休診日 | 日・祝 |
| 理事長 / 総院長 | 杉野 智啓 |
| TEL | 03-5540-0137 |
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線・JR京葉線「八丁堀」駅A3出口より徒歩2分 都営浅草線「宝町」駅A1出口より徒歩4~5分 |