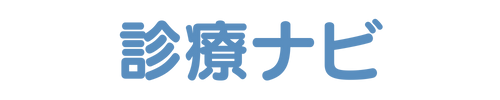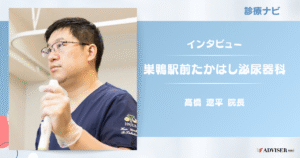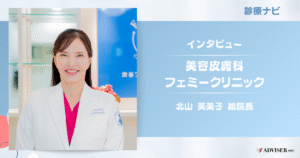2025年9月30日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「なんだか胸がドキドキする」
「健康診断で血圧が高いと言われたけど、どこの病院に行けばいいんだろう…」
「大きな病院は待ち時間が長くて大変…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
西小山駅から徒歩2分、地域に根差した医療を提供する「はるクリニック西小山」で院長を務める飛川浩治先生は、症例数の多い大学病院で心臓血管外科医として数多くの命と向き合ってきました。
その豊富な経験と知識を活かし、単なる「町のお医者さん」に留まらない「かかりつけ医」を目指しています。
この記事では、飛川院長のこれまでの歩み、大学病院を知り尽くしたからこそできる医療連携、そして患者一人ひとりに寄り添う治療への想いに迫ります。
日本トップクラスの心臓血管外科から西小山の「かかりつけ医」へ|飛川先生の歩みと想い
年間800件以上の心臓手術が行われる最前線から、地域に密着したクリニックへ。
その異色の経歴の背景には、飛川院長の信念と、日本の医療システムに対する真摯な想いがありました。
これまでの歩みと、西小山の地で開業した理由を伺いました。
ーー先生は大学をご卒業後、心臓血管外科の道に進まれました。数ある診療科の中で、なぜこの分野を専門に選ばれたのでしょうか?
飛川院長
大学卒業後、当時、日本の心臓外科を牽引していた東京女子医科大学の門を叩きました。私が研修医になった頃、多くの大学病院では心臓手術の症例数が年間100件程度でしたが、女子医大はすでに800件を超えていました。そこでは、3つも4つもの手術が同時に進行している。教授クラスの医師が何人もいて、活気に満ちあふれている。そのダイナミックな環境に圧倒され、「ここで学びたい」と強く思ったのがきっかけです。
大学病院では通常2年ほどの研修が一般的ですが、女子医大は欧米にならった6年制のレジデント制度を導入しています。おかげで、同年代の医師と比べても圧倒的な経験を積むことができ、それが私の医師としての大きな土台となっています。
ーーその後、アメリカへの留学もご経験されていますね。
(飛川院長)
もともと高校生くらいから海外への憧れが強く、医師という仕事を選んだ背景にも「海外で活躍したい」という想いがありました。女子医大での研修を終えた後、母校の横浜市立大学に戻り、その後アメリカのピッツバーグ大学へ留学する機会を得ました。そこで移植研究に携わった経験は、視野を広げる上で非常に貴重なものだったと感じています。
ーー輝かしいキャリアを積まれた後、なぜ開業医の道を選ばれたのですか?
飛川院長
正直に言うと、長年身を置いてきた大学病院の医療、特に心臓外科のあり方に疑問を感じるようになったのが大きな理由です。私が手術に明け暮れていた頃、一部では病院の経営のために手術件数を増やす、という風潮が強まっていました。中には「本当にこの患者さんに今、この手術が必要なのだろうか」と首を傾げたくなるようなケースも散見されました。
また、日本の医療システムの問題点も見過ごせませんでした。日本は心臓外科医の数が非常に多いのですが、医師の数を国や医学会が適切にコントロールする仕組みがありません。結果として、専門医の資格を持っていても、実際に執刀経験がほとんどない医師も少なくないのが実情です。手術が好きでこの道に入りましたが、このような状況の中で手術を続けていくことに、ある種の虚しさを感じてしまったのです。
そこで一度立ち止まり、「残りの医師人生をどう歩むか」を考えました。そして、これまでの高度医療の経験を、もっと身近な場所で、一人ひとりの患者さんのために役立てたいと思い至りました。まずは自分の知らない分野を学ぼうと、訪問診療を専門とするクリニックで2年間お世話になり、在宅医療の現場を学びました。その経験を経て、2013年にこの西小山の地で「はるクリニック西小山」を開院したのです。

「とりあえず大学病院へ」はもう古い?はるクリニック西小山が提供する”ハブ”という価値
「何かあったら大きな病院へ」と考える方は多いかもしれません。
しかし、そこには長い待ち時間や何度も通院する手間といった課題もあります。
はるクリニック西小山は、そうした患者さんの負担を軽減し、最適な医療へと繋ぐ「ハブ」としての機能に力を入れています。
ーー先生のクリニックが持つ「強み」は何だと思われますか?
飛川院長
当院の特徴の一つは、私が20年近く大学病院の中枢にいたこと、これに尽きると思います。多くの開業医の先生方は、10年ほど経験を積んで開業されるケースが多いです。しかし私は、様々な病院で心臓血管外科のチーフとして勤務し、大学病院という組織の仕組み、良いところも悪いところもわかっています。
「大学病院に行ったら、まず初診で待たされて、次に検査の予約をして、後日また検査のために来院して、さらに後日、結果を聞きに行く…」といった一連の流れや、科をたらい回しにされてしまう可能性など、患者さんが直面するであろう状況が手に取るようにわかるのです。この「内部を知っている」という経験が、患者さんをスムーズに最適な医療へ導く上で、何よりも役立っていると自負しています。
ーー具体的に、患者さんはどのようなメリットを受けられるのでしょうか?
飛川院長
例えば、当院で診察した結果、CT検査が必要だと判断したとします。通常なら、紹介状を書いて大学病院へ行っていただき、そこからまた予約、という流れになりますよね。しかし当院では、連携している病院の検査予約を、クリニックから直接、電話一本やインターネットで取ることが可能です。
患者さんには、当院で発行した予約票を持って、指定された日時に直接病院の検査室へ行っていただくだけ。検査結果は当院に送られてくるので、説明も当院で行います。つまり、患者さんが大学病院に行くのは、検査当日の1回だけで済むのです。初診、予約、結果説明と、本来なら3回、4回と足を運ばなければならなかった手間が、大幅に削減されます。
これは、病院側が経営効率化のために、検査機器の稼働率を上げたいというニーズと、私たちの「患者さんの負担を減らしたい」という想いが合致した、いわばWin-Winの仕組みです。私たちはこの仕組みを最大限に活用し、患者さんにとっての「無駄」を省くことを心がけています。まさに、地域の医療機関と基幹病院とを結ぶ「ハブ」のような役割ですね。
ーーなぜ、それほど多くの病院とスムーズな連携ができるのですか?
飛川院長
私が特定の大学の出身者で固められた派閥に属していない、という点が大きいかもしれません(笑)。横浜市立大学を卒業し、東京女子医大で学び、その後も様々な病院で勤務してきたため、特定の病院との強いつながり、いわゆる「しがらみ」がありません。だからこそ、純粋に患者さんの症状や価値観、ご希望に合わせて、最適な病院をフラットな視点で選んでご紹介できるのです。
この地域には、NTT関東病院、昭和大学病院、東京医療センターなど、あらゆる方面に大病院・基幹病院があります。それぞれの病院の得意分野や特徴を把握した上で、「この手術ならあの先生がいい」「とにかく早く検査を受けたいならこの病院がいい」といった、オーダーメイドの紹介が可能です。
また、ITを積極的に活用していることも理由の一つです。もともと早稲田大学で学んでいたこともあり、PCやシステムを効率化に活かすのが好きなんです。「行列ができるクリニックが良いクリニックだ」という風潮がありますが、私はそうは思いません。患者さんの貴重な時間を奪わないよう、これからも効率的な診療体制を追求していきたいですね。
手術だけが選択肢ではない|元・執刀医が語る、患者にとっての「最善の医療」
長年、メスを握り続けてきた飛川院長。しかし、その治療方針は「手術ありき」ではありません。
患者一人ひとりの人生を見据え、時には「手術をしない」という選択肢も提示します。
その根底にある、医療への深い哲学を伺いました。
ーー心臓の病気と聞くと、すぐに「手術」をイメージしてしまいます。
飛川院長
もちろん手術でしか救えない命はたくさんありますし、私自身もそのために技術を磨いてきました。しかし、誤解しないでいただきたいのは、手術をすれば100%良くなるわけではない、ということです。どんな手術にも後遺症のリスクは伴いますし、手術は成功しても、その後寝たきりになってしまうケースもゼロではありません。
例えば、50代の方と80代の方で、同じ心臓の病気が見つかったとします。50代の方であれば、体力もあり、これからの人生を考えれば早期に手術をした方が良いかもしれません。しかし、80代の方で、手術をしなくても薬などでコントロールしながら10年は元気に過ごせると判断したならば、あえて手術をしないというのも、非常に重要な選択肢なのです。どこまでなら手術をせずに頑張れるか、その見極めこそが、心臓外科を専門としてきた私の最も重要な役割だと考えています。
ーー複数の病気を抱えているご高齢の患者さんも多いかと思います。治療の優先順位は、どのように判断されるのですか?
飛川院長
それこそが、かかりつけ医の腕の見せ所だと思っています。一つひとつの病気には、学会が定めた「ガイドライン」という治療の指針があります。しかし、病気が5つ、10つと増えた時に、「どの治療を優先すべきか」は、どのガイドラインにも書かれていません。
増え続ける薬の問題もあります。そのすべてを杓子定規に治療することが、果たしてその患者さんの幸せに繋がるのか。私は、常に「もしこの人が自分の親だったら、自分自身だったらどうするか」という視点で考えるようにしています。大学病院時代、心臓の合併症に対応するため、脳外科や消化器科など、あらゆる科の先生方と連携し、全身を管理する経験を積んできました。その経験が今、患者さん一人ひとりにとっての「最善」を考える上で、本当に役立っていると感じます。
薬だけに頼らない医療。5年後、10年後を見据えた「はるクリニック西小山」の治療スタイル
飛川院長の診察は、ただ薬を処方して終わりではありません。
患者さん一人ひとりの生活背景や年齢を考慮し、未来の健康までも見据えたきめ細やかな指導を重視しています。
ここでは、薬との上手な付き合い方や、日々の生活で気をつけるべきポイントについて、先生の考えを伺いました。
ーー生活習慣病の治療というと、長く薬を飲み続けるイメージがあります。先生は薬の処方について、どのようにお考えですか?
飛川院長
基本的に、薬の量はできるだけ少なくしたいと考えています。例えば、コレステロール値が高い20代、30代の方であれば、まずは「運動しなさい、ご自身の力で頑張ってみなさい」とお伝えします。もちろん、40代、50代と年齢を重ね、心臓や血管の病気のリスクが高まってくる方には、「将来のことを考えると、このお薬を飲み始めた方が良いかもしれません」と、その方の状況に合わせたメリハリのある提案をします。医者の仕事は薬を出すことだと思われがちですが、私は5年後、10年後の患者さんの健康を考えた時に、本当に必要な薬を、適切な量だけ処方することが大切だと考えています。
ーー薬以外の部分では、どのようなアドバイスをいただけるのでしょうか?
飛川院長
例えば高血圧の治療では、薬を飲むことと同じくらい、ご自身の血圧を日々記録し、把握すること(モニタリング)が重要だと考えています。血圧の薬を飲んでいるから大丈夫、と安心してしまい、ご家庭で血圧を測らない方がいますが、それでは不十分な場合があります。当院では、記録したデータをクリニック側でも確認できる血圧管理アプリの活用をお勧めすることもあります。毎日でなくても「3日に1回は測ってください」など、その方の状態に合わせて具体的なアドバイスをします。こうした地道な自己管理が、将来の深刻な病気を防ぐことに繋がるのです。
ーー先生は心臓血管外科がご専門ですが、専門外の症状について相談しても良いのでしょうか?
飛川院長
もちろんです。むしろ、何でも相談してほしいと思っています。大学病院で心臓手術後の患者さんを管理するということは、心臓だけでなく、合併症として起こりうる脳、消化器、腎臓など、あらゆる臓器の状態を把握し、全身を管理することと等しいのです。その経験から、どの科でどのような検査や治療が行われているか、大体のことは理解しています。
ですから、例えば「胃カメラを鼻から楽に受けたい」というご希望があれば、「それなら〇〇病院の内視鏡センターが新しくできたのでご案内できますよ」とか、「△△クリニックなら電話一本で予約が取れますよ」といった、具体的で実践的な情報を提供できます。専門外のことでも、あなたにとって最適な医療への道筋を示すことこそ、かかりつけ医の最も重要な役割だと考えています。
その胸の痛み、放置しないで|かかりつけ医が”救急の入り口”に
はるクリニック西小山には、風邪や生活習慣病の患者さんと並んで、心臓手術後のフォローアップを求める患者さんも多く訪れます。
ーー普段、どのような症状の患者さんが多く来院されますか?
飛川院長
大きく二つに分かれる傾向があります。一つは、近隣にお住まいで、風邪やインフルエンザ、高血圧や脂質異常症といった生活習慣病で定期的に通院されている方々です。もう一つが、私の心臓血管外科医としての経歴を頼りに、心臓手術後のフォローアップを求めて来られる方々です。大学病院も多くの患者さんを抱え、手術後の状態が落ち着いた方までは手が回らないこともあり、最近では病院側から「アフターフォローをお願いします」とご紹介いただくケースも増えてきました。
ーー高血圧の治療で、先生が特に重視されていることは何ですか?
飛川院長
日々の血圧を正しくモニタリングすることです。残念ながら、ただ薬を処方するだけで、血圧測定の重要性や正しい測り方を十分に指導していないケースが少なくありません。特に大切なのが、早朝の血圧です。ご自宅での血圧をきちんと把握せず、漫然と薬を飲み続けていると、5年後、10年後に大きな差となって現れる可能性があります。
当院では、患者さんに血圧管理アプリをお渡しし、記録していただいたデータがクリニックに届く仕組みを導入しています。もちろん、毎日測るのが大変な時もあるでしょう。そういう時は「3日に1回でいいですよ」とお伝えするなど、無理なく続けられるようサポートします。ただ薬をもらうだけでなく、5年後、10年後の健康を見据えた医療を提供している、という自負はあります。
ーーその他に先生のクリニックの特徴はございますか?
飛川院長
当院に来る救急車が多いということです。当院に救急車で運ばれて来るのではなく、当院から救急車を呼んで、大病院へ搬送するケースが月に数件あります。「胸がむかむかする」といった、ご自身では「大したことない」と思われている症状で来院された方が、実は心筋梗塞や重篤な不整脈を起こす寸前だった、ということがあるのです。
診察の結果、「これはすぐに専門的な治療が必要だ」と判断すれば、その場で連携している病院の循環器内科や集中治療室に直接電話をかけ、状況を説明して受け入れ態勢を整えてもらい、救急車で向かっていただきます。もし、ためらって受診が遅れていたら、深刻な事態になっていたかもしれません。何か気になる症状があれば、「これくらいで…」と遠慮せず、まずは相談に来ていただきたいですね。
目黒区・品川区を中心とする地域の皆様へ|飛川院長からのメッセージ
インタビューの最後に、クリニックのこれからと、地域の皆様へのメッセージをいただきました。
ーー「心臓外科」とクリニック名にあると、少し敷居が高いと感じてしまう方もいるかもしれません。
飛川院長
それは、開業してからずっと感じている課題です(笑)。「自分は心臓が悪いわけじゃないから」と、来院をためらってしまう方もいらっしゃるようです。本当は、地域のかかりつけ医として、どんな些細なことでも相談してほしい、という想いで「はるクリニック西小山」と名付けました。心臓外科医としての専門性は私の強みですが、それ以上に、皆さんの健康をトータルでサポートするホームドクターでありたいと思っています。
高血圧も、コレステロールも、風邪だと思っていた咳も、巡り巡って心臓に繋がっていることがあります。どんな症状でも、まずは気楽にいらしてください。
ーー最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
飛川院長
体のことで何か心配なことがあれば、何でもご相談ください。それが仮に私の専門外のことであっても、お話を伺い、状況を整理し、次に何をすべきか、どこへ行くべきか、最善の道筋をお示しすることはできます。
私は、だらだらとお話を引き延ばすような診療はしません。要点を的確に捉え、あなたにとって今、何が一番大切かをお伝えします。皆様の今後の人生をトータルで管理していける、そんなパートナーのような存在でありたいと思っています。お気軽にご相談ください。
はるクリニック西小山
| 診療科目 | 内科、心臓血管外科、循環器内科、訪問診療 |
|---|---|
| 住所 | 〒142-0062 東京都品川区小山6丁目1‐1 ラメゾンシータ1階 |
| 診療日 | (月・火・木・金・土) 9:00-12:15 (月・火・木・金) 16:00-18:30 |
| 休診日 | 水・日 |
| 院長 | 飛川 浩治 |
| TEL | 03-5794-8630 |
| 最寄駅 | 東急目黒線「西小山駅」から徒歩2分 |