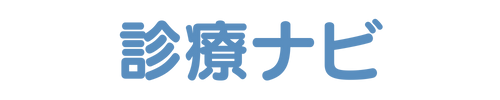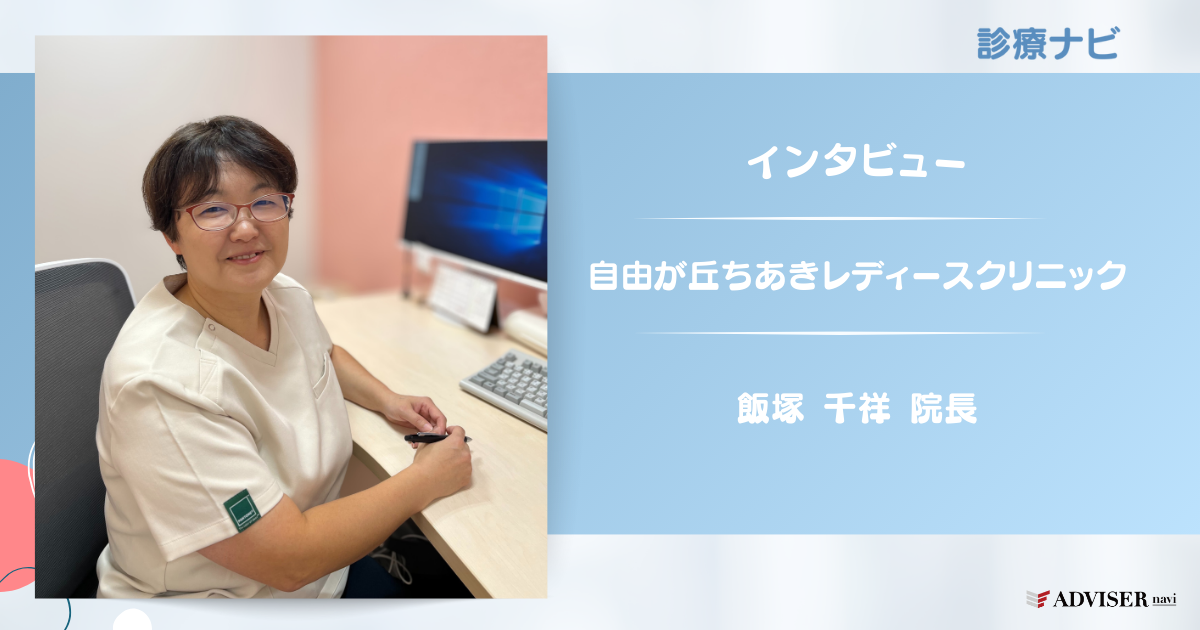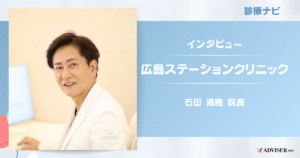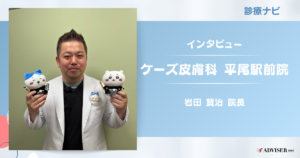2025年7月19日に実施したインタビューを元に執筆しています。
「生理痛はあって当たり前」そう思っていませんか?
その不調は病気のサインかもしれません。
今回は、自由が丘ちあきレディースクリニック・飯塚 千祥(いいづか ちあき)院長に婦人科のがん治療やクリニックで治療できる症状など、色々とお聞きしました。
婦人科がん治療の最前線で活躍してきた専門医が、なぜ「がんになる前」の予防に情熱を注いでいるのでしょうか。
自由が丘ちあきレディースクリニックの開業|「救えるはずの命があった」―婦人科がん治療の最前線から、予防医療の道へ
年間数千件もの手術が行われる、がん治療の拠点病院。
その第一線で婦人科腫瘍専門医として腕を振るい、後進の育成にも尽力してきた飯塚千祥院長。
多くの命を救う一方で、日に日に強くなる想いがあったと言います。
ーー先生は長年、大学病院やがん専門病院で婦人科がん治療の最前線にいらっしゃったと伺いました。なぜ、地域に根差したクリニックの開業を決意されたのでしょうか?
飯塚院長
大学病院やがん専門病院の役割は、すでに「がん」と診断された患者さんの治療を行うことです。私たちは最高の医療を提供すべく日々研鑽を積んでいますが、どんなに医療が進歩しても、がんになってからの治療には限界があります。多くの患者さんを診る中で痛感したのは、「がんになる前の段階で介入することの重要性」でした。
例えば、子宮頸がんや子宮体がんの多くは、がんになる前の「前がん病変」という、いわば“がんの芽”の状態が何年か続きます。この段階で発見し、適切に対処できれば、がんそのものの発症を防ぐことが期待できるのです。しかし、大学病院には検診目的やちょっとした症状で気軽に訪れることはできません。病気と診断された方しか診ることができないのです。
もっと早い段階で、病気になる前の段階から女性の一生に寄り添いたい。予防接種や検診を通じて、がんを未然に防ぎたい。その想いが日に日に強くなり、「予防」を主体とした医療を実践するために、クリニックを開業するという決断に至りました。
ーーそもそも、数ある診療科の中で産婦人科医の道を選ばれたのはなぜですか?
飯塚院長
私が産婦人科に惹かれたのは、女性の一生をトータルで診られるという点です。多くの科が臓器別や疾患別に細分化されていく中で、産婦人科は思春期に始まり、性成熟期、妊娠・出産、更年期、老年期まで、一人の女性のライフステージすべてに関わることができます。
手術もしたい、抗がん剤治療もしたい、患者さんと長く寄り添いたい…そう考えた時に、診断から治療、そしてその後の人生まで一貫して関われる産婦人科は、私にとって非常に魅力的な分野でした。
また、小児科は子どもで終わりですが、私たちは生まれる前から関わり、おばあちゃんになるまでお付き合いが続きます。これほど幅広く、深く患者さんと関われる科は他にないと思っています。
ーー開業を決意される上で、特に印象に残っている経験はありますか?
飯塚院長
はい。大学病院で様々な患者さんと向き合う中で、病気の予防や早期発見の重要性を痛感する場面が数多くありました。
例えば、妊娠中に子宮頸がんが見つかり、急速に進行してしまうようなケースも見てきました。最善の治療を尽くしても、残念ながらお母様の命を救うことができないという、非常に悔しい経験もします。後になって、そのがんがワクチンで予防が期待できるタイプであったと知ることも少なくありません。
「予防という手段があったのに」という現実は、医師として非常に重くのしかかります。「がんで悲しむ人を一人でも減らしたい」、そうした数々の経験の積み重ねが、予防医療を中心としたクリニックを開業しようと考えた原点だと思います。
自由が丘ちあきレディースクリニックの診療・手術|全国から患者が訪れる子宮頸がんのための「日帰り手術」とは
自由が丘ちあきレディースクリニックには、その専門性の高さから、近隣住民だけでなく、北は青森から、そして関西からも患者さんが訪れます。
その目的の一つが、飯塚院長が執刀する子宮頸がんの日帰り手術です。
ーー子宮頸がん検診で「要精密検査」という結果が出た場合、どのような検査や治療を行うのでしょうか?
飯塚院長
まずは、「コルポスコープ」という拡大鏡を使って子宮の入り口(子宮頸部)を詳しく観察し、病変が疑われる部分の組織を少しだけ採取して調べる精密検査を行います。その結果、がんになる一歩手前の「異形成」という状態だと診断された場合に、手術による治療を検討します。
当院では、異形成の進行度合いに応じて、「レーザー蒸散術(じょうさんじゅつ)」や「子宮頸部円錐切除術(えんすいせつじょじゅつ)」といった治療を日帰りで行っています。レーザー蒸散術は、病変部をレーザーで焼き、蒸発させて取り除く方法です。一方、円錐切除術は、子宮頸部を円錐状にメスで切除する方法で、より進行した異形成に用いられます。
ーー日帰りで手術ができるというのは驚きです。入院の必要はないのでしょうか?
飯塚院長
はい。当院では静脈麻酔を使用し、手術は午前中に行えば、2時間ほどお休みいただいて、午後にはご帰宅いただけます。大学病院であれば入院が必要なケースでも、私たちの経験と技術、そして整った設備によって、患者さんの身体的・時間的なご負担をできるだけ抑えた日帰り治療が可能になっています。
大きな病院と同等レベルの治療を、身近なクリニックで提供すること。それが私たちの役割だと考えています。
ーー手術となると、特に若い方は将来の妊娠への影響が心配だと思います。
飯塚院長
だからこそ、私たちはこの手術を単なる切除ではないと考えています。産婦人科医になって若手が最初に行う手術の一つが、この円錐切除術なのですが、ここで医師の技量の差が大きく出ます。必要以上に大きく切除してしまうと、子宮頸部が短くなり、将来の妊娠で早産のリスクが高まる可能性があります。
私たちは婦人科腫瘍専門医としての豊富な経験を活かし、病変を確実に取り除きつつ、切除範囲を必要最小限に留めることで、将来の妊娠への影響を限りなく少なくすることを追求しています。これは、数多くの症例を経験し、子宮の構造を知り尽くしているからこそできる、私たちの強みです。
ーー治療後のフォローアップが非常に重要だと伺いました。具体的にどのようなことをするのですか?
飯塚院長
ここが最も重要なポイントの一つです。残念ながら、異形成の治療において、「何をもって“治った”とするか」を明確に定義して実践している医師は、まだ多くないのが現状です。治療して、数ヶ月後の検診で異常がなければ「治りました」と言われてしまうケースも少なくありません。
しかし、私たちはそれでは不十分だと考えています。なぜなら、異形成の根本原因はHPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスだからです。治療後はハイリスクHPVが陰性になるまでフォローアップし必要があれば追加治療をします。
また、円錐切除術後のHPVワクチン接種で再発頻度が20%から5%に減少するというエビデンスに基づき、将来の再発予防のためのHPVワクチン接種も積極的に推奨しています。ウイルスが陰性になると再発リスクは下がりますが、再感染の可能性もあるため、定期的なフォローが大切です。
「もう大丈夫ですよ」と心から言える状態になるまで、しっかりと見届ける。そこまでやって、初めて「治療が完了した」と言えるのです。
【専門医が解説】本当に意味のある「がん検診」とは?検診の精度と賢い受け方
多くの自治体で推奨されている子宮頸がん検診。
しかし、その検診さえ受けていれば100%安心、とは言えないそうです。
自分の体を守るために、私たちが知っておくべき検診の知識とは何でしょうか。
ーー子宮がん検診についてお聞きします。「検診を受けていれば安心」というわけではないのでしょうか?
飯塚院長
現在、自治体の検診などで一般的に行われている子宮頸がん検診の診断精度は、約50〜60%だと言われています。もちろん、定期的に受け続けることで発見精度は高まりますが、1回の検査では見逃されることがあります。
一方で、先ほどお話しした、がんの原因となるウイルスそのものを調べるHPV検査の診断精度は約90%とされています。ここからわかるように、精度が全く違うのです。子宮頸がん検診で「陰性」が続いているからと安心していると、実はウイルスが体内に潜み続けていて、何年も経ってから突然がんが見つかる、というケースも実際にあります。
ーーでは、私たちはこれから、どのように検診を受ければ良いのでしょうか?
飯塚院長
理想を言えば、子宮頸がん検診とHPV検査の両方を併用して受けることをお勧めします。そうすることで、見逃しのリスクを大幅に減らすことができます。欧米ではこの併用検診がスタンダードになってきています。
日本ではまだ自費診療になることが多いですが、数年に一度でもHPV検査を受けておくことで、ご自身の本当のリスクを知ることができます。当院ではもちろん、この併用検診に対応していますので、ぜひご相談ください。
ーー子宮頸がんと並んで、子宮体がんも心配です。こちらはどのように注意すればよいでしょうか?
飯塚院長
子宮体がんは、子宮頸がんに比べて見逃されがちな婦人科がんです。特に注意してほしいサインが、更年期前後の不正出血や月経不順です。「もう閉経が近いから、生理が不規則なのは当たり前」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、それが正常な閉経に向かうサインなのか、子宮体がんへ向かうサインなのかを見極めることが極めて重要です。
また、過多月経、つまり生理の量が非常に多い状態を放置することも、子宮体がんのリスクを高めることがわかっています。40代以降で経血量が増えたり、レバーのような塊が出たりする方は、一度検査を受けることを強くお勧めします。
ーー子宮体がんの検査は「痛い」というイメージがあります。
飯塚院長
そうですよね。多くの方がそうおっしゃいます。従来の検査器具は硬く、痛みを感じやすいものでした。ですが、当院では「がん研有明病院」で開発された、従来品の3分の2ほどの細さで、しなやかな素材の検査器具を採用しています。
これにより、ほとんど痛みを感じることなく検査を受けていただくことが可能です。実際に、他院で「痛くて耐えられなかった」という患者さんからも、「痛くなかった」というお声をたくさんいただいています。検査の痛みへの不安から受診をためらっている方がいらっしゃれば、ぜひ一度当院にご相談いただきたいです。
生理痛、更年期、漢方…各分野の専門家が集結する「チーム医療」という強み
自由が丘ちあきレディースクリニックが提供する医療の質を支えているのは、院長が持つ技術だけではありません。
女性のための医療を支えていくにあたって、様々な専門性を持つドクターがそれぞれの知見を持ち寄り、一人の患者を多角的に支える「チーム医療」体制がありました。
ーーこちらのクリニックには、様々な専門分野の先生方がいらっしゃるそうですね。
飯塚院長
はい。私と的田副院長は婦人科腫瘍が専門ですが、それ以外に、月経不順や更年期障害といった内分泌(ホルモン)の病気を専門とする常勤の宮上医師がいます。
さらに、週に一度ですが、漢方医学の専門医である田中医師も診療にあたっています。助産師や保健師、薬剤師といった多職種のスタッフも在籍しており、まさにチームで患者さんをサポートする体制が整っています。
ーー具体的に、どのように連携して一人の患者さんを診ていくのですか?
飯塚院長
例えば、私が子宮頸がんの前がん病変で定期的にフォローしている患者さんが、40代後半になり更年期の症状(ホットフラッシュや気分の落ち込みなど)を訴えられたとします。その場合、次回の検診は半年後でも、その間の更年期症状の治療は、ホルモン専門の宮上医師に引き継ぎます。
「次の検診までは宮上先生に診てもらいましょう」というように、クリニック内でスムーズに連携できるのです。患者さんは病院を変える必要がなく、私たち医師はカルテを通じて常に情報を共有しています。その結果、患者さんは安心して、その時々の症状に最適な専門医療を受けることができます。
一人の患者さんを、我々ドクターが入れ替わりながら、それぞれの専門領域で支えていく。これが当院が目指すチーム医療の形です。
ーー西洋医学だけでなく、漢方の治療ができる先生もいらっしゃるのはなぜでしょうか?
飯塚院長
実は、日本の医学部では漢方医学を体系的に学ぶ機会がほとんどありません。多くの医師は、添付文書の効能書きを見て、「この症状ならこの漢方」というように処方しているのが実情です。
しかし、本来の漢方医学は、その人の体質や状態を総合的に診て処方を決める、非常に奥が深い診療となります。
当院に来てくれている田中医師は、大学院で本格的に漢方医学を学び、専門医の資格を持つエキスパートです。彼女の診察は、問診や舌の所見などからその人の「証(しょう)」を見極め、その人に本当に合った漢方薬をオーダーメイドで処方しています。処方の仕方が全く違うのです。
ピルなどの西洋薬が合わない方や、なんとなく続く不調に悩む方にとって、漢方治療は選択肢の一つとなります。
「生理痛は当たり前じゃない」すべての女性に伝えたい体のサイン
「これくらいは仕方ない」。
多くの女性がそう思い込み、我慢してしまっている症状の中に、将来の不妊や病気につながる重大なサインが隠れているそうです。
ーー先生が診察をされていて、特に「見過ごさないでほしい」と強く感じる症状は何ですか?
飯塚院長
それは、繰り返しになりますが「生理痛」です。軽い不快感や痛みを感じる人はいますが、強い生理痛は病気のサインである可能性があります。「1日目くらいは痛いもの」「市販の鎮痛剤を飲めば大丈夫」と思っている方があまりにも多い。しかし、生理痛を訴える方の中には「子宮内膜症」という病気を患っている可能性もあります。
ーー子宮内膜症とは、どのような病気なのでしょうか?
飯塚院長
本来、子宮の内側にしか存在しないはずの子宮内膜組織が、卵巣や骨盤の中など、子宮以外の場所で増殖してしまう病気です。生理のたびにその場所で出血と炎症を繰り返し、癒着や卵巣の腫れ(チョコレート嚢胞)などを引き起こします。そして最も深刻なのは、子宮内膜症と診断された方の3割から5割が、不妊症になるということです。痛みだけでなく、将来子どもを望んだ時に、その夢を妨げる原因になりかねないのです。
ーー何歳くらいから婦人科を受診することを考えればよいでしょうか?
飯塚院長
生理が始まって、もし生理痛があるのであれば、小学生、中学生からでも受診してほしいです。内診に抵抗があるのは当然ですから、無理に行うことはありません。お腹の上からの超音波検査や、丁寧な問診だけでもわかることはたくさんあります。早期にピルなどによる治療を開始することで、子宮内膜症の進行を抑え、将来の不妊リスクを下げることが期待できます。
ーー思春期のお子さんを持つ親御さんへ伝えたいことはありますか?
飯塚院長
ぜひ、親御様世代の「生理痛は我慢するもの」という価値観をアップデートしていただきたいです。「うちの子、生理痛がひどいみたい」と感じたら、それは婦人科を受診するサインかもしれません。小児科では対応が難しい生殖器の診察も、私たち婦人科医なら専門的に行うことができます。
モナリザタッチ|デリケートゾーンの悩みに寄り添う治療とは
自由が丘ちあきレディースクリニックでは、がん治療や月経トラブルだけでなく、加齢に伴う女性特有の悩みにも、最新の知見と技術で応えています。
ーー新しい取り組みとして「モナリザタッチ」という治療を導入されたそうですね。これはどのようなものでしょうか?
飯塚院長
モナリザタッチは、閉経後の女性ホルモンの減少によって生じる、膣や外陰部の不快な症状(乾燥、かゆみ、痛み、ゆるみ、尿もれなど)を改善するためのレーザー治療です。膣の粘膜にレーザーを照射することで、コラーゲンの生成を促し、粘膜のふっくらとした潤いや弾力を取り戻すことを目指します。
ーーどのような悩みを抱えた方が、この治療を受けに来られるのでしょうか?
飯塚院長
「もう10年もかゆみが治らない」「性交痛がつらくて、パートナーとの関係もこじれてしまった」など、本当に切実な悩みを抱えて来院される方が多いです。皮膚科や他の婦人科に行っても、「年のせい」「菌が原因でしょう」と言われて、抗菌薬やステロイドを処方されるだけで、全く良くならなかったという方々です。
実は、おりものに常在菌がいるのは当たり前のことで、それ自体がかゆみの直接の原因になることは少ないのです。根本的な原因である粘膜の萎縮を改善しない限り、症状は繰り返してしまいます。
モナリザタッチは膣粘膜の萎縮を改善することを目的とした治療です。有効との報告はありますが、長期的な効果や安全性についてはまだ研究段階で、希望する方には十分にご説明した上で行っています。
ーーそのような症状の裏に、重大な病気が隠れていることもあるそうですね。
飯塚院長
その通りです。これも専門医としての視点が重要になる部分です。長年かゆみに悩んでいた患者さんを診察した際、ただの炎症ではない、特有の湿疹を見つけました。組織を採って調べてみたところ、「乳房外パジェット病」という、ごく稀な皮膚がん(上皮内がん)であることがわかりました。何万人に一人という稀な病気ですが、私はこれまでに数名、がん専門病院にご紹介しています。
ただ症状を聞いて薬を出すだけでなく、常に「何か別の病気が隠れていないか」という視点を持ち、見慣れていないと見逃してしまうような病気のサインを捉えること。これも、悩んで来られた患者さんに対する私たちの責任だと考えています。
飯塚 千祥院長が診療において心がけていること
専門性の高い医療を提供する一方で、飯塚院長が何よりも大切にしているのは、患者が安心して心を開ける場所であること。
受診への高いハードルを取り払うための様々な工夫が、クリニックの随所に凝らされています。
ーー診察への恐怖心から、なかなか受診に踏み出せない方も多いと思います。安心できるクリニックにするために心がけていることはございますか?
飯塚院長
女性として、そして一人の医師として、本当によくわかります。だからこそ、私たちは患者さんに安心していただくことを何よりも優先しています。先ほどお話しした痛みの少ない器具の選択はもちろん、診察の際には十分な説明を行い、ご質問にも丁寧にお答えします。また、中でも知っていただきたいのは、内診はすべての患者さんに必須ではないということです。
怖がっている方や、性交渉の経験がない方に、いきなり内診台に上がってもらうようなことは決してありません。お腹の上からの超音波検査や、お話を聞くだけで解決できることもたくさんあります。患者さん一人ひとりの年齢や状況に合わせた、オーダーメイドの診察を心がけています。
ーーオンライン診療も行っているそうですが、どのように活用すればよいでしょうか?
飯塚院長
ピルの継続処方など、定期的なお薬が必要な方で、なかなか来院の時間が取れないという方に多くご利用いただいています。また、「婦人科に行くのが怖いけれど、まずは相談だけしてみたい」という、初診の方も歓迎しています。オンラインでまずお話ししてみて、そこで「やはり一度診察を受けましょう」となれば、来院への心の準備もしやすいかと思います。
ただし、ピルのオンライン処方には注意も必要です。ピルには血栓症などの副作用のリスクがあり、定期的な血圧測定や問診が欠かせません。安易にオンラインだけで処方を続けるのではなく、年に1〜2回は必ず対面で診察を受け、安全に服用を続けていただきたいと考えています。
自由が丘ちあきレディースクリニックのこれから
飯塚院長が目指すこれからの自由が丘ちあきレディースクリニックの未来について伺いました。
ーーこれからの展望や実現したいことはございますか?
飯塚院長
「すべての女性のがんを予防したい」。この一言に尽きます。これまで、がん治療の最前線で多くの命と向き合ってきたからこそ感じるのですが、婦人科のがんを取り扱うことができるクリニックは決して多くはありません。そのため、大学病院レベルの専門性と、どんな些細な悩みにも耳を傾ける温かさを両立させた、女性のためのかかりつけクリニックを目指していきます。
ーー最後にこれから受診される方に向けてメッセージをお願いします。
飯塚院長
生理痛、月経不順、更年期の不調、デリケートゾーンのお悩み。婦人科は、病気になってから慌てて駆け込む場所ではなく、健康で自分らしい人生を送り続けるために、定期的に訪れてほしいと考えています。ぜひお悩みを抱えていたら、少しでも不安に感じるようなことがあればご相談ください。
自由が丘ちあきレディースクリニック
| 診療科目 | 婦人科 |
|---|---|
| 住所 | 〒152-0034 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘2-A |
| 診療日 | (月火木金)9:00-12:30 (月火木金)14:00-17:30 ※水曜日は9:00-12:30/15:00-18:30 ※土曜日は9:00-14:00 |
| 休診日 | 日曜・祝日 |
| 院長 | 飯塚 千祥 |
| TEL | 03-3723-1117 |
| 最寄駅 | 東急東横線・大井町線「自由が丘駅」より徒歩2分 |