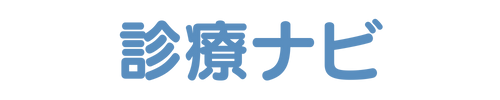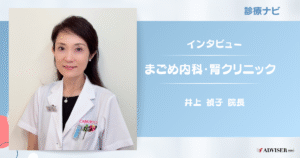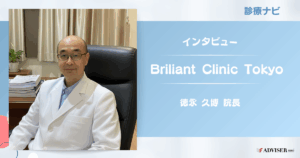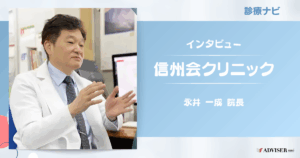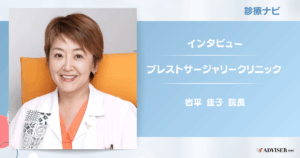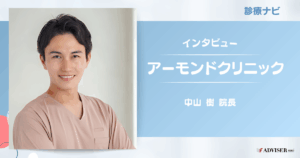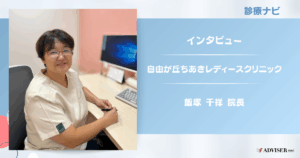2025年8月26日に実施したインタビューを元に執筆しています。
出生前診断やNIPT(新型出生前検査)、そして遺伝子検査に関心はあるけれど「何から相談すればいいのか分からない」「検査後の支援が不安」と感じていませんか。
ミネルバクリニックは、妊娠前から妊娠中、小児期、成人期、さらにはがんの予防や治療方針の提案まで、人生のあらゆるステージで遺伝医療を提供するクリニックです。
本記事では、仲田 洋美(なかた ひろみ)院長にインタビューを実施しました。
絶望の淵から生まれた使命感|異色の医師、仲田 洋美院長の軌跡
内科、がん、そして臨床遺伝。
複数の専門領域を極め、常に患者の側に立ち続けてきた仲田院長。
その道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
日本の医療が抱える矛盾との闘いの中で、いかにしてその強い使命感は育まれていったのでしょうか。
ーー先生が遺伝医療という、当時まだ日本では確立されていなかった分野に進まれたのには、どのようなきっかけがあったのでしょうか?
仲田院長:私が遺伝の世界に足を踏み入れる最初のきっかけは、大学院時代に出会った一人の患者さんでした。外国籍の女性で、ご家族にがんを患った方が多く、「自分の子どもたちに遺伝しているか知りたい」と強く望んでいました。しかし、当時の日本の大多数の大学病院では、遺伝診療は小児科が細々と運営している程度。しかも「医師が遺伝性を疑って紹介してはいけない。患者本人が自ら希望して予約を取らなければならない」という、信じがたいルールがあったのです。患者さんが心から望んでいるのに、なぜ検査すらできないのか。 私は強い違和感と憤りを覚えました。それがすべての原点です。患者さんのための医療であるはずが、制度や慣習が壁となり、本当に必要な情報や選択肢を奪っている。この現実を目の当たりにし、「誰かがやらなければならない」と強く思いました。
ーーその強い思いを抱えながらも、実際に道を切り拓いていくのは大変なご苦労があったのではないでしょうか。
仲田院長:そうですね。遺伝診療の研修を受けようと決意しただけで、大学院の指導医から「勝手なことをするな」と破門されてしまいましたから。しかし、その“破門”が、逆に私の背中を押してくれました。さらに決定的な出来事がありました。四国がんセンターで研修していたときに出会った、19歳の末期の胃がんの患者さんです。彼の一家は、父、叔父、祖父が30代で胃がんで亡くなっているという特異な病歴がありました。私は「遺伝性びまん性胃がん」を強く疑いましたが、上級医たちは「リンチ症候群」だと決めつけ、彼の「なぜ自分が病気になったのか知りたい」という切実な声を無視し続けたのです。未知のものに向き合わず、責任を回避する。そんな医師たちの姿勢を見て、心の底から思いました。「これでは患者のための医療と言えない」と。結局、無給で後期研修を行っていた医師の私には何もできず、彼は亡くなりました。私は、何もしてあげられなかった彼のことを思い、心の中で静かに誓ったのです。「あなたにしてあげられなかったことを、いつか私が、当たり前にしてあげられるようにするからね」と。この誓いが、今も私を支える原動力になっています。
ーーまさに、ご自身の信念を貫くために、組織と闘ってこられたのですね。
仲田院長:闘いというより、ただ患者さんのことだけを考えて行動していたら、そうなってしまった、という方が近いかもしれません(笑)。医局とも距離を置いていたので、遺伝カウンセリング学会の研修セミナーに申し込むときも、生まれて初めて一人でFAXを送ったくらいです。ところが、申込開始の午前0時ぴったりに送ったのですが、紙を逆さに入れてしまい、先方に届いたのは白紙のFAXでした。それに気づかず、セミナーの3日前に慌てて電話して事なきを得たのですが、このドタバタのおかげで逆に目立ってしまって。会場で、後に私の指導医となるT先生から「あなたがあの白紙FAXの方ですね」と声をかけていただいたんです。今思えば、この“失敗”こそが、私が臨床遺伝専門医として本格的に歩み出す大きな転機になりました。人生、何が幸いするか分かりませんね。
がん、内科、臨床遺伝|ミネルバクリニックの専門性
仲田院長は、がん、内科、臨床遺伝という3つの専門性を武器に、従来の医療の枠組みを超えたアプローチを実践しています。
それは、病気になってから治療するのではなく、人生のあらゆるステージで患者に寄り添い、未来の選択肢を共に探していく医療です。
ーー先生は複数の専門領域をお持ちですが、ミネルバクリニックでは具体的にどのような医療を提供されているのでしょうか?
仲田院長:私は「内科」「がん」「臨床遺伝」を専門としていますが、当院で実践していることは、従来の“治療中心”の医療とは少し異なります。例えばがん領域では、薬物療法そのものを行うのではなく、がんを発症する前にリスクを知り、予防や早期発見につなげることに力を入れています。遺伝性腫瘍のリスクがある方には、包括的がん遺伝子検査で153種類のがん関連遺伝子を調べ、発症前にリスクを把握し、定期的な経過観察(サーベイランス)の計画を立てます。また、リキッドバイオプシーという、血液でがんを調べる検査も提供しています。これは血液中に漏れ出たごくわずかながん由来のDNAを解析するもので、「がんがすでに発症しているか」「手術後に再発していないか」などを、体に負担なく繰り返し調べることが可能です。
ーー臨床遺伝の分野では、どのようなご相談が多いですか?
仲田院長:全国から本当に多種多様なお悩みが寄せられますが、特に近年、ご自身の経験を公表されたYouTuberの関根理沙さんの影響もあり、保因者検査(キャリアスクリーニング)を希望される方が増えています。これは、ご自身は発症していなくても、子どもに遺伝する病気の遺伝子を持っている可能性(保因しているかどうか)を調べる検査です。もし保因者であることが分かっても、そこで終わりではありません。お子さんに遺伝的な影響があるかもしれない場合、カップルの二人ともが同じ遺伝子の保因者だとわかって、赤ちゃんに疾患のリスクがある場合には、出生前診断という選択肢があります。NIPTでは母子の遺伝子は区別できないので、at riskなカップルの場合は確定検査(羊水検査や絨毛検査)が必要となります。このように、妊娠前からリスクを把握し、次のステップに備えることができる体制を整えています。
ーー最近では、特にお悩みの深い患者さんが来院されるケースも増えていると伺いました。
仲田院長:はい。「診断がつかないまま幼くして子どもが亡くなってしまった。原因が分からないと、怖くて次の子を持つことを考えられない」という、非常に切実なご相談を受けることが増えています。そうした場合、当院では、残された臍帯や保存検体からDNAを抽出し、遺伝子やゲノムを網羅的に調べることで疾患の原因を特定し、ご家族の再発リスクを検討するという取り組みも行っています。日本では「差別につながる」といった理由から、こうした検査が制度として十分に認められていないのが現状です。しかし、目の前で苦しんでいるご夫婦やカップルがいる。私は、そうした制約の先を見据え、「患者さんが本当に必要とする医療を実現するために、現状の枠を超えていくこと」が専門家としての使命だと考えています。
「寄り添う」とは迎合ではない|患者の権利を守り抜く、仲田 洋美の流儀
「患者さんに寄り添う」
多くのクリニックがこの言葉を掲げる中で、仲田院長の考える「寄り添い」は特別なものです。
単なる優しさや同調ではなく、法律知識と自身の壮絶な経験に裏打ちされた、「患者の権利と尊厳を守り抜く」という固い決意がありました。
ーー先生の診療スタイルを語る上で「寄り添う」という言葉がキーワードになるかと思いますが、先生の考える「真の寄り添い」とはどのようなものでしょうか?
仲田院長:「寄り添う」という言葉は、時に「何でも言うことを聞いてくれる」と誤解されがちです。しかし、私は専門家として、単なる感情的な迎合はすべきではないと考えています。私が考える「寄り添い」とは、「患者さんの権利を守ること」に他なりません。この信念を確かなものにするため、私は医師になって8年目に、大学の法学部に学士入学しました。臨床を続けながら憲法、民法、刑法などを学び、患者さんの持つ「医療を受ける権利」「説明を受ける権利」「自己決定権」が、法律上どのように保障されているのかを徹底的に理解しました。ですから、例えばNIPTで陽性の結果が出たとしても、「こうしなさい」と道を押し付けることはありません。正しい情報を分かりやすく提供し、あらゆる選択肢を示し、ご家族の将来設計まで含めて一緒に考える。最終的に「患者さんご自身が納得できる答え」にたどり着けるよう、専門家として伴走し、その自己決定権を守り抜く。それが私の考える「寄り添い」です。
ーー先生ご自身も、遺伝性疾患の当事者であり、大変なご出産を経験されたと伺いました。そのご経験が、現在の診療にどう影響していますか?
仲田院長:はい、私自身、常染色体優性(顕性)遺伝の疾患を持っています。そのため、若い頃は子どもを持つことを諦めていました。1/2の確率で遺伝するかもしれないという恐怖があったからです。しかし、思いがけず妊娠し、しかも双子でした。ところが、36週6日で、お腹の中で一人が亡くなってしまったのです。緊急帝王切開で、もう一人の息子は無事に生まれてきてくれましたが、母親になった日と、息子を亡くした日が同じ日になってしまいました。その後半年ほどは、毎日泣いて過ごしました。同じ顔の子がもう一人いたんだと思うと、涙が止まらなくて。この経験は本当に辛いものでしたが、時を経て、この経験があったからこそ、同じように苦しむお母さんたちの力になれるのだと分かりました。死産を経験して次の妊娠が怖い方、お腹の子に異常が見つかって選択を迫られている方。そういう方たちに、「私もこうだったんだよ」と伝えることができます。トータルで見れば、あの経験は今の私にとって、患者さんにフィードバックできる大きな力になっています。亡くなった息子が、今も一緒に働いてくれているような、そんな気がするんです。
ーーまた、患者さんの権利を守るためなら、医師の立場を超えることも厭わない、と。
仲田院長:おせっかいな性格なんです(笑)。在宅診療をしていた頃、家庭裁判所が選任した保佐人が、認知症の患者さんの財産を不正に使っている現場を目撃しました。「これは見過ごせない」と、家庭裁判所に直接乗り込んで問題を訴えました。「なぜ自分たちが選任した保佐人をチェックしないのか。これは制度の欠陥だ」と。家裁に乗り込んできた医師は初めてだと驚かれましたね。その後も厚生労働省や法務省などにも働きかけを続けた結果、数年後にガイドラインが新規制定され、後見人などに対する監督が強化される流れができました。目の前の一人を救うことはもちろん大切です。でも、将来の何千、何万人の状況を良くすることはもっと大切かもしれない。 だから、目の前の一人にも全力を尽くすし、制度改革にも決死の覚悟で臨む。それが私の流儀です。
NIPT業界の「闇」と、ミネルバクリニックのこだわり
近年、NIPTを提供するクリニックは急増しています。
しかしその裏で、適切な説明やフォローアップ体制が伴わない、利益優先のビジネスが横行しているという暗い側面も存在するようです。
仲田院長は、日本の医療制度が抱える構造的な問題と、業界の「闇」に警鐘を鳴らしました。
ーーミネルバクリニックは自由診療を基本とされていますが、それはなぜでしょうか?専門的な遺伝子検査こそ、保険適用で誰もが受けられるべき、と考える人もいるかと思います。
仲田院長:それは、現在の日本の保険診療の仕組みでは、やればやるほど赤字になってしまうからです。例えば、染色体の微細な異常まで調べるマイクロアレイ検査は、非常に高度な専門知識と解釈のための膨大な時間が必要になります。しかし、保険点数は検査会社に支払う費用と消費税を合わせると、完全に赤字(逆ざや)になってしまう。これでは、誰も勉強しようと思いませんし、丁寧な診療などできるはずがありません。遺伝子検査は、結果を出すこと自体は機械でもできます。しかし、その遺伝子の変異が「どういう意味を持つのか」「病気に結びつくのか」を判断し、患者さんに分かりやすく説明することこそが、最も重要で難しい部分なのです。この専門的な分析とカウンセリングにこそ価値があるのに、現在の保険制度はそこを全く評価してくれない。だからこそ、私たちは自由診療という形で、責任を持って質の高い医療を提供することを選んでいます。そうでなければ、悩みの深い患者さんを本当に支えることはできないのです。
ーーそのような状況にあるとは知りませんでした。
仲田院長:欧米では、専門家の知識や時間には当然のように正当なフィーが支払われます。医師、弁護士、会計士など、プロフェッショナルの助言を得るということは、その瞬間から契約関係が成立し、対価が発生するのが常識です。専門的な知識と経験は「社会的資源」であり、それを活用するには相応の投資が必要だという文化が根付いています。だからこそ、専門家は学び続けることができ、質の高いサービスが提供されるのです。一方、日本では「専門家の意見は無料で聞けるもの」という意識がまだ根強く残っています。保険診療の仕組みによって、医師が高度な知識と長時間の労力を提供しても、その価値が十分に評価されない状況が続いています。これでは、専門家が努力を重ねても報われず、結果的に医療や研究の質も停滞してしまいます。日本がこれから国際競争力を培い、世界に伍していくためには、専門家のフィーを軽視する文化を改める必要があります。知識と経験に正当な対価を支払うという意識を社会全体で共有しなければ、先端医療や科学技術の分野で世界に遅れをとることは避けられません。自由診療という形は、その一歩として「専門性に正しく価値を認める仕組み」をつくり、患者さんに真に有益な医療を提供するための選択でもあるのです。
ーーその他にも保険診療ではなく自由診療で行う理由はあるのでしょうか?
仲田院長:はい。保険診療にできない理由がもう一つ厳然とあります。それは、健康保険法第63条 に「被保険者が、業務外の事由による 疾病、負傷、出産又は死亡 に関しては、この法律の定めるところにより、保険給付を行う。」と定められています。さらに、健康保険法 第74条から療養の給付の内容が定められており、「治療を目的とする医療行為」に限定されています。 たとえば、健康診断や予防接種は治療を目的としていないので、健康保険は使えません。ですので、当院で扱っているような遺伝子検査はそもそも保険診療の枠組みに乗らないのです。ですが、保険診療の枠組みには乗らないほうがいいと思っています。むしろ、保険診療の枠組みに入れてしまうと、体外受精がそうであったように、本来クリニック同士が切磋琢磨して技術や知識を高め合ってきた土壌が失われてしまいます。体外受精は自由診療だからこそ、各施設が工夫を重ね、より高い成功率や新しい方法を追求することができ、日本の生殖医療は世界的にも高い水準を誇ってきました。しかし保険適用後は、制度の制約により使用できる薬剤や回数、治療方法が画一化され、自由な挑戦が困難になり、研究や技術革新の停滞が懸念されています。遺伝子検査も同じです。日々進化するゲノム科学に対応するには、柔軟に新しい技術や解釈の方法を取り入れ続けることが不可欠です。保険制度の硬直的な枠組みに押し込めてしまえば、その進歩は確実に阻害されます。だからこそ、自由診療であることが、質の高い医療を維持し、世界に通用する専門性を培っていくために必要なのです。
ーーNIPT業界には様々なクリニックが参入し、中には問題のある施設もあると聞きます。
仲田院長:悲しいことですが、この業界には闇の部分もあります。NIPTは、適切な遺伝カウンセリングや陽性だった場合のフォローアップ体制が不可欠です。しかし、検査だけして結果を渡し、「詳しいことは産婦人科に聞いてください」と丸投げするような、ビジネス優先のクリニックも残念ながら存在します。そういった施設では、確定検査もせずに安易に中絶に至ってしまうケースもあり、本来病気がなくて何の問題もなかった命が失われている可能性すらあります。当院には、そうした他のクリニックで陽性になった時のカウンセリングを断られたり、不安な思いをされたりした方が、全国からいらっしゃいます。「ここにしかないから」。そう言っていただけることが、私たちの存在価値なのだと思います。私たちはただ検査をするだけではありません。診断をつけること、そしてその先にある患者さんの人生に、最後まで責任を持つこと。 それが、利益優先のクリニックとの決定的な違いです。
ーー2025年6月からは産婦人科を併設されているそうですね。どのような変化がありましたか?
仲田院長:はい、NIPTで陽性が出た後の絨毛検査(CVS)や羊水検査といった確定検査まで、すべて当院で一貫して行える体制を整えました。これにより、患者さんからは「安心してNIPTを受けられるようになった」というお声をいただいています。実は以前、深く後悔した経験があります。他院でNIPT陽性とわかった後、羊水検査を受けて「異常なし」とされたものの、心臓に奇形が見つかった方がいました。しかし、私が関わった時点ではすでに対応できる週数が過ぎており、患者さんにはもう何の選択肢も残されていませんでした。NIPTや羊水検査は万能ではなく、限界があります。もっと多角的な情報を提供し、患者さん自身が判断できる環境を作るべきだったのではないかと感じています。この経験が、私に「NIPTから確定検査まで、すべてに責任を持てる体制を作らなければならない」と強く決意させました。この体制ができたことで、ようやく患者さんに本当の意味での安心を提供できるようになったと感じています。
ミネルバクリニックの遺伝子検査|未来を主体的に選ぶための道具
遺伝子検査と聞くと、「怖い結果を知らされるもの」と身構えてしまうかもしれません。
しかし仲田院長は、「それは未来を主体的に選ぶための道具だ」と断言しています。
遺伝子検査は運命を決めるものではない。未来をより良く生きるための「道具」
ーー遺伝子検査について、社会に一番伝えたいことは何でしょうか?
仲田院長:私が一番伝えたいのは、「遺伝子検査は、あなたの運命を決めつけるものではない」ということです。多くの方は「遺伝子検査=怖い結果を突きつけられるもの」というイメージをお持ちです。しかし、本当はその逆。遺伝子検査は、自分の未来をより主体的に、より良く生きるための「道具」だと考えています。病気のリスクを知ることは、「どうせ病気になるんだと諦める」「結果によっては子供を諦める」ためではありません。「では、どうすれば予防できるか」「どうすれば安心して生きていけるか」を考え、行動するためのスタートラインです。本来、遺伝学は人を排除するためのものではなく、誰もが自分らしく生きるための「安心の基盤」を作る学問。私は、「遺伝子検査=不安の種」という誤解を解き、「遺伝子検査=安心と納得のための道具」であることを、社会にもっと広く伝えていきたいと願っています。
ーー出生前診断の技術は、NIPTからNIPD(非侵襲的出生前遺伝学的検査)へと進化が見込まれています。この技術について、どのようにお考えですか?
仲田院長:NIPDは大きな可能性を秘めていますが、「何でも診断できる」といった過大な期待や誤解が広がることを懸念しています。現時点ではまだ技術的に難しく、応用できるのはごく一部の疾患に限られます。特に、多くの常染色体劣性(潜性)遺伝性疾患については、現状ではNIPDよりも妊娠前に保因者検査(キャリアスクリーニング)を行う方が有用です。ご夫婦が前もってリスクを知り、将来に備える上で非常に価値が高いと考えています。もちろん、技術は着実に進歩しています。NIPDを過信するのではなく、その限界を正しく理解した上で適切に運用し、将来的にはもっと多くの情報を事前に把握できるようになることが理想です。そのためには、技術の発展だけでなく、制度や倫理の枠組みを社会全体で整えていくことが不可欠だと思います。
ミネルバクリニック 仲田院長からのメッセージ
仲田院長から、来院を考えている方や遺伝子検査をするか悩んでいる方にメッセージをいただきました。

ーー先生が診療する上で心がけていることはございますか?
仲田院長:私自身も、希少な常染色体優性遺伝性疾患を抱える当事者です。妊娠・出産をした頃には、その疾患について「常染色体優性遺伝である」ということ以外、ほとんど分かっていませんでした。妊娠のたびに、子どもに遺伝するかどうかは1/2の賭け――。不安の中で過ごしていました。けれど今は、技術の進歩によって「調べること」ができる時代になっています。遺伝に関する悩みはとても深いものですが、私自身がその苦しさを体験しているからこそ、同じように悩む方に手を差し伸べたいと心から思います。どうか一人で抱え込まず、私と一緒に未来への扉を開いていきましょう。私はそのために、ここにいます。
ーー最後に、遺伝に関する悩みや不安を抱えている方々へ、メッセージをお願いします。
仲田院長:どうか一人で不安を抱え込まないでください。先ほども申し上げた通り、遺伝子検査は「怖い結果を知るためのもの」ではなく、未来を自分の手で選ぶための道具です。ミネルバクリニックは、妊娠前から妊娠中、小児期、成人期、そしてがんの予防まで、人生のあらゆるステージで「その方にとっての最善」を一緒に探し、伴走していきます。私の好きな言葉に「その先を超えていく」があります。検査を通じて不安を超え、迷いを超え、その先の人生を安心して歩んでいけるように、私たちは全力であなたをサポートします。いつでも、ご相談ください。
| 診療科目 | 出生前診断専門外来、遺伝子診療専門外来、 がん診療専門外来、セカンドオピニオン専門外来 |
|---|---|
| 住所 | 〒 107-0061 東京都港区北青山2-7-25 神宮外苑ビル1号館2階 |
| 診療日 | 月・木・金・土・日 午前 10:00~14:00(最終受付13:30) 午後 16:00~20:00(最終受付19:30) |
| 休診日 | 火・水 ※不定休があります。 ※詳しくは公式HPの”休診日のお知らせ”をご確認ください |
| 院長 | 仲田 洋美 |
| TEL | 03-3478-3768 |
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「外苑前駅」2b出口から徒歩1分 東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目駅」から徒歩9分 東京メトロ銀座線・半蔵門線「表参道駅」から徒歩11分 |